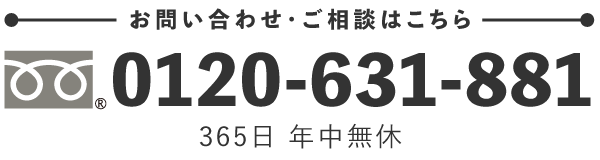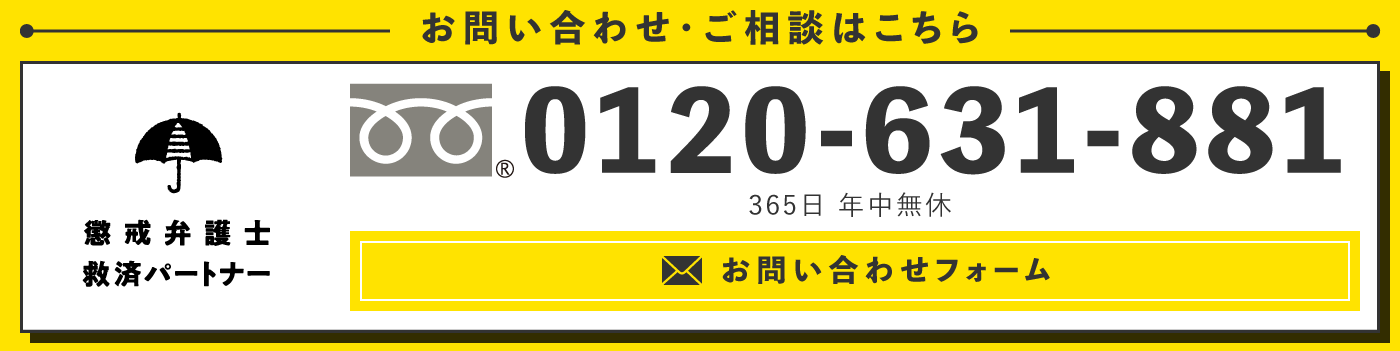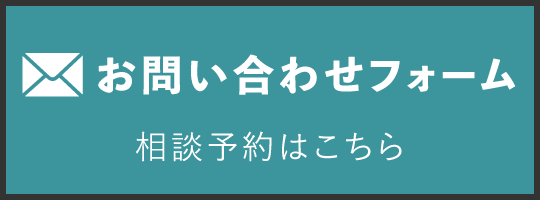Archive for the ‘懲戒事由(各論)’ Category
【弁護士が解説】保証人と主債務者の両方の代理人となることは許されるか

【事例】
X弁護士は、Aさんから貸金返還請求をされている旨の相談を受けました。見ると、Aさんを被告として訴えが提起されており、Aさん自身も金銭を借りた事実や、現時点で返済をしていないことを認めています。
ところで、この借金をするにあたり、Aさんは自身の兄のBさんを連帯保証人としていました。Aさん自身には支払い能力はなく、今後Bさんも訴えられる可能性は相当高い状況にあると思われました。Aさんからは「兄も一緒に受けてあげて欲しい」と依頼されています。
X弁護士として、Bさんの事件も受任することに問題はないでしょうか。
【解説】
今回の問題は、主債務者の代理人が、連帯保証人の代理人を兼ねることが許されるかという問題になります。主債務者と保証人の関係では、どちらかが返金すれば、その分相手方が返金を免れるという形になりますので、一方の出捐で他方が得するという関係を見ると、利益相反思想にも思われます。ただ、時効の援用や弁済の抗弁など、双方に共通する主張ができる可能性もあります。
しかし、主債務者と保証人は、求償の場面以外では「相手方」という立場にはなりません。そのため、弁護士職務基本規程28条3号が問題となり「依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件」に該当することになります。
そのため、同条の柱書にある「第三号に掲げる事件についてその依頼者及び他の依頼者のいずれもが同意した場合」には、受任をすることができることになります。
もっとも、途中で利益相反が顕在化した場合には、双方の代理人を辞任することになります。そのため、最初に委任を受ける際には、場合によっては双方辞任になる可能性を十分伝えた上、受任をする必要があります。
【弁護士が解説】依頼者との紛争についてはどのように対応すべきか?

【事例】
X弁護士は、Aさんから、貸金返還請求訴訟を起こされたとの相談を受けました。
Aさんが持ってきた訴状や証拠書類を見ると、Aさんが金銭を借りたことは比較的明らかなようでした。また、Aさんに尋ねると、現金を借りたことは事実であり、現在まで返金していないと述べました。
このような事案であったため、X弁護士は、Aさんに対して、「この事件は、争うと負けてしまう可能性が高いので、分割払いの合意などができないか和解を目指していくのがよいのではないか」と述べ、この説明に納得したAさんと委任契約を締結しました。
期日が進み、相手方の訴訟追行態度に納得ができなくなったAさんは、突如否認をしたいと言い出しました。しかし、既に自白している事実も多く、X弁護士が難しい旨を述べると、突如としてX弁護士を解任し、弁護士費用の支払いも未払いのままに音信不通となってしまいました。
このときX弁護士はどのように対応すればよいでしょうか。
【解説】
弁護士と依頼者の信頼関係が破綻し、途中で委任契約を終了させるということ自体はそう珍しくありません。仮に終了させるにしても、金銭関係をきれいに清算し、後々問題が生じない形で終了できていれば、悩みも少ないと思われます。
しかし、事例のように、突如解任され、報酬も未払いであった場合、弁護士としてどのように対応するべきか苦慮することになります。
ここで、報酬未払いを理由として民事訴訟(調停も含みます)を起こした場合、どのような問題が生じるか考えてみましょう。
通常、弁護士が委任契約を締結している以上、相手方の氏名や住所、電話番号といった基本的な個人情報は知っていると思われます。そのため、郵便を発送したり、訴状を作成することについては困難はないと思われます。
ただ、訴状を作成すると、委任契約書を証拠として提出する必要があることは当然のこと、受任していた事件の推移や、解任されるに至った経緯など、「職務上知り得た秘密」(弁護士法23条)を書面に記載することになる可能性は高いと思われます。また、民事事件の記録はだれでも閲覧可能ですので、記録を閲覧した第三者に、元々の受任事件の内容を知られることになります。
そのため、弁護士が元依頼者を訴えるということは、仮に報酬請求訴訟であったとしても、守秘義務の観点からそう簡単に肯定されるものではありません。
このような観点から、各弁護士会には紛議調停委員会などの、依頼者との紛争を解決する機関が設置されています。弁護士職務基本規程26条では「弁護士は(中略)紛議が生じたときは、所属弁護士会の紛議調停で解決するように努める。」とされており、紛議調停委員会の利用を促しています。こちらであれば、非公開であることや、開示する相手も弁護士であることなどから、守秘義務違反の問題は少ないものと思われます。
【弁護士が解説】会社の顧問弁護士をしているときに、会社の役員・従業員とはどのような関係になるのか

【事例】
X弁護士は、長年にわたり株式会社Aの顧問弁護士を務めてきており、代表取締役を含む役員らの日常の相談や、会社の経営等について相談に乗ってきた。
⑴役員パターン
しかし、あるとき、会社役員と株主の間に深刻な利害対立が生じ、役員らは株主代表訴訟を提起されるに至った。
そのため、役員らは訴訟代理人を選任する必要が生じたが、これに普段から会社のことをよく知っているX 弁護士が適任ではないかという話が持ち上がった。
⑵従業員パターン
あるとき、従業員のBが逮捕されたという報道がなされた。A社としても早急に対応する必要があったことから、X弁護士に依頼し、Bに面会してもらうこととした。
話を聞いたA社幹部らは、Bのことを思い、このままXにBの弁護人になってもらうことを考えた。
X弁護士として、これらの依頼を受任しても問題はないか。
【解説】
会社の顧問弁護士を務めている場合、弁護士職務基本規程28条2号の「継続的な法律事務の提供を約している」状態にあるということができます。そのため、「会社」を相手方とする事件を受けることは、同号に該当し、同条但書の場合(依頼者・相手方の双方の同意がある場合)を除いては、職務を行ってはならないことになります。
⑴のようなケースの場合、株主代表訴訟の役員側代理人を務めることは、仮に株主=会社であると考えると問題が生じるということになります。たしかに、株主代表訴訟は、個々の株主の直接的利益を満たすものではなく、あくまでも会社の利益を保護するための制度です。その訴訟において、役員側の代理人となることは、会社を相手方にしているのと同じ状況になりますので許されるものではありません。
しかし、会社法849条により、会社は役員側に訴訟参加することが許されています。そうすると、株主対会社・役員という構図の場合もあり得ますので、このような場合には役員の代理人となることが許されるのではないかという疑問もあります。これについては、『解説 弁護士職務基本規程(第3版)』では消極的な見解が取られています。このケースでも会社の代理人となることは問題ないものの、役員の代理人となることは利益相反の可能性が消滅しないとしています。ですので、受任を差し控える方が良いものと思われます。
⑵のケースの場合、会社が依頼者となり、従業員を弁護するというものです。従業員の起こした事件の内容が会社と全く関係ないのであれば、従業員と会社の間には何らの関係もないように思われます。
しかし、弁護士は弁護士法上の守秘義務を負っていますので、逮捕された従業員から聴取した事項については、本人が同意しない限り会社関係者に告げることができません。対して、会社から顧問弁護士として従業員の処遇について尋ねられた場合には、会社の立場から検討してしまうことになります。こうなると公平性を疑わせる状況になりますので、場合によっては問題化する可能性があります。やはり、知り合いの弁護士に依頼するなどした方が妥当であると思われます。
【弁護士が解説】相手方との交渉の際、許される言動はどの程度であるか

【事例】
X弁護士は、Aから、自身の配偶者BがCと不貞関係にあるとの相談を受けた。相談の結果、AはCに対して慰謝料請求をするということになったが、その時点でもAとBの間の婚姻関係は破綻しているとはいえなかったほか、BとCの間に不貞行為があるという証拠が具体的にある状況ではなかった。
このような状況で、X弁護士は、Cの1000万円の慰謝料を請求する旨の受任通知を送るとともに、Cの携帯電話に複数回電話をした上で、Cの勤務先にも電話をした。そして、折り返しをしてきたCに対して、1000万円の慰謝料を請求した上で、仮に応じなかった場合にはCの上司に通告する旨を伝えるなどした。
X弁護士の対応に問題はないか。
【解説】
1 弁護士の義務
弁護士である以上、法令や証拠に基づき主張をするべきなのは半ば当然です。もちろん、相談時点では事実関係が明らかではなく、当事者の一方の主張を聞いた結果、(結果的に見れば)一方的な主張となってしまうこともありますが、これはあくまでも結果論であり、やむを得ない面もあります。
ただ、明らかに証拠が不足している状況で、断定するような形で主張をするということは許されません。
今回のX弁護士の例の場合、婚姻関係の破綻がない以上、不貞慰謝料請求をすることになり、不貞の証明をする必要があります。ただ、Aの一方的な主張のみであり、他に根拠がないという状況では、慰謝料請求が認められる可能性はほとんどありません。せめて、婚姻関係が破綻していないのであれば、Bから話を聞き、不貞の事実を確認することは可能であったはずです。にもかかわらず、この段階で不貞慰謝料請求権の存在を前提としてCに交渉していくことは不適切と評価される可能性があります。
2 不安をあおる言動
さて、X弁護士は、Cに対して1000万円の慰謝料請求を行っています。
婚姻関係が破綻したという事例での慰謝料請求であったとしても、この金額が裁判所によって認定されるとは通常考えられません。もちろん、算出方法等によって金額が高めになったり低めになったりすることはあり得ますが、今回の金額はあまりにも高額です。このような高額の請求を受けたCからすれば、相当不安を感じるはずです。
また、X弁護士は何度もCに電話をしています。もちろん交渉のために電話をすることは否定できませんが、あまりにも回数が多いようであれば、着信履歴の状況からしてもCは不安を感じると思われます。
弁護士として相手方と交渉をすることは当然ですし、一方の代理人の立場として交渉をする以上、客観的な事実や、当然予想される帰結(たとえば「裁判になったら、弁護士さんを通常雇うことになり、お金と手間と時間がかかります」など)を告げることには問題がないと思われますが、それ以上のことについては余程の証拠がなければ告げること自体も危険であると言えます。
3 脅迫的言辞
最後に、X弁護士は、Cの勤務先の上司に通告する旨を述べています。Cの行為は当然私生活上の行為であり、Cの仕事とは関係ありません。にもかかわらずこれを職場に告げるというのは、脅迫的な下農であり、弁護士として許されるようなものではありません。
このような脅迫的言辞は、弁護士として当然認められるものではありませんし、悪質なものであると認定されます。もちろん、事実としてそういうことになるということを告げることは問題ありません。たとえば、(今回の事案では問題がありそうですが)「慰謝料の支払いを裁判所に命じられることになり、それを支払わなかった場合には、給与について裁判所から差押えの命令が会社に行き、会社に裁判を起こされたことが分かってしまう」というのはあり得る結末の1つであり、弁護士であれば通常想定する手段だとは思いますが、一般の方からすると脅されているように感じると思われます。このような言動まで脅迫であると認定されることはないと思われますが、それでも表現や言い方などの点には注意を要します。
弁護士同士でも注意が必要ですが、そうでない方を相手に交渉を行う場合、弁護士の世界の常識が当然通用するわけではありません。表現や言葉遣いには十分注意をして交渉を行う必要があります。
【弁護士が解説】接見室内で被疑者・被告人に電話をさせるとどのようになるか

【事案】
X弁護士は、Aの国選弁護人として選任され、Aが逮捕されているB警察署で接見を行っていた。
Aはいわゆる特殊詐欺で逮捕され、他にも共犯がいると考えられるほか、接見等禁止決定が付されていた。
面会中、AはXに対して、「先生は面会室に携帯電話を持ってきていますよね。俺の彼女とどうしても話がしたいから、先生が電話をかけて、アクリル板越しに電話機を近づけて、電話で話をさせてくれませんか」と依頼を受けた。
このような依頼を受けて問題はないだろうか。
【解説】
1 面会室内での電子機器の利用について
警察署や拘置所で接見を行う際、携帯電話を預けるように言われることがあるほか、パソコンなどの電子機器を利用する際には事前に申し出るように言われることがあります。また、このような指示に従わなかった場合、面会の中が注されるといったケースもあるようです。
このような取り扱いに対し、日弁連は一貫して対抗する姿勢を見せていると思われます。確かに、現在刑事事件では電子データが証拠開示されることも多いところ、仮に電子機器の利用が禁止されるとすれば、電子データを示しながらの本人と話すことができなくなってしまい、防御上の不利益は極めて大きいものとなってしまいます。その他にも、現在はパソコンでメモを取ることもそう珍しいことではありませんから、電子機器の利用一切を禁止しようとする流れには対抗する必要があります。
2 面会室内での電話の利用
しかし、電話(LINE通話なども含みます)機能を使用するという話になると、問題の争点が変わってきます。
弁護士との間では秘密交通権が保障されていますが、これはあくまでも被疑者・被告人と弁護士の間で防御を行うために認められた権利です。そのため、被疑者・被告人と弁護士以外の人物との間での秘密交通が認められているわけではありませんから、弁護士が外部へ電話をかけ、被疑者・被告人とその者を会話させるというようなことは認められません。
今回の事例の場合、Aは特殊詐欺で逮捕されており、他に共犯者がいるということが容易に推察されます。Aが彼女であると称する人物が本当に彼女であるかどうかも分かりませんし、仮に彼女であったとしても事件関係者ではない保証はありません。そうすると、弁護士が罪証隠滅に加担することになる可能性もあります。
また、今回のAには接見等禁止決定が付されています。弁護士以外の者とは面会等をさせないという状態ですから、仮に会いに来たとしても彼女は面会できない状態です。そのような状態にある被疑者・被告人と電話をさせるというのは、接見等禁止決定の趣旨にも大きく反してしまいます。
ですので、仮にこのような依頼があった場合、X弁護士は必ず断らなければなりません。また、これに応じてしまった場合には、業務停止以上の重い処分が予想されます。最近でも類似のケースで処分を受けていることがありますので、注意を要します。
【弁護士が解説】利益相反規定に直接は当てはまらないような場合に受任をすることは可能か
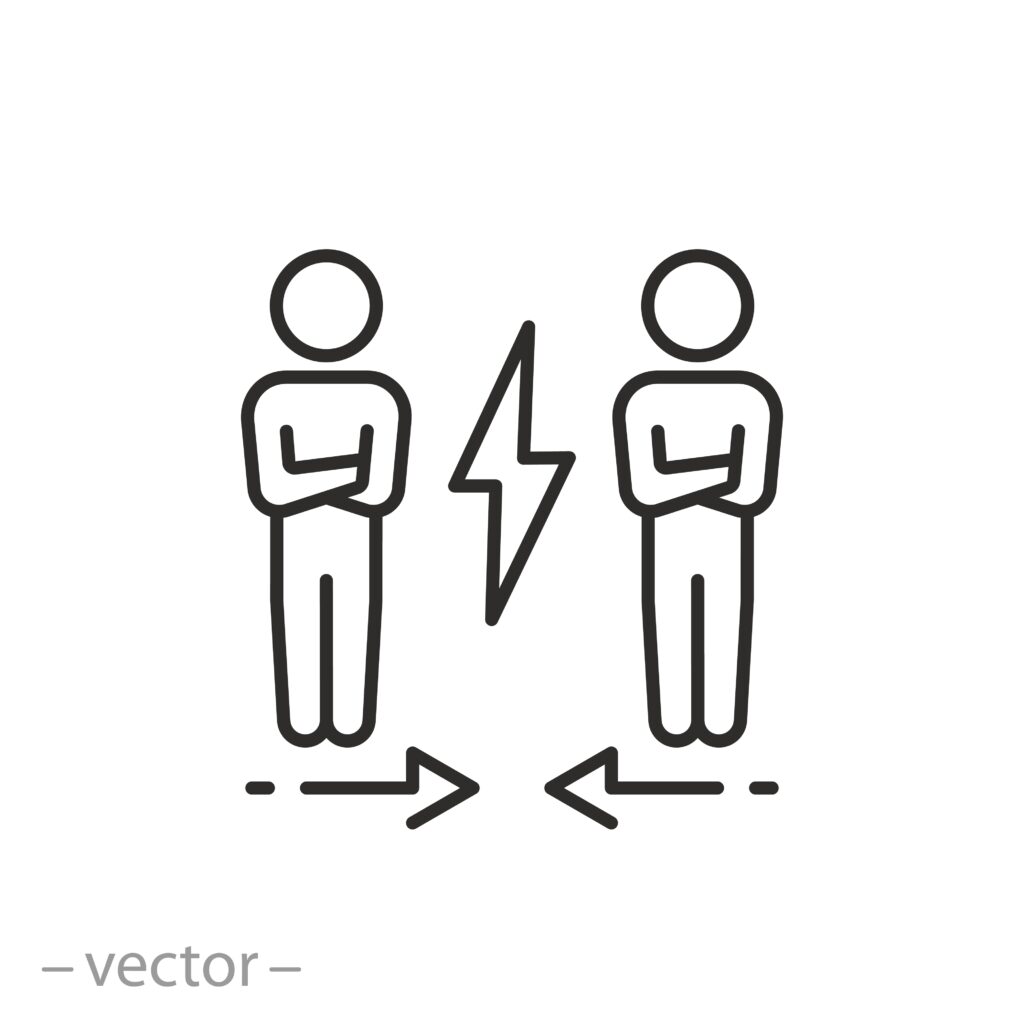
【事例】
X弁護士は、亡Aの遺産相続に関して遺言執行者に選任され、遺言執行を終えた。
ただ、その遺産の中にあった不動産について、Aの相続人のBとCの間で対立があり、Aの遺言上はBが相続するということになっていたのでXもその通り手続きを進め、登記上はBが所有者となったのだが、実際にはCが占有を継続しているような状況となった。
X弁護士は、遺言執行が終了した後、Bから「先生、Cがまだ建物を占拠しているのは納得できないので、先生が私の代理人となってCを訴えてください」との依頼を受けた。
そこで、X弁護士は、Bを代理して、Cに対して明け渡し訴訟を提起した。
【解説】
X弁護士が最初に請け負っていた事件は、遺言執行であり、依頼者はいうなれば亡Aでした。しかし、遺言執行者は特定の相続人の代理人というわけではありませんので、相続人間では公平であるべきです。
実際、東京高判平成15年4月24日によると「遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の権利義務を有し(民法一〇一二条)、遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない(同一〇一三条)。すなわち、遺言執行者がある場合には、相続財産の管理処分権は遺言執行者にゆだねられ、遺言執行者は善良なる管理者の注意をもって、その事務を処理しなければならない。したがって、遺言執行者の上記のような地位・権限からすれば、遺言執行者は、特定の相続人ないし受遺者の立場に偏することなく、中立的立場でその任務を遂行することが期待されているのであり、遺言執行者が弁護士である場合に、当該相続財産を巡る相続人間の紛争について、特定の相続人の代理人となって訴訟活動をするようなことは、その任務の遂行の中立公正を疑わせるものであるから、厳に慎まなければならない。」とされており、中立性が要求されています。
本事例と同様の事例において、戒告の処分とした例があります。遺言執行者としての任務が終了したからといって直ちにどのような事件でも受任可能になるというわけではなく、特定の相続人に偏ったものではないかどうかを検討したうえで、弁護士の公平さ(弁護士職務基本規程第5条)に反しないかを検討するべきであると言えます。形式的には利益相反の規程に反しませんが、注意を要します。
【弁護士が解説】弁護士が受任をしてはいけない事件にはどのようなものがあるか
【事例】

X弁護士は、A株式会社の顧問弁護士を長らく務めており、会社の代表取締役Bからの信任も厚かった。
ある日、X弁護士のもとへ、Bから「大変だ。うちの従業員が何かをして逮捕されたらしい。先生が弁護活動してもらえませんか」という連絡があり、実際に警察署に行ってみると、A社に勤務しているCが盗撮の疑いで逮捕されていた。Cに話を聞き、弁護人をどうするのか尋ねたところ、社長の意向に従うということであったので、そのままXがCの弁護人となることになり、AとXの間で委任契約が締結されることとなった。
1 X弁護士として気を付けるべきことはなんでしょうか。
2 後にA社において、Cを懲戒処分とするべきかの議論が行われました。Xのところへも、Bから「C君について、懲戒解雇相当だと思うのが、どうだろう」という質問がありました。Xとしてはどのように対応するべきでしょうか。
【解説】
刑事事件の被疑者、被告人の方に、勤務先の顧問弁護士が面会を行い、そのまま弁護人として選任されるということはそれほど珍しくありません。しかし、注意すべき点があります。
1 守秘義務違反
まず、弁護士には弁護士法上の守秘義務が課せられます。弁護士職務基本規程では「依頼者について」という文言となっていますが、一般的な解釈としてはこの対象は限定されていません。
今回でいえば、委任契約者はBということになりますが、基本的に秘密にしたい事項が多いのはCとなります。また、委任契約の当事者でなかったとしても、XはCの弁護人となりますので、Cに関する秘密は守秘義務の対象となります。
そうすると、Cの秘密は、たとえ委任契約を締結しているのがBであったとしても、Bに対しても口外してはならないということになります。
会社の顧問弁護士が従業員の事件を受けること自体は否定されるものではありませんが、守秘義務の点が問題となりますので注意が必要です。特に、このようなケースでは、C自身が「お金を払ってもらっているのだから話をしなければならない」と勘違いしている可能性も相応にあります。ですので、Cと面会する際には、守秘義務の存在や会社に伝えていい範囲などを十分に確認しておく必要があります。
2 利益相反
Cの性的姿態等撮影被疑事件の弁護人であったXですが、今度はCに懲戒解雇の話が持ち当たっています。
Cの刑事事件と、Cを解雇するという話では、当事者は同じCではあるものの、事件の種類や手続きは全く異なります。このような場合、Xは後の事件である解雇に関わってよいのでしょうか。
弁護士法25条及び弁護士職務基本規程27条、28条には、職務を行い得ない事件が記載されています。いわゆる「利益相反」に関する規制です。
弁護士法25条1項は「相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件」を受任することを禁じています。
今回の事例で見ると、X弁護士は、①A社の顧問弁護士②Cの弁護人の順番で受任をしていますので、後から出てくるのはCの事件です。しかし、Cを解雇するかどうかという問題は、X弁護士がCの弁護人になってから生じた問題であると言えます。そうすると、契約の順番とは反対となりますが、「Cの弁護人であったXが、Cの解雇について助言できるか」という問題が設定されることになります。
Cの解雇に関する問題の「相手方」は、Cを指しています。ただ、解雇という労働問題と、刑事事件は全く異なる手続きですので、一見すると受任可能なように見えます。しかし、過去の日弁連の決定の中には、事件の同一性は、単なる訴訟物の同一等のみで判断するのではなく、実施的な判断するべきであることが指摘されています。
Cの刑事事件もCの解雇も、いずれもCが盗撮をしたことに端を発しています。そうすると、事実上事件は同一であるといえ、Cの弁護人であったXは、Cの解雇に関する事件について関与しない方が適切であると考えられます。
【弁護士が解説】共犯者双方の弁護人を引き受けるとどのような問題が生じるか
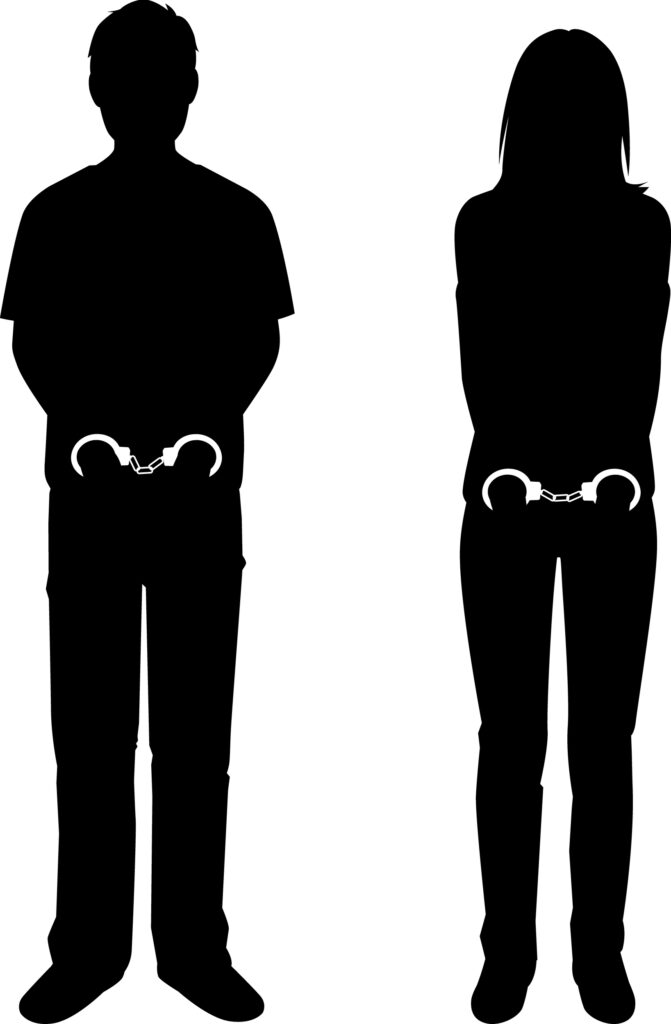
【事例】
X弁護士は、ある窃盗事件を起こしたAから私選の刑事弁護の委任を受け、弁護人として活動していた。窃盗事件の内容は、Aが別の共犯者Bと共謀してカードショップに忍び込み、高価なカードを盗むというものであった。
この事件でAは逮捕されていたが、同時にBも逮捕されているようであった。また、報道によるとAもBも両方とも事件について認めている様子であった。
AとBは元々地元の先輩後輩の間柄であり、AはBの先輩であった。本件事件についても、AがBを誘い、分け前を分配するということでBはしぶしぶ応じるような形で現場についてきていた。
ある日X弁護士がAの面会に行くと、Aから「Bも逮捕されていると聞いている。Bは自分の後輩だし、もとはと言えば自分が誘ったようなものだから、自分が迷惑をかけてしまっている。お金については自分が負担するので、先生がBの弁護士もやってください」と依頼された。
X弁護士はこの依頼に応じるべきであろうか。
【解説】
今回は、共犯事件において、共犯者相互の弁護人になることができるのかという問題となります。
弁護士法や弁護士職務基本規程では、同時に複数人の弁護士となることについて「利益相反」の規定があります。ただ、たとえば弁護士法25条1号では「相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件」のような定め方をしており、ある事件において依頼者と相手方と双方を受けることなどは禁じていますが、刑事事件共犯者相互についてどのように考えるのかは明らかではないところもあります。
そもそも、刑事訴訟規則29条5項では「被告人又は被疑者の利害が相反しないときは、同一の弁護人に数人の弁護をさせることができる。」と定めており、1人の弁護士が複数人の弁護をすることが想定されています。ただ、こちらでも「利害が相反しないとき」という条件が付されています。
それでは、刑事の場合に「利害が相反する」とはどのような場合を指すのでしょうか。
典型的に問題になりそうなのは、共犯者の一方は認め、片方は否認というケースです。認め事件と否認事件では、事件への対応方針も大きく異なり、特に認めている共犯者の方が否認している共犯者についての関与を自白するような場合には、明らかに一方の行動が他方に不利になっていると言えます。
次に、共犯者双方が認めていたとしても、その間に上下関係や主従関係がある場合です。一方が主導的な役割を果たし、他方が従属的な場合、従属的な者の弁護人となった場合には当然主犯に従っただけであるという弁護活動を展開します。ただ、これは主犯に責任を多く負担させるという主張ですので、主犯から見れば不利益になっているとも言えます。
それでは、両方とも否認をする場合はどうでしょうか。この場合、否認の内容にもよります。たとえば、お互いが「相手方が1人でやった」というような主張であれば利益相反は明らかですが、双方黙秘の場合には表面上は利益相反は明らかではありません。
一般的に、複数人の弁護人を同時に引き受けることには慎重であるべきとされています。それは、弁護活動が時間の経過によりさまざまな変化を見せる以上、たとえ現時点で利益相反の問題が生じていなくとも、将来的に利益相反となる可能性は常に存在するからです。そして、いったん利益相反が顕在化してしまうと、どちらか一方の弁護人を辞任するだけでは足りず、双方の弁護人を辞任するべきであると考えられているため、どちらの依頼者にも迷惑をかけることになってしまいます。
今回の事例では、AとBの間に主従関係があるようです。また、Bの弁護士費用はAが負担すると述べています。このようにお金をAが負担していると、BとしてはAに反抗するような主張をしにくくなる可能性があります。以上のような理由から、X弁護士としては受任を差し控える方が好ましいと言えます。
【弁護士が解説】国選弁護人として被疑者・被告人の家族から受け取ってもいいものとは?

【事例】
X弁護士は、Aさんの被疑者国選弁護人に選任されました。Aさんの留置されているB警察署は、X弁護士の事務所からも相当遠く、不便なところにありました。
Aさんは窃盗で逮捕・勾留されていたため、示談をする必要性があると考えたX弁護士は、示談金の用意をAさんに依頼しました。
最終的には示談が成立し、Aさんは不起訴により釈放されることとなりました。
このとき・・・
⑴示談金としてAさんの家族から現金を預かった。これは預かって問題ないだろうか。
⑵遠くのB警察署へ接見に行くことを不憫に思ったAさんの家族が、「どうせ私たちもAの接見に行きますので、一緒に車で送ってあげますよ」と提案してきた。X弁護士は車に乗っても問題ないだろうか。
⑶事例と異なり、仮にAさんが起訴されたとして、公判請求証拠の一部をコピーし、これをAさんに差し入れた。公判請求証拠のコピー代をAさんに請求することは問題ないだろうか。
【解説】
弁護士職務基本規程49条第1項は、「弁護士は、国選弁護人に選任された事件について、名目のいかんを問わず、被告人その他の関係者から報酬その他の対価を受領してはならない。」としています。
国選弁護人への報酬は法テラスを経由して国庫から支払われているので、この報酬以外を弁護士が受領することは国選弁護人の職務の公正さを疑わせ、ひいては国選弁護制度の公正さを害すると考えられています(「解説 弁護士職務基本規程第3版」142頁)。
そのため、国選弁護人は「対価の受領」を禁止されているのですが、反対に「対価」でなければ受領してよいようにも思えます。
⑴の事例は、あくまでも示談金としてお金を預かったのみです。これは私選や国選を問わず弁護士の手元に残るお金ではなく、最終的には被害者に支払われるお金ですから、これは当然「対価」には当たりません。ただ、端数などで余りが出た場合には、その余りを受領することは当然禁止されますので、返金をしなければなりません。
⑵は、車での移動という便益です。受領を禁止されているものは「対価」ですので、現金や有価証券などの金銭的な価値のあるものだけではなく、利益のようなものも含まれます。
問題は「名目のいかんを問わず(中略)報酬その他の対価」の受領を禁じていることをどのように解釈するかというところにあります。弁護活動の「対価」を受領することが問題となる場合、対価とはならない「実費」部分をどのように考えるかという問題が生じます。「名目のいかんを問わず」ということを強調するとたとえ実費であっても受領することが禁じられるという方向に解釈することとなります。反対に「報酬」が問題であると考えた場合、実費部分は受領することも許容されるという理解もあり得るところです。
⑵については、交通費相当額部分が問題となります。接見を行うと日当が法テラスから支払われますが、遠距離であるという事情がなければ、交通費という名目は別に支払われません。ただ、交通費込みで支払われていると考えると、既に法テラスから交通費部分の支払いを受けていることになりますから、重ねて交通費部分を関係者から受領することは問題となります。国選弁護士の報酬についてのQ&Aを見ると「算定基準では、近距離の交通費については基礎報酬で賄うことを前提」とすると記載されていますので、交通費部分も受領しているという考え方になるのではないかと思われます。ですので、⑵は断ることが適切であると考えられます。
対して⑶は、現在の国選弁護人の報酬体系の中では支払われない費用についての項目です。これについて実費相当額を受け取るべきかどうかが問題となりますが、厳しい考え方をとると、このような費用も受領することは禁じられるということになります。ただ、反対に弁護活動の充実ということであれば公判請求証拠を差し入れることは認められるべきでしょうし、この費用を受け取ったからといって弁護士が得をするような事態は生じません。慎重に検討し、金額の多寡なども踏まえ検討することが妥当であろうと思われます。また、事前に単位会の刑事弁護委員会やメーリングリストなどで尋ねるのも一つの手段です。
【弁護士が解説】法令調査義務違反をした場合どのような処分となるのか

【事例】
X弁護士は、Aから労働トラブルについての相談を受けたが、その際同僚からの名誉毀損行為についての相談も受けた。
X弁護士としては、Aが受けた被害が、公衆の面前でAの様子などをバカにするような内容であったため、名誉毀損罪は成立するであろうと考えた。そこで、Aに対して慰謝料の請求ができるということのほか、刑事告訴が可能であるということを伝えました。なお、この名誉毀損発言があった時期は、令和5年4月3日、相談を受けた日は令和6年4月3日であるとします。
X弁護士の行為にはどのような問題があるのでしょうか。
【解説】
前提として、X弁護士の法的判断は正しく、名誉毀損罪は成立するとします。
名誉毀損罪は、親告罪となっています(刑法232条)。そのため、告訴がなければ公訴を提起することはできません。
しかし、「親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。」とされています。そのため、名誉毀損罪においては、公訴時効とは別に告訴できる期間に制限があるということになります。
冒頭の設例では、Aが犯人を知ったのは、当然同僚であるため事件日です。しかし、Aが相談に訪れたのは、事件から1年後になっています。そのため、親告罪の告訴期限を経過しており、現時点から受任したとしても、告訴をすることはできません。ですので、X弁護士はAに対して誤った説明をしたことになります。
弁護士職務基本規程第37条1項によると、「弁護士は、事件の処理に当たり、必要な法令の調査を怠ってはならない。」とされています。その他に、同規程7条には「弁護士は、教養を深め、法令及び法律事務に精通するため、研鑽に努める。」とされているほか、弁護士法2条にも「弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。」とされています。
このように、弁護士は法律の専門家として、法令に精通し、法律を調査する義務を負っています。なお、弁護士職務基本規程37条2項は「弁護士は事件の処理に当たり必要かつ可能な事実関係の調査を行うように努める。」となっており、事実調査については努力義務の規程となっていますが、1項は義務づけられているところに違いがあります。
X弁護士は、法律的に誤った回答をしていますので、この法令調査義務に違反していると考えられます。事案の趨勢や勝ち負け等といったことは法令に基づくものではありませんので、見通しが誤っていたこと等はこの規程との関係では問題となりません。しかし、X弁護士のように、法律上不可能(かつ不変)な回答をしてしまったり、上訴等の期限を徒過してしまったような場合には、純粋に法律上の判断でありかつ裁量の余地もないようなものなので法令調査義務違反となってしまいます。
このような場合、戒告以上の処分となる可能性が否定できません。特に、今回のような刑法犯、親告罪の告訴というような比較的単純な法律についての問題であれば、その分処分が重くなってしまいます。
このような事態に陥った場合には、すぐに依頼者に正しい法律の解釈を伝えたうえで、場合によっては委任契約の解除や依頼者との和解等の手段をとる必要があります。また、そもそもこのような事態に陥らないためには、日常的に接する分野以外については直ちに回答せず法令調査をしてから改めて回答する旨伝える等、慎重に対応する必要があります。
弁護士において、法令調査義務は相当重い義務です。ただ、弁護士の信用の源泉となっていますので、処分としても比較的重いものが下されます。依頼者からの懲戒請求があったり、紛議調停申し立てがあったような場合には、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
« Older Entries Newer Entries »