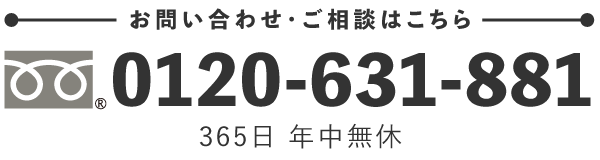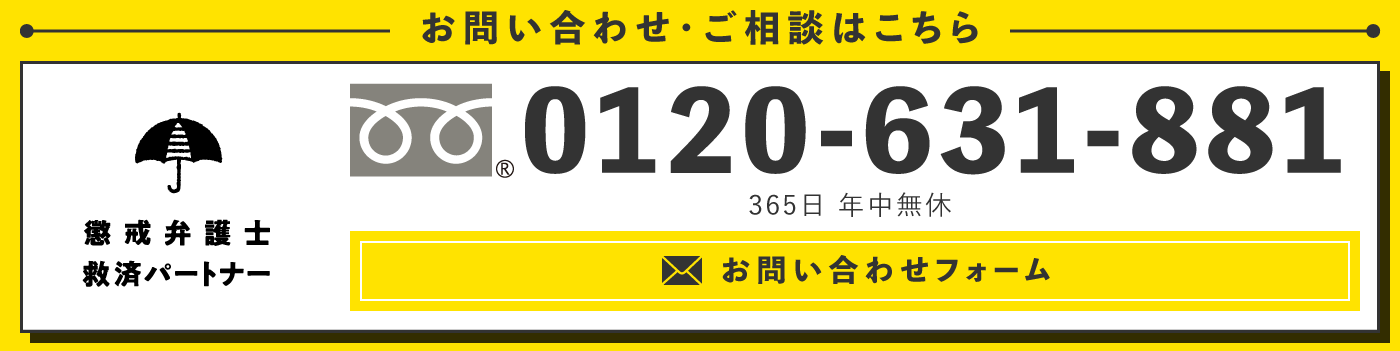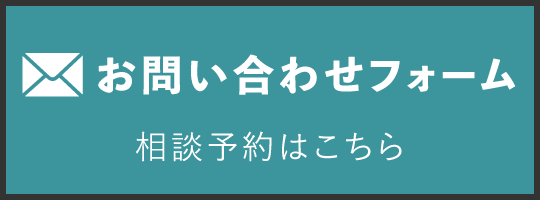Archive for the ‘未分類’ Category
【弁護士が解説】共犯者双方の弁護人を引き受けるとどのような問題が生じるか
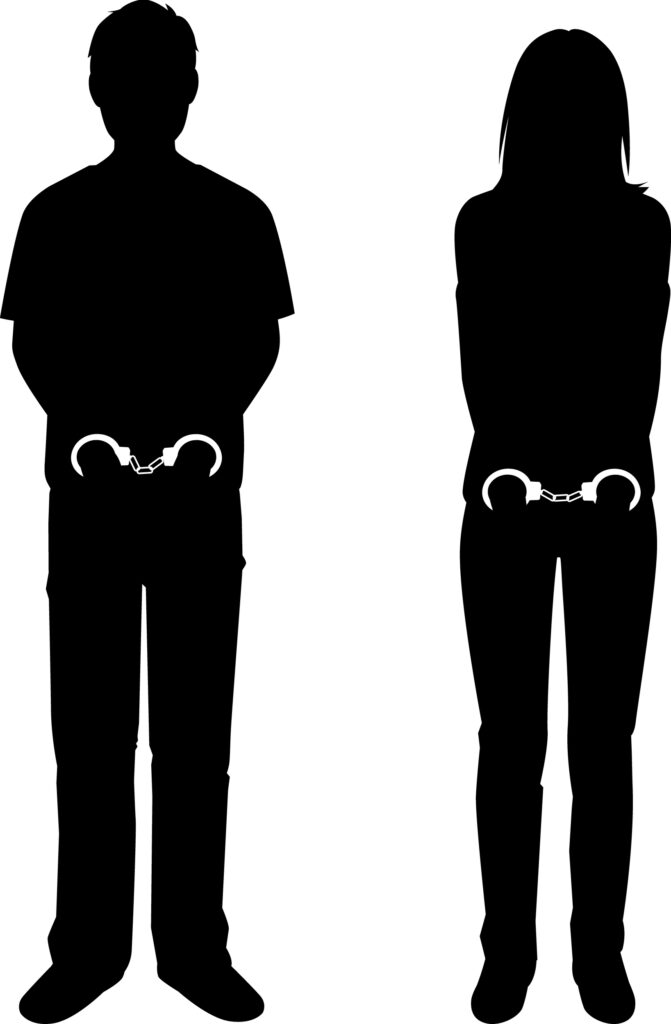
【事例】
X弁護士は、ある窃盗事件を起こしたAから私選の刑事弁護の委任を受け、弁護人として活動していた。窃盗事件の内容は、Aが別の共犯者Bと共謀してカードショップに忍び込み、高価なカードを盗むというものであった。
この事件でAは逮捕されていたが、同時にBも逮捕されているようであった。また、報道によるとAもBも両方とも事件について認めている様子であった。
AとBは元々地元の先輩後輩の間柄であり、AはBの先輩であった。本件事件についても、AがBを誘い、分け前を分配するということでBはしぶしぶ応じるような形で現場についてきていた。
ある日X弁護士がAの面会に行くと、Aから「Bも逮捕されていると聞いている。Bは自分の後輩だし、もとはと言えば自分が誘ったようなものだから、自分が迷惑をかけてしまっている。お金については自分が負担するので、先生がBの弁護士もやってください」と依頼された。
X弁護士はこの依頼に応じるべきであろうか。
【解説】
今回は、共犯事件において、共犯者相互の弁護人になることができるのかという問題となります。
弁護士法や弁護士職務基本規程では、同時に複数人の弁護士となることについて「利益相反」の規定があります。ただ、たとえば弁護士法25条1号では「相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件」のような定め方をしており、ある事件において依頼者と相手方と双方を受けることなどは禁じていますが、刑事事件共犯者相互についてどのように考えるのかは明らかではないところもあります。
そもそも、刑事訴訟規則29条5項では「被告人又は被疑者の利害が相反しないときは、同一の弁護人に数人の弁護をさせることができる。」と定めており、1人の弁護士が複数人の弁護をすることが想定されています。ただ、こちらでも「利害が相反しないとき」という条件が付されています。
それでは、刑事の場合に「利害が相反する」とはどのような場合を指すのでしょうか。
典型的に問題になりそうなのは、共犯者の一方は認め、片方は否認というケースです。認め事件と否認事件では、事件への対応方針も大きく異なり、特に認めている共犯者の方が否認している共犯者についての関与を自白するような場合には、明らかに一方の行動が他方に不利になっていると言えます。
次に、共犯者双方が認めていたとしても、その間に上下関係や主従関係がある場合です。一方が主導的な役割を果たし、他方が従属的な場合、従属的な者の弁護人となった場合には当然主犯に従っただけであるという弁護活動を展開します。ただ、これは主犯に責任を多く負担させるという主張ですので、主犯から見れば不利益になっているとも言えます。
それでは、両方とも否認をする場合はどうでしょうか。この場合、否認の内容にもよります。たとえば、お互いが「相手方が1人でやった」というような主張であれば利益相反は明らかですが、双方黙秘の場合には表面上は利益相反は明らかではありません。
一般的に、複数人の弁護人を同時に引き受けることには慎重であるべきとされています。それは、弁護活動が時間の経過によりさまざまな変化を見せる以上、たとえ現時点で利益相反の問題が生じていなくとも、将来的に利益相反となる可能性は常に存在するからです。そして、いったん利益相反が顕在化してしまうと、どちらか一方の弁護人を辞任するだけでは足りず、双方の弁護人を辞任するべきであると考えられているため、どちらの依頼者にも迷惑をかけることになってしまいます。
今回の事例では、AとBの間に主従関係があるようです。また、Bの弁護士費用はAが負担すると述べています。このようにお金をAが負担していると、BとしてはAに反抗するような主張をしにくくなる可能性があります。以上のような理由から、X弁護士としては受任を差し控える方が好ましいと言えます。
【弁護士が解説】法令調査義務違反をした場合どのような処分となるのか

【事例】
X弁護士は、Aから労働トラブルについての相談を受けたが、その際同僚からの名誉毀損行為についての相談も受けた。
X弁護士としては、Aが受けた被害が、公衆の面前でAの様子などをバカにするような内容であったため、名誉毀損罪は成立するであろうと考えた。そこで、Aに対して慰謝料の請求ができるということのほか、刑事告訴が可能であるということを伝えました。なお、この名誉毀損発言があった時期は、令和5年4月3日、相談を受けた日は令和6年4月3日であるとします。
X弁護士の行為にはどのような問題があるのでしょうか。
【解説】
前提として、X弁護士の法的判断は正しく、名誉毀損罪は成立するとします。
名誉毀損罪は、親告罪となっています(刑法232条)。そのため、告訴がなければ公訴を提起することはできません。
しかし、「親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。」とされています。そのため、名誉毀損罪においては、公訴時効とは別に告訴できる期間に制限があるということになります。
冒頭の設例では、Aが犯人を知ったのは、当然同僚であるため事件日です。しかし、Aが相談に訪れたのは、事件から1年後になっています。そのため、親告罪の告訴期限を経過しており、現時点から受任したとしても、告訴をすることはできません。ですので、X弁護士はAに対して誤った説明をしたことになります。
弁護士職務基本規程第37条1項によると、「弁護士は、事件の処理に当たり、必要な法令の調査を怠ってはならない。」とされています。その他に、同規程7条には「弁護士は、教養を深め、法令及び法律事務に精通するため、研鑽に努める。」とされているほか、弁護士法2条にも「弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。」とされています。
このように、弁護士は法律の専門家として、法令に精通し、法律を調査する義務を負っています。なお、弁護士職務基本規程37条2項は「弁護士は事件の処理に当たり必要かつ可能な事実関係の調査を行うように努める。」となっており、事実調査については努力義務の規程となっていますが、1項は義務づけられているところに違いがあります。
X弁護士は、法律的に誤った回答をしていますので、この法令調査義務に違反していると考えられます。事案の趨勢や勝ち負け等といったことは法令に基づくものではありませんので、見通しが誤っていたこと等はこの規程との関係では問題となりません。しかし、X弁護士のように、法律上不可能(かつ不変)な回答をしてしまったり、上訴等の期限を徒過してしまったような場合には、純粋に法律上の判断でありかつ裁量の余地もないようなものなので法令調査義務違反となってしまいます。
このような場合、戒告以上の処分となる可能性が否定できません。特に、今回のような刑法犯、親告罪の告訴というような比較的単純な法律についての問題であれば、その分処分が重くなってしまいます。
このような事態に陥った場合には、すぐに依頼者に正しい法律の解釈を伝えたうえで、場合によっては委任契約の解除や依頼者との和解等の手段をとる必要があります。また、そもそもこのような事態に陥らないためには、日常的に接する分野以外については直ちに回答せず法令調査をしてから改めて回答する旨伝える等、慎重に対応する必要があります。
弁護士において、法令調査義務は相当重い義務です。ただ、弁護士の信用の源泉となっていますので、処分としても比較的重いものが下されます。依頼者からの懲戒請求があったり、紛議調停申し立てがあったような場合には、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
【弁護士が解説】委任契約書の不作成はどのような処分となるのか

【事例】
X弁護士は、高校時代からの同級生であるAから債務整理の依頼を受けました。
X弁護士としては、無償で債務整理をするわけではないものの、旧来の友人であるAからの依頼であることから、堅いことはしたくないと考え、委任契約書を作成せず、現金を預り、委任状を作成しました。
X弁護士の行為に問題はないでしょうか。
【解説】
弁護士職務基本規程30条によれば、「弁護士は、事件を受任するに当たり、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。」とされています。そのため、基本的に事件を受任する場合には委任契約書を作成しなければなりません。
ただし、委任契約書を作成しなくてもよい場合もあります。
1つ目は「委任契約書を作成することに困難な事由があるとき」です。この場合、事由が止んだ後作成しなければなりませんが、当面は作成しなくてもよいことになります。どのような場合が「困難な事由」であるかについて特段の解説などは付されていませんが、たとえば病院に入院中でプライバシーが確保できない場合などが考え得ると思われます。
2つ目は、「法律相談、簡易な書面の作成」の場合です。簡単なものである場合には、その場で業務が終了してしまい、報酬も支払われると考えられるので契約書の作成が免除されています。ただ、書面の作成でも複数回の打ち合わせが必要となるもの等の場合には「簡単な」と評価されない可能性がありますので注意が必要です。
3つ目は「顧問契約その他継続的な契約に基づくもの」です。継続的な依頼関係があれば、あえて個別の契約を作成しなくてよいということに基づきます。ただし、顧問契約の対象から外れるようなことを行う場合には、委任契約書の作成を要すると思われます。
いずれにしても「合理的な理由」があれば委任契約書を作成しなくてもよいとされていますが、『解説 弁護士職務基本規程』に明示されているように、旧知の間柄である場合には委任契約書の作成義務は免除されないとされています。ですので、今回のX弁護士の場合には委任契約書の作成義務があることになります。
その上で、契約書作成義務違反に対する処分ですが、弁護士報酬等が明示されるべき契約書作成義務の違反は比較的問題のある違反類型であるとされているようです。ただ、委任契約書を作成しない事例は、比較的期の上の弁護士にみられることや、委任契約書作成義務違反のみで処分を受けることは多くなく、何か他の義務違反も付随している例が多いこともあって、単発でどのような処分になるかは明確ではありません。
ただ、委任契約書作成は基本的な義務ですので、この義務に違反している場合にはほかにも何らかの違反を犯している可能性が高いとも言えます。そのような場合には戒告や業務停止といった処分も十分ありうるところです。
委任契約書の作成が免除されている場合であっても、委任契約書の作成を禁じられているわけではありません。委任契約書であるかどうかは書面の標題のみで決まるものではないので、契約書作成に迷った場合には安全策として何らかの書面を用意しておいた方が良いと思われます。
【弁護士が解説】刑事弁護活動中に被疑者・被告人から依頼をされた場合にはどのように対応すればよいか

【事例】
X弁護士は、窃盗で逮捕、勾留中のAの弁護人です。
ある日、X弁護士が接見に行くと、Aから次のようなことを言われました。X弁護士としてはどのように対応するとよいでしょうか(各設定は独立です)。
①Aから、「実は自分は真犯人ではなく、本当の犯人はBなのだが、Bには義理もあるし、今後もあるから自分が犯人だということで裁判を受けたいと思う」と言われた場合
②Aから、「示談金が必要になるのだが、身寄りもないし、自分の持っているキャッシュカードを先生に渡して、暗証番号も伝えるので、それで示談金を引き出してきて欲しい」と言われた場合
③Aから、「自宅に猫がいるので、猫に毎日餌やりに行って欲しい。」と言われた場合
④現行犯逮捕の事案であり、証拠上もAが犯人であると考えるのが合理的な事件であるが、Aから
犯人性を否認して争って欲しいと言われた場合
⑤保護観察付執行猶予中のAから、再度の執行猶予を付けて欲しいと言われた場合
【解説】
身体拘束中の被疑者、被告人からは様々な依頼を受けることがあります。ご家族など第三者の協力が期待できるような状況であれば協力をしてもらうことになりますが、そうでない場合には弁護人がある程度までは対応することとなります。それではどこまで弁護人が対応するべきなのか、また対応してはいけないと考えられるのはどのようなことなのか、事例ごとに検討していきます。なお、今回は国選であるか私選であるかを明記していません。私選であれば最終的に進退窮まれば辞任をするという方法がありますが、国選弁護人の場合にはそうもいきません。国選弁護人でこのような問題に直面した場合、メーリングリストや単位会の刑事弁護委員会に相談するなど、かならず1人で対応しないようにすることが肝要です。
①いわゆる身代わり犯人の問題です。身代わり犯人を立てること自体、犯人隠避罪に該当するものですので、まずはその点について本人に十分に説明する必要があります。ただ、それでもなお考えが変わらないような場合に、どのような弁護活動をするべきかが問題となります。これについては『解説 弁護士職務基本規程』15頁に詳しい説明がありますが、①私選の場合辞任する②認否をせず情状弁護のみする③被疑者、被告人の意向通りに弁護活動をするという考え方があります。③の場合は弁護士自身も犯人隠避罪の共犯となるわけですが、これについては正当業務行為として違法性阻却されると考えることになります。ただ、③の説を採用した裁判例があるわけではないので、本当に違法性阻却をされるのかは明らかではないところです。また、③の線で進め、仮に被害者と示談交渉をするようなことがあった場合、被害者に対する詐欺になりかねません。そうすると、③でどこまで弁護活動ができるのかということも考えものですから、できる限り本人の説得に努める方が良いと思われます。
②現金の引き出しもよく問題となります。認めている事件の場合には示談交渉が中心となり、特に身体拘束事件では早期に示談をすることが必要です。また、被害者の側からしても本当に支払いを受けられるのかという点が不安ですので、示談書交付時に同時に支払う方が好ましいとも言えます。しかし、協力者が外にいなければ、どうしても拘束中に現金を用意することができません。このとき、弁護人が本人のキャッシュカードを使うかどうかについては、弁護士によって考え方が様々だと思われます。少なくとも使用するとしても、引き出し前と引き出し後の通帳記帳を行い、引き出し行為についての同意などを書証化したうえで行うべきであり、口頭での合意のみで行うことは控えるべきです。
③①②はまだ弁護活動に関する悩みでしたが、③は直接弁護活動に関係することではありません。このような場合、だれか世話をしてくれる第三者を探すなどして、弁護人が直接餌やりを行うということは断るということも考えられます。また、弁護士が被疑者被告人の自宅に1人で入ること自体、後にトラブルになる可能性もあります。ですので、弁護士としては避けたいところではありますが、反面生き物のことですので、無碍にできないところもあります。これについてもどこまでやるかは弁護士それぞれですが、上述のようにトラブルの可能性もありますから、記録に残したうえで対応するべきであるとは言えます。
④弁護士から見て、主張が不合理であり争いようのないと感じられる事件はあると思います。ただ、これについては、弁護士は本人の主張を前提に弁護活動をすべきであると考えられますので、たとえ無理だと思ったとしても本人の意向通りに犯人性否認をするべきです。ただ、やみくもに否認をするのではなく、本人と証拠を検討する中で、厳しい主張となるという心証を伝えることは、信頼関係を害さない範囲であれば問題ないと思われます。
⑤④と異なり、こちらは法律上不可能であるという話です。保護観察付執行猶予中に再度の執行猶予を付することはできませんので、本人の意向はどうしても叶えられません。窃盗罪であれば罰金刑の主張をすることができるのでその方向性で本人を説得することができると思いますが、詐欺のように罰金刑のない罪名の場合には、そのような方向も取れません。ひとまずは本人に法律上の制度を説明し、それでも納得しなかった場合にどのような方向性をとるかが問題となります①法律を無視したうえで主張する②刑法の規定を憲法違反であると主張し、違憲無効であると述べたうえで主張する③寛大な処罰を求めるとする、など考えられるところです。ただ、①の場合には法律精通義務違反になっているように見えるところでもありますので、後から本人からこの点を指摘される可能性もあります。ひとまず②の主張をするか③も本人の意向に含まれると考えて主張するかというところですので、よく本人と協議のうえで弁論をする必要があります。
【弁護士が解説】弁護士自身の犯罪はどのような影響を及ぼすか

【事例】
X弁護士は、ある日の会食で飲酒をし、その後帰宅する際に自家用車を運転して帰宅してしまいました。
途中、ハンドル操作を誤ったX弁護士は、前方に停車中の車両に衝突してしまい、運転者に全治1週間のけがを負わせてしまいました。
すぐに警察を呼んだのですが、アルコールの匂いがするということで呼気検査が行われ、基準値を上回る数値が計測されたことから、酒気帯び運転の罪で逮捕されることとなりました。
弁護士が酒気帯び運転で逮捕されたということで、このニュースはX弁護士が所属するA県で大きく報道され、A弁護士会の会長が謝罪する事態となりました。
このとき、X弁護士にはどのような処分が科されるのでしょうか。
【解説】
今回のX弁護士の行為は、道路交通法違反(酒気帯び運転)、過失運転致傷罪に該当することになります。もちろん、飲酒の程度や直前の運転行為などから危険運転致傷となる可能性も否定できませんが、今回はひとまず道路交通法違反、過失運転致傷罪ということで検討を進めます。
弁護士の資格と刑事罰に関しては、明確なものとして弁護士法7条1号があります。同号は
第七条 次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者
と定めており、禁錮以上の刑に処せられた者については弁護士となる資格を有しないこととなっています。この条文では、刑の執行の猶予の有無などは問われていません。そのため、仮に執行猶予付きの判決であったとしても、判決確定と同時に弁護士となる資格を喪失することとなります。
たとえ怪我の程度が軽かったとしても、酒気帯びの上での交通事故であれば公判請求の可能性もありますから、弁護士となる資格を喪失する可能性があります。
そこで、何とか交通事故の被害者の方とは示談交渉を行い、宥恕を得られたとします。そうすると、過失運転致傷については不起訴となる可能性が出てきます。
ただ、それでも道路交通法違反については何らかの処罰がなされる可能性が高いと言えます。
酒気帯び運転の初犯の場合には、多くの場合には罰金刑となります。そして、罰金刑自体は、「禁錮以上の刑」ではありませんので、明示的な資格喪失要件ではありません。
しかし、法を守るべき弁護士が法を犯したということ自体が品位を失う非行であると考えられているため、懲戒処分の対象となります。
昨今飲酒運転の撲滅が叫ばれ、公務員であれば一発で懲戒免職となる時代です。そのため、弁護士に対しても厳しい目が向けられていますから、戒告などではなく、業務停止1~3か月程度(事情により期間は前後します)となる可能性が高いと言えます。
飲酒運転で事故を起こしてしまった場合、まずは被害者の方との示談交渉を成立させなければ、弁護士資格自体を喪失してしまいます。ですので、これが最も大切な活動です。
次に、道路交通法違反での処罰をできる限り回避するような弁護活動が必要なところですが、どうしても避けられない場合には、できる限り弁護士会への処分が軽くなるよう、被害者の方からの嘆願書を提出したり、再犯防止のための取り組みを書証化するなどできる限りのことをする必要があります。
このような事態になってしまった場合には、自分で対処しようとするのではなく、専門の弁護士に依頼する方が事態に対する冷静かつ客観的な評価が可能であると思います。このような事態になってしまった場合には、あいち刑事事件総合法律事務所へご連絡下さい。専門の弁護士が相談の対応をさせていただきます。
【弁護士が解説】相手方代理人が就任している事案で、相手方本人と直接交渉することは許されるのか

【事案】
X弁護士は、Aから自身が所有する賃貸マンションからの住人の退去交渉を依頼された。
このマンションの204号室に住むBは、以前から周りの住人とトラブルを起こし、騒音問題などが生じていたことから、Aとしては退去して欲しいと考えていた。
Aが直接Bのところに行って退去を求めると、Bはこれを拒絶し、その翌週にはY弁護士がBの代理人となった旨の通知がAのところに送られてきた。
このようなわけでAはX弁護士のところに依頼しに来たのだが、AはX弁護士に対して「明日の午前中であればBさんはいつも家にいる時間だから、先生が直接Bさんのところに行って、話をつけてくださいよ」と依頼した。
X弁護士はこれに応じてよいのだろうか?
【解説】
現状、Bは代理人としてY弁護士を選任しているようです。通常の法律相談であればAがこれを持参してきており、余程の事情がない限り真実Yが選任されていると考えることになると思われます。
このように、事件の相手方に代理人いる場合には、弁護士は原則直接事件の相手方と交渉することは許されません。
弁護士職務基本規程52条は「弁護士は、相手方に法令上資格を有する代理人が選任されたときは、正当な理由なく、その代理人の承諾を得ないで直接相手方と交渉してはならない。」としています。
Yは弁護士ですので、まさに法令上資格を有する代理人です。このような状況でY弁護士の承諾なくXが交渉を行うようなことは、この規程に違反することになります。
ですので、XはAからの依頼についてはこの規程を理由に断らなければなりません。
今回のようなケースでは、当然依頼を断るべき事案となるのですが、事件によっては相手方に代理人が就任していることに気が付かなかったという場合もあり得ると思われます。通常の相手方であれば、自分で代理人を選任していることを告げると思われますが、仮に途中で発覚したような場合には、その時点で交渉を止め、相手方から聞いた代理人に対して連絡を行うべきであると思われます。
反対に、代理人が選任されており、代理人に何度も連絡をしたにもかかわらず、代理人が一向に返答をしないような場合もあり得ると思われます。このような場合、代理人が返答をしないことは、相手方本人にとっても不利益となりかねないものですし、そもそも相手方代理人の行動自体が事件放置として懲戒の対象になりかねない行動となっています。このような場合には「正当な理由」があると評価され、直接の連絡、交渉が許される場合が生じると考えられています。
弁護士が懲戒請求を申し立てられた場合、弁護士は代理人ではなく紛争の当事者となります。代理人として紛争にあたるのと、当事者として紛争にあたるのとでは気持ちもパフォーマンスも大きく変わってくると考えられます。代理人を入れることで、事実をしっかりと整理し、懲戒処分の回避や軽減につながる可能性が上がります。
懲戒請求手続について詳しく、懲戒請求に対する弁護活動経験が豊富な弁護士への相談を検討している先生方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
弁護士報酬について、不当に高額と評価されるのはどのような場合であるのか

【事例】
X弁護士は、Aから貸付金の返還を求める訴訟の依頼を受け、委任契約書を作成した。
Aが返還を求めたい金額が100万円だったとして
①着手金10万円、成功報酬は回収金額の16%
②着手金20万円、成功報酬は回収金額の32%
③着手金30万円、成功報酬は回収金額の48%
④着手金10万円、成功報酬は回収金額の3%+69万円
という報酬での契約をした場合(実費、日当等は考慮しない)、何か問題が生じるでしょうか。
【弁護士報酬の規律】
2003年に弁護士法が改正されるまでは、弁護士法上、弁護士会の会則として弁護士報酬等を定めなければならないとされていました。このとき定められていた会則がいわゆる「旧報酬規程」と呼ばれているものです。
①のケースで記載している金額は、この旧報酬規程に従った金額となります。経済的利益が300万円以下の事件の場合には、着手金はその8%とされているのですが、最低金額は10万円ということになっていたので、このケースでは着手金は10万円となります。
そして、成功報酬は経済的利益の16%とされていましたので、この点もそのままです。
旧報酬規程自体は撤廃され、現在の弁護士報酬は自由化されています。しかし、現状でも旧報酬規程のままの金額を用いている弁護士は相当数おられるのではないかと思われます。
現在、弁護士報酬に関する規律を定めているのは、弁護士職務基本規程24条となります。そこでは、「弁護士は、経済的利益、事案の難易、時間及び労力その他の事情に照らし、適正かつ妥当な弁護士報酬を提示しなければならない」と定めているのみで、具体的な金額は記載していません。
しかし、だからと言っていくらでも問題にならないというわけではなく、不当に高額な弁護士報酬を請求したような場合には、懲戒の対象となる可能性があります。
ひとまず、①は旧報酬規程に従った金額となります。基本的にはこの金額で問題になることは多くないようです。
しかし、示談交渉事件などで、あまりにも短期間にかつ非常に高額な金額での示談交渉がまとまった場合、かけた時間に対して弁護士報酬が非常に高額となってしまいます。このような場合、仮に旧報酬規程に従った金額であったとしても、不当に高額であるとの評価を受ける可能性があります。
②の金額は旧報酬規程の2倍の金額、③の金額は旧報酬規程の3倍の金額、④の規定は旧報酬規程の中で経済的利益が旧報酬規程の中で経済的利益が3000万円を超え3億円以下のときを参考にしたものです。
仮にX弁護士が完全に勝訴し、かつ金銭も回収できたと考えた場合、②の件は着手金20万円、成功報酬32万円で合計52万円となります。つまりAは勝利したとしてもほぼ半分が消えていくということになります。
同じように計算すると、③のケースでは78万円、④のケースでは82万円が弁護士費用(実費日当は除く)となります。
③④のケースが不当に高額と評価されることについてはおそらく争いがないと思われます。
②のケースについては、必ず不当の評価を受けるとまでは言えない可能性があります。事案の難易度や、事件処理の程度によってはやむを得ない場合も存在すると思われます。
ただ、②③④のケースに共通する問題として、果たして依頼者であるAに対して、契約締結時に正しい説明がなされたのかどうかという点です。③④のような場合には、仮に勝訴したとしても自分の手元にはほとんど残りません。今回は考慮しませんでしたが、実費日当を考慮するとマイナスになる危険性すら生じてきます。このような契約を締結するとは通常考え難い面がありますから、このような契約があること自体、弁護士が契約締結時に十分な説明をしなかった可能性を推認させてしまいます。
ですので、契約締結時には、最終的に終了したときにどれくらい手元に残るのかということについても、十分に説明をした上で依頼者には検討してもらう必要があります。
【弁護士が解説】委任契約書を作成せず事件処理を行った場合、弁護士職務基本規程に違反するのはどのようなケースか

【事案】
A弁護士は、法律相談できたXから、お金を貸した相手が返さないという相談を受けた。
A弁護士はその中で、内容証明郵便を送付してお金を取り立ててみる方法や、支払督促、民事訴訟などの方法で返済を求めることができるという説明をしました。
Xはその場でA弁護士に委任をしましたが、この際A弁護士は委任契約書を作成しませんでした。
このとき、Xが委任した事項が
①内容証明郵便の文面を作成するのみで、文章の発出元はX自身とされている場合
②内容証明郵便を作成し、A弁護士がXの代理人という形で文頭に記載されている場合
③民事訴訟の委任を受けた場合
のいずれかであった場合、委任契約書を作成しなかったことが問題とならないか検討していきます。
【規程】
委任契約書の作成については、弁護士職務基本規程30条に定めがあります。
1 弁護士は、事件を受任するに当たり、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。だだし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由が止んだ後、これを作成する。
2 前項の規定にかかわらず、受任する事件が、法律相談、簡易な書面の作成又は顧問契約その他継続的な契約に基づくものであるときその他合理的な理由があるときは、委任契約書の作成を要しない。
弁護士職務基本規程は平成16年11月に定められましたが、それより前の平成16年2月に制定された「弁護士の報酬に関する規程」5条2項、3項にも同様の定めがありました。
この規程によれば、原則は委任契約書を作成する必要があります。委任契約書を作成しなくてよいのは2項に定めがある例外的な場合に限られます。また、2項に定めのあるような例外的な場合であっても、委任契約書の作成が禁止されるわけではありませんから、法律相談のような明確な場合はさておき、後から委任契約書作成義務違反の指摘を受けないため、念のため作成しておくということも有効であろうと思います。
【事案の検討】
それではA弁護士が委任契約書を作成しなかったことが問題とならないか検討していきます。
①のように、内容証明郵便の文面だけ作成するような行為については、「簡易な書面の作成」となる可能性が高いと思われます。ただ、簡易な書面の作成について委任契約書の作成が不要とされているのは、その場で仕事が完了し、弁護士報酬の支払いも済んでしまうような場合であるからとされています
(解説 弁護士職務基本規程第3版 109頁)。
そうすると、たとえ①のような場合であっても、何度もやり取りを行い、文面案を作成していくような場合には、委任契約書が必要ないとまでは断言できなくなってきます。
②の場合は、もはや形式上AがXの代理をしていると見えますので、委任契約が不要となるような簡易なものではないと言えます。
条文上は「合理的な理由があるとき」は契約書の作成を要しないとされていますが、親族など深い関係にあるからなどというようなものは理由にならないと考えられます。
③の場合は当然委任契約書の作成が必要となります。ただ、「委任契約書を作成することに困難な事由があるとき」は、直ちに作成せず、事由が止んだ後に作成することが許されています。この「困難な事由」がいかなる場合に該当するのかという問題については、明確な解釈などは公表されていません。
たとえば、最初に法律相談に来た際には法的な問題点が見えてこず、依頼者としては何らかの解決に向けて弁護士に依頼はしたいけれど・・・という事態は生じ得ます。この場合、1回目の法律相談時には事件の全体像が見えない関係で、報酬等が定められず、契約書は作成できないという場合も考えられます。
このような場合に委任契約書を作成せず事件処理をすることが「困難な事由」に該当するかどうかについて確定的な判断があるわけではないですが、少なくとも法律相談料として毎回支払いを受けるとか、仮に対外的なことをしなければならないような場合にはその点に限って委任契約書を作成するなど、回避する方法は十分あると思われます。そのため、徒に契約書を作成せず、相談を継続していくようなことは危険であると考えられます。
いずれにしても、委任契約書作成の義務があるケースで、これを作成しなかった場合には弁護士職務基本規程違反となります。そして基本規程違反は懲戒事由となりますので、何らかの懲戒処分を受けることになります。これまで委任契約書不作成で処分を受けているケースは、報酬や説明義務の点などほかの問題と一緒に併せて処分を受けていることがほとんどです。そのため、委任契約書不作成のみでどのような処分を受けるかは一概に評価できませんが、弁護士としての基本的な義務に属するものであると考えられますので、戒告の処分は十分あり得るところです。
【弁護士が解説】相手方から弁護活動を依頼された場合にはどのような点に注意しなければいけないか

【事案】
A弁護士は、BからCを相手方とする不法行為に基づく損害賠償請求(交通事故)事件を受任しました。
A弁護士はCに連絡を取り、示談交渉を行いました。
その後、今度はCからAに連絡があり、C自身の離婚事件をA弁護士に受けてもらえないかと言われました。
このとき
①まだBC間の損害賠償事件が終結していなかった場合
②Bとの間の委任契約は別の形(別件刑事事件等)で存続していたが、BC間の示談交渉は既に終結し、示談が締結されていて、Cに対する事件が終結していた場合
③既にBとの委任契約は終了していた場合
で何か対応方法に違いがあるのでしょうか。検討していきたいと思います。
【利益相反】
弁護士として一般の方と示談交渉等をしており、特にその示談交渉が円満に解決したような場合には、相手方当事者から事件の依頼の勧誘を受けることはそ う珍しいことではありません。
しかし、自身の依頼者と相手方当事者では、利害対立があることが通常であり、利益相反をしていることになります。
ですので、このような依頼を無制限に受けてしまうと、誰の味方であるのかという根本的な点に不信感を生じさせる危険性があります。
そのため、弁護士法及び弁護士職務基本規程では、「職務を行い得ない事件」を定めています。通常これを「利益相反」と呼んでおり、利益相反がある場合には受任をしてはならないことになっています。
まず、今回直接的に問題となりそうな弁護士法25条3号(職務基本規程27条3号も同じ)を見てみましょう。
弁護士法25条
弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第三号及び第九号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
弁護士法25条3号は、受任している事件の相手方からの依頼については、「他の事件」であっても原則職務を行うことを禁じています。ただ、他の利益相反規定と異なり、この3号については但書によって「受任している事件の依頼者が同意した場合」には受任が認められています。
A弁護士の例でいえば、①はまさにこの3号が問題になります。ですので、依頼者であるBの同意があれば受任できることとなります。
ただ②はより難しい状況です。BとCの間の事件は終了していますので、その意味ではCは「受任している事件の相手方」ではなくなっているとも言えます。しかし、Bとの委任契約は継続中ですから、Bは現在も依頼者であると言えます。仮にこの状況でA弁護士がCからの事件を受任した場合、Bは自己の事件(BC間の損害賠償事件)についてもCに有利に解決されたのではないかと相当の疑念を持つことが自然であると言えます。ですので、受任を差し控えるか、①と同様Bの了解を得ていた方が好ましいと考えられます。
③は、すでに委任契約が終了していますので、条文上はCは「受任している事件の相手方」には全く当たりません。そのため、自由に受任できるということになります。ただ、②で指摘した事情は当てはまりますので、Bとの委任契約終了から間がないのであれば、Bの同意を得ていた方が後のトラブル回避につながると考えられます。
【守秘義務】
しかし、このBの同意を得るためには、もう1つ考えなければならないことがあります。
Bから同意を得る以上、自身がCのどのような事件を受任するのかについて、Bに説明をする必要があります。これは、Cに対する守秘義務との関係で問題が生じます。
もちろん、Bに対しては、Cが同意をした範囲でしか話すことはできません。ただ、今回のような離婚事件の場合、Cの資力に影響が生じる可能性もあります。これは、B自身がCに対する債権者となる損害賠償請求事件を受けていた場合、BC間の交渉に影響を与えかねない事情となります。
Bからの同意はもちろん真意に基づく同意でなければなりませんので、錯誤等意思表示に瑕疵があるようなものであってはいけないと考えられます。そのため、Cから受任しようとする事件が、直接的にも間接的にもBC間の事件に影響を与えてしまうような場合で、その内容をBに説明できないような場合には、そもそも同意を取り付けることはできない(同意をしたとしても問題がある同意である)ということになりますから、最初から受任を差し控えるべきであると考えられます。
問題が生じてしまった後では、いかにこの事態を収拾するかがポイントとなります。(元)依頼者の方との間の話し合いが必要となった場合などには、第三者を介して話し合った方が冷静な話し合いが可能になります。
また、懲戒請求を受けてしまった場合には、これに対応する必要もあります。このような場合には、経験豊富なあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。懲戒請求の流れや、弁護方針等についてお答えします。
【弁護士が解説】外部へ郵便物を郵送する際、守秘義務違反とならないようにするためにはどのような点に注意すればよいか
【共通設定】
A弁護士は、窃盗罪で逮捕されたXの国選弁護人として選任され、留置先であるB警察署へ
接見に赴きました。
面会したXから、自身の両親に連絡を取って欲しい旨を告げられましたが、Xは両親の連絡先を知らず、元々Xが暮らしていた住所しかわからない状況でした。
そこで、A弁護士は、郵便を用いて両親へ連絡を取ることとしました。
このとき
事例1
A弁護士は、普通の官製はがきの通信面に「私は息子さんの国選弁護人となりました。息子さんの件でお話ししたいので、事務所までご連絡ください」と記載した。
事例2
A弁護士は、茶封筒の中に、事例1と同じ内容を記載した手紙を同封した。そして、Xが指示する郵送先へ郵送したが、Xの実家は既に転居しており、実家には別の第三者が居住していた。そのため、郵便物は第三者によって開封された。
事例3
A弁護士は、茶封筒の中に、事例1と同じ内容を記載した手紙を同封した。そして、Xが支持する郵送先に郵送し、そこは確かにXの実家であった。しかし、手紙はXの兄弟が受領し、郵便物は兄弟が開封した。
これらの事例で、A弁護士の行動には問題がないか、検討していきたいと思います。
(事例は架空のものです)
【守秘義務】
弁護士法第23条及び弁護士職務基本規程第23条では、秘密の保持が義務付けられています。
これは、信頼関係を基礎に置く弁護士の職務上、最も基本的な義務と考えられており、守秘義務違反は最も注意をしなければいけない点となります。
ただ、弁護士の守秘義務には例外もあり、一番大きな例外が「本人の同意がある場合」と考えられます。なお、ここでの「本人」は、秘密の対象となる本人と考えられます。たとえば、依頼者の相手方の秘密については、依頼者及び相手方双方の同意があった場合のみ守秘義務が解除されると考えられます。
今回の事例で、A弁護士はXから「両親に連絡を取って欲しい」と言われています。このようなやり取りがある以上はXが勾留されていることなどについては、両親に対しては守秘義務が解除されていると考えてよいように思われます。もっとも、事件内容をどこまで詳細に話してよいかなどについては、本人とよく相談の上考える必要があります。
ただ、あくまでも両親に対して守秘義務が解除されているにすぎませんので、両親以外については守秘義務は解除されていないことになります。
【事例の検討】
⑴事例1
事例1の問題点は官製はがきを用いた点です。はがきは封書よりも郵便料金が安くなる半面、はがきの通信面は誰からでも容易に閲覧が可能となってしまいます。実際に郵便配達を行う郵便職員から見えることはもちろんのこと、ポストなどに投函された後も場合によっては第三者から閲読可能な状況になる可能性が否定できません。
郵便職員については、郵便法8条2項により秘密保持義務がありますのでここからさらに外部へ広がるという可能性は高いものではありませんが、それでも郵便職員に対して内容を知られること自体が問題であると言えます。
今回、A弁護士は自身が「国選弁護人」に選任されたことを記載しています。この内容と、はがきに記載されている内容から考えれば、宛名の人物の子どもが何らかの刑事事件を起こしたことは容易に明らかになります。刑事事件を起こしたことは一般に知られたくないことでしょうから、守秘義務の対象となる秘密であるというべきです。
そのため、このようは秘密に該当する事項をはがきに記載することは、守秘義務違反として何らかの処分を受ける可能性がある事項ということになります。
⑵事例2
事例2の問題は、A弁護士が実家の住所の所在を確認せず郵送したところにあります。
Xが両親の連絡先を知らないということは、実家と疎遠になっていることは予想できたようにも思われます。ただ、本人から言われた住所を逐一確認しなければ郵送できない(たとえば戸籍の附票や住民票を職務上請求しなければ郵送できないと考えること)とするのは、現実的ではないようにも思われます。
ただ、A弁護士からすれば、正確性の担保がない住所である以上、郵送する際には慎重に行う方が望ましかったと考えられます。これに対し、Xから指示された住所が勾留状記載の住所であれば、捜査機関が特定した住所であるということになりますから、それに従って郵送することに合理性があると考えられます。
A弁護士とすれば、たとえば簡易書留などの方法で送り、対面での受け取りが必要となる手段を講じるとか、最初の手紙の中身を「お伝えしたいことがありますのでご連絡ください」程度とし、事案の推測がなどができないようにしておくなどの対策が考えられたと思われます。
⑶事例3
事例3の問題は、思った通りに郵送がなされたものの、郵送先で第三者が開封してしまったという点にあります。
とはいえ、Xの兄弟が実家にいること自体は全く不自然ではないため、両親以外の親族が開封してしまう可能性は否定しきれません。また、上述のように簡易書留で郵送した場合であっても、兄弟であれば受けることができてしまいます。
そのため、このような事態を回避するためには、郵便そのものを本人限定受取郵便という形で郵送することが考えられます。ただ、この方法で郵送した場合には、受け取りに手間がかかる場合があることもありますので、保管期限内容に郵便が受け取られない可能性があること、郵送費が高額となることが問題となります。
ですので、1つの方法としては内容を具体的に書かず「ご連絡ください」とだけ記載して郵送することも考えられます。ただ、昨今弁護士の名をかたった特殊詐欺も横行していますので、このような手紙に不自然さを覚える方がおられる可能性も否定できません。
このような事情もありますので、本人と十分協議を重ねたうえで、同居の親族への守秘義務解除について予め検討しておくことが必要であると思われます。そして、メリットデメリットを伝えたうえで、最終的には本人にどのような連絡先を取るか決定してもらうことが重要であろうと思われます。
« Older Entries