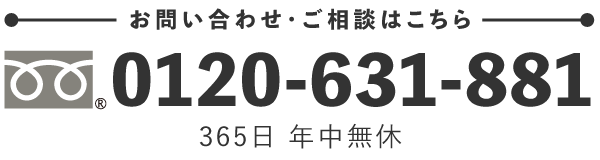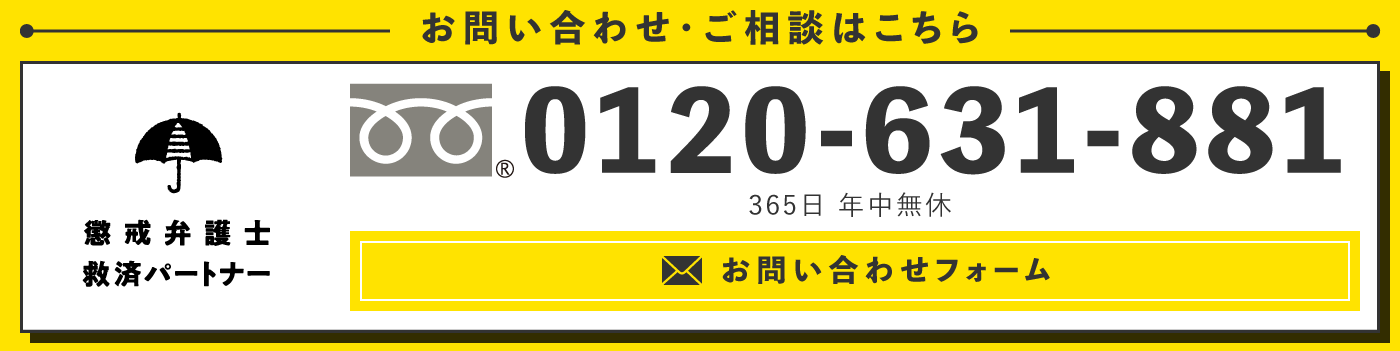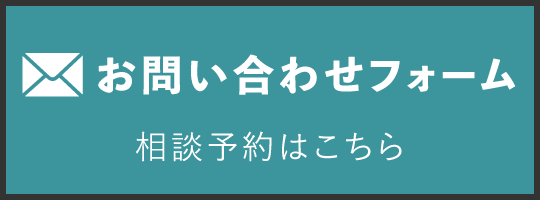Archive for the ‘その他の手続き’ Category
係争権利の譲り受けが訴訟法上問題となった事案
1 事案の概要
XはYに対して土地を貸していたが、この賃貸借契約に対してXが契約解除の意思表示をした。
しかしその後もYは延滞賃料を支払わず、この賃貸借契約に基づく紛争は解決していなかった。
A弁護士はXからこの紛争について訴訟委任を受けていたが、その途中で訴訟の目的物である土地の一部を買い受けることを予約した。
このような予約をしている弁護士の行った訴訟行為が問題となった。
(最判昭和35年3月22日の事案)
2 判旨
ところで、弁護士法二八条は弁護士が事件に介入して利益をあげることにより、その職務の公正、品位が害せられまた濫訴の弊に陥るのを未然に防止するために設けられた規定であるから、たとえ弁護士が同条に触れる取引行為をしたとしても、その場合に右取引行為の私法上の効力が否定されまたその弁護士が同法七七条所定の刑罰を受けるのは別論として、右取引行為の目的となつた権利に関する訴訟委任およびこれに基く訴訟行為が同二八条により直ちに無効とされるものではないと解するのを相当とする。されば、弁護士AがXとの間でした右土地売買予約が前記法条に違反するとしても、これがためXがA弁護士に対してした訴訟委任およびA弁護人がその代理人としてした訴訟行為は無効となるものではない
3 説明
今回の行為が弁護士法28条に違反すること自体は認定されています。
ただ、第1審の東京地裁も「右法条〔28条〕は同法第二十五条のように弁護士の職務活動を制限するものではなくて、弁護士の品位の保持と職務の公正な執行を担保するために抜本的に弁護士の係争権利の譲受を禁止し、その違反行為はこれを無効とする趣旨の規定であるから、右売買の予約が仮に同法第二十八条に牴触するものとしても、AはこれがためにXから本件訴訟を受任することができなくなるものではない」としています。つまり、あくまでも私法上の問題である以上、訴訟行為を無効とする理由はないというものです。
もっとも、このような行為が懲戒事由に該当することには注意を要します。
非弁提携が問題となった事案
1 事案の概要
元々の事案は、原告である大手貸金業者が、被告(個人)に対してキャッシングに基づく貸金契約の返済を求めた事件でした。
しかし、これに対して被告が原告に対して反訴提起しました。この反訴提起は、被告が、原告に対して不当利得返還請求権を有する別の人物からその債権を譲り受け、譲り受けた不当利得返還請求権を元に起こしたものでした。
この債権譲渡について、弁護士法72条に違反するものではないかということが問題となりました。
(東京地判平成17年3月15日の事案)
2 判旨
まず、弁護士法七三条は、「何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によって、その権利の実行をすることを業とすることができない。」と規定しているところ、被告が、本件債権譲渡を「業」としてしたことを認めることはできないから、本件債権譲渡が同条に直接違反するものとはいえない。
また、弁護士法二八条は、「弁護士は,係争権利を譲り受けることができない。」と規定しているところ、本件債権譲渡の法律主体は被告であるから、やはり、本件債権譲渡が同条に直接違反するものとはいえない。
また、弁護士法二五条の趣旨を受ける弁護士倫理二六条二号は、弁護士が「受任している事件と利害相反する事件」については職務を行ってはならないと規定しているところ、本件債権譲渡を前提とした反訴の提起自体が、被告及びApの債務整理受任事件と直接利害相反するものと認めるのは困難である。
さらに、弁護士法七二条本文は、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件(中略)その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」と規定しているところ、被告が本件債権譲渡を受けて反訴を提起したこと自体が同条によって直接禁止される行為であるということも困難である。
そうすると、本件債権譲渡に関する被告又は被告訴訟代理人らの行為について、これらの各規定の直接適用はできないものというほかない。
もっとも、弁護士法七三条の趣旨は、非弁護士が権利の譲渡を受けて事実上他人に代わって訴訟活動を行うことによって生ずる弊害を防止し、国民の法律生活に関する利益を保護しようとする点に、また、弁護士法二八条の趣旨は、弁護士が事件に介入して利益を上げることにより、その職務の構成、品位が害せられることを未然に防止しようとする点に、それぞれ存するものと解される。
また、弁護士倫理二六条二号の趣旨は、弁護士が、法律上及び事実上の利益・利害が相反する事件について職務を行うことを防止し、もって当事者の利益を保護するとともに、弁護士の品位を保持し、さらには、弁護士の職務の公正さと弁護士に対する信用を確保しようとする点に存するものと解される。
さらに、弁護士法七二条本文前段の趣旨は、弁護士業務の誠実適正な遂行の担保を通して当事者その他の関係人の利益を確保し、もって、法律秩序全般を維持し、確立させようとする点に存するものと解される。
ところで、前記に認定した本件紛争の経緯に、被告が本人尋問に出頭しないことにつき民事訴訟法二〇八条の規定の趣旨を併せると、本件債権譲渡は、Bら法律事務所に所属する弁護士主導のもとに斡旋されたものであることが明らかである。
そして、これら一連の行為を実質的に見れば、法律事務所の弁護士らが主体となり、報酬を得る目的で、業として、自らが債務整理を受任した依頼者のうち原告に対して不当利得返還請求権を有している不特定多数の者から原告に対して貸金債務を負担している不特定多数のものに同不当利得返還請求権を譲渡させ、これらの権利の実現を訴訟等の手段を用いて実行しているものということができる。
かかる行為は、前記の弁護士法七三条及び二八条の趣旨に抵触するものというべきであり、かつ、斡旋の際の説明内容や、対価の額及び支払態様、これらと債務整理事件の報酬との関係によっては、原告に対して不当利得返還請求権を有している不特定多数の依頼者の利益を損ねるという、前記の弁護士倫理二六条二号の趣旨に具体的に反するおそれが高い、看過し難い行為であるというべきである。
そうすると、かかる債権譲渡行為の私法上の効力を認めてこれを放任することは、不特定多数の関係人の利益を損ね、広く弁護士業務の誠実適正な遂行やこれに対する信頼を脅かし、ひいては法律秩序を害するおそれがあると認められるのである。
よって、かかる態様による債権譲渡は、公序良俗に反し無効であると解するのが相当である。
3 説明
なぜ弁護士事務所がこのようなことをしたのかということについて明らかにはされていませんが、おそらく訴訟手数料の集約や、手続の負担を軽減する(同じ相手方に対して多数の訴訟が係属するより、一本の訴訟内でまとめて解決したほうが負担が少ない)という目的ではないかと思われます。
このとき、弁護士自身が譲り受けるわけにはいかない(係争権利の譲り受けとなる)ため、依頼者の内の一部の者に権利を集約してしまうという手法がとられたものと思われます。
しかし、このような手法は当然法の潜脱ということになりますから、上記判旨の通り無効されました。
係争権利の譲り受けが問題となった事案
1 事案の概要
BはCとの間で、Cが実施する事業について、Bにとって必要な経費をCが負担し、Cがその経費をBに送金して支払う旨の契約を締結した。
A弁護士は、Bから上記契約に基づく債権の回収を依頼され、Cに対して訴訟の提起を行うこととしたが、その前にBからその権利を譲り受けた、A弁護士がこのようなことをした理由は、Bが日本国内に登記した支店や営業所を持たない外国法人であったため、民事訴訟法上の訴訟手続の困難を回避するためであった。
譲り受け後、A弁護士は自ら原告となりCに対して本案訴訟を行い、債権を保全するため仮差押えを行った。
(最決平成21年8月12日の事案)
2 判旨
債権の管理又は回収の委託を受けた弁護士が,その手段として本案訴訟の提起や保全命令の申立てをするために当該債権を譲り受ける行為は,他人間の法的紛争に介入し,司法機関を利用して不当な利益を追求することを目的として行われたなど,公序良俗に反するような事情があれば格別,仮にこれが弁護士法28条に違反するものであったとしても,直ちにその私法上の効力が否定されるものではない(最高裁昭和46年(オ)第819号同49年11月7日第一小法廷判決・裁判集民事113号137頁参照)。そして,前記事実関係によれば,弁護士である抗告人は,本件債権の管理又は回収を行うための手段として本案訴訟の提起や本件申立てをするために本件債権を譲り受けたものであるが,原審の確定した事実のみをもって,本件債権の譲受けが公序良俗に反するということもできない。
3 解説
原審は、「抗告人が本件債権を譲り受けた当時,本件負担金の支払を求める訴訟等は係属していなかったから,本件債権の譲受けが,弁護士法28条に違反する行為であるとはいえない。しかし,弁護士の品位の保持や職務の公正な執行を担保するために弁護士が係争権利を譲り受けることを禁止した同条の趣旨に照らせば,本件負担金の支払を求める訴訟等が係属していなかったとしても,本案訴訟の提起や保全命令の申立てをすることを目的としてされた弁護士による本件債権の譲受けは,特段の事情がない限り,その私法上の効力が否定されるものというべきであり,本件債権の譲受けは無効であって,抗告人が本件債権を有しているとはいえない。」という理由で効力を否定していましたが、最高裁はこれを覆し、弁護士法28条違反(ないしこれに類する事態)だけでは直ちに民法90条に反するものではない旨を判示し、高裁に事件を差し戻しました。
なお、この最高裁決定には宮川裁判官の補足意見があり、その中ではこのような事態が民法90条に違反しないとしても、懲戒事由たる「品位を失うべき非行」には該当しうることが述べられています。
懲戒処分を受けた者がした行為の効力
1 業務停止以上の処分を受けた場合
業務停止、退会命令、除名の処分を受けた場合、業務停止中はその期間弁護士の業務を行うことができなくなりますし、退会命令、除名の処分を受けた場合には効力発生後からは弁護士登録がなされていない状態となりますから、当然弁護士としての業務を行うことはできなくなります。
そのため、このような弁護士としての業務が行えない状態になっている期間に弁護士としての業務を行った場合、これが弁護士法上違法なものであることは明らかだと思われますが、それ以外(たとえば民事訴訟や刑事訴訟など)の場面ではどのように扱うべきかが問題となります。
2 民事訴訟における行為の効力
民事訴訟の代理人として、弁護士たる業務を行えない者がなした行為は、訴訟法上どのように解釈されるべきでしょうか。
民事訴訟法上は、一定の例外は存在するものの、弁護士代理の原則が存在します(民事訴訟法54条1項)。これを厳格に解釈すると、弁護士ではない者が代理して行った訴訟行為は、一切無効なものであると考えることになります。
しかし、これを厳密に考えすぎると、それまでに訴訟が進行し、相手方や裁判所が対応してきた訴訟行為も含めて一切無効という解釈になり、手続の安定性を害することになってしまいます。
そのため、弁護士たる業務を行えない者を訴訟から排除しなければならないことには異論はないものの、これまでに行ってきた訴訟行為を有効と判断するかについては解釈が分かれています。
この点について、最判昭和42年9月27日では、その代理人が弁護したる資格を喪失している状態(業務停止中)を看過してなされた訴訟行為について、直ちに無効になるものでない旨判示されました。この事例は、業務停止中の訴訟行為であったため、期間が経過すれば再び弁護士に戻る者ということになりますので、除名や退会命令の場合に同様の判断を行うことができるかどうかは判然としません。ただ、最高裁は、手続の安定性確保のため、上記のような結論を採用しました。
3 刑事訴訟
憲法37条により、被告人には弁護人を依頼する権利が与えられています。このような弁護人の地位は相当公益性が高く、弁護士資格が当然の前提となるように思われます。
そのため、たとえ業務停止中であっても、弁護士業務が行えない状態でなされた訴訟行為等については無効であると考えるべきですし、被告人の追認も同様であると思われます。
なお、被疑者については弁護人選任権が憲法上付与されているわけではありませんが、憲法31条に基づき刑事訴訟法が制定されていると考えられますので、同様に理解してよいのではないかと思われます。
4 訴訟外の行為
除名、退会命令を受けた元弁護士が弁護士同様有償で法律上の業務を行うことは、弁護士法72条に違反することになります。そして、この弁護士法72条は、公益性の高い規定であると考えられますので、弁護士法72条に違反してなされた行為については民法90条により無効となる可能性があります。
反対に、業務停止中の弁護士が代理して行った訴訟外の行為については、あくまでも業務停止中には弁護士たる資格を喪失するわけではないので、そのような代理行為は懲戒事由とはなるものの、弁護士法72条に違反するものではありません。しかし、国民を非弁護士から保護するという弁護士法72条の規定の趣旨からすると、懲戒の処分により業務を停止された弁護士に代理行為を行わせるのは適当ではないと思われますので、このような場合にも無効となる可能性はあるように思われます。
非弁行為の私法上の効力が問題となった事案
1 事案の概要
AはBとの間で、債権の取り立て及び債権取り立てのための訴訟について弁護人を選任する等解決の一切を委任され、取り立てに成功した場合には訴訟費用を除いた金額の半額を受け取るという契約を締結した。
この委任契約は有効なものであるかどうか、弁護士法72条違反が私法契約に与える影響が問題となりました。
(最判昭和38年6月13日の事案)
2 判旨
弁護士の資格のないAが右趣旨のような契約をなすことは弁護士法七二条本文前段同七七条に抵触するが故に民法九〇条に照しその効力を生ずるに由なきものといわなければならないとし、このような場合右契約をなすこと自体が前示弁護士法の各法条に抵触するものであつて、右は上告人が右のような契約をなすことを業とする場合に拘らないものであるとした原判決の判断は、当裁判所もこれを正当として是認する。
3 解説
この判決は特に理由は述べていませんので、最高裁が是認した原審(福岡高判昭和37年10月17日)の判断を見てみます。
「思うに弁護士法第七二条は、弁護士でない者は一般に法律家としての識見、能力に欠くるところがあるので、かような者が報酬を得る目的を以て法律事務の取扱をしたり、あるいはその周旋を業とすることを放任すれば、法律生活における国民の正当な利益を害する虞があり、また司法の健全な運用、訴訟の能率向上、及び人権の擁護等の要請上弁護士を公認した同法の趣旨に反するとの見地から右のような非弁護士の行為を禁止した公益的規定と解せられ、その違反行為に対しては同法第七七条により刑罰の制裁を以て臨んでいるのであるからこれに違反する事項を目的とする契約は、公の秩序に反する事項を内容とし民法第九〇条に照してその効力を生ずるに由なきものといわなければならない。」
このように、弁護士法72条の趣旨から考え、国民の正当な利益を確保するため、本条違反の行為は民法90条により無効となるとされました。
広告規程が問題となった事例
1 国際ロマンス詐欺案件を取り扱う弁護士業務広告の注意点
東京弁護士会(https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hibenteikei/news/post_7.html)
千葉県弁護士会(https://www.chiba-ben.or.jp/news/2023/000727.html)
等において、一部の弁護士業務広告に対する注意が呼びかけられています。
今回は、弁護士の業務広告について検討をします。
2 業務広告についての規制
弁護士の業務広告については、弁護士職務基本規程第9条に「弁護士は、広告又は宣伝するときは、虚偽又は誤導にわたる情報を提供してはならない。」「弁護士は、品位を損なう広告又は宣伝をしてはならない」と定めています。
かつては弁護士の業務広告は原則禁止とされていましたが、2000年にこれが自由となったことに伴い、業務広告への制限がなされるようになりました。
この職務基本規程第9条は、あくまでも総論的なものを定めるのみですが、より具体的には「弁護士等の業務広告に関する規程」が定めれており、この中で具体的な禁止事項が規定されています。
また、この規程には「業務広告に関する指針」が別途定められており、規程の解釈がより具体的なものとして示されています。
3 弁護士等の業務広告に関する規定
それでは、実際に禁止されている広告とはどのようなものでしょうか。
⑴禁止されている広告
規定3条により禁止されている広告は以下の通りです(例として記載しているのは指針に記載されているものです)。
①事実に合致していない広告(例:虚偽の表示、実態が伴わない団体又は組織の表示)
②誤導又は誤認のおそれのある広告(例:交通事故の損害賠償事件の件数を損害賠償事件取扱件数に含めて延べ件数を表示し、あたかも損害賠償事件全般に習熟しているかのような印象を与える表現、弁護士報酬についての曖昧活不正確な表現)
③誇大又は過度な期待を抱かせる広告(例:「たちどころに解決します」)
④困惑させ、又は過度な不安をあおる広告(例:「今すぐ請求しないとあなたの過払金は失われます」)
⑤特定の弁護士、弁護士法人、外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人又はこれらの事務所と比較した広告(例:「○○事務所より豊富なスタッフ」)
⑥法令又は本会若しくは所属弁護士会の会則若しくは会規に違反する広告(例:非弁提携をうたうもの)
⑦弁護士等の品位又は信用を損なうおそれのある広告(例:違法行為若しくは脱法行為を助長し、又はもみ消しを示唆する表現)
⑵表示できない事項
規程第4条では、広告中に表示することが禁止されているものがあります。
①訴訟の勝訴率(3条2号に違反するものの例として)
②顧問先又は依頼者。ただし、顧問先又は依頼者の書面による同意がある場合を除く。
③受任中の事件。ただし、依頼者の書面による同意がある場合及び依頼者が特定されず、かつ、依頼者の利益を損なうおそれがない場合を除く。
④過去に取り扱い、又は関与した事件。ただし、依頼者の書面による同意がある場合及び広く一般に知られている事件又は依頼者が特定されない場合で、かつ、依頼者の利益を損なうおそれがない場合を除く。(以上3項は守秘義務との関係で問題となる)
4 まとめ
このように、弁護士の業務広告には種々の規制があり、これらの規定が日弁連の会規として定められている以上、広告規程違反は会規違反として懲戒の事由となる場合があります。
利益相反が問題となった事例①
1 事案の概要
西暦P年、A社はY弁護士と委任契約を締結し、民事再生手続きの申立て等の委任をした。
同年、Y弁護士はA社に対する再生手続開始の申立てを行い、その際にはB社をスポンサーとして再生手続きを進めることとしていた。
その後、A社に対する再生手続は開始されたが、B社がスポンサーを降りてしまったため、同手続きは廃止されてしまった。
そしてA社について破産手続開始決定がなされ、その破産管財人にX弁護士が選任された。
P+1年、管財人であるX弁護士は、B社を被告として否認権行使訴訟等を提起したところB社はY弁護士を訴訟代人として選任した。
この選任行為に対し、X弁護士が弁護士法第25条1号を理由としてY弁護士を訴訟行為から排除するよう裁判所に申し立てを行った。
(最高裁平成29年10月5日決定の事案)
2 裁判所の判断
(1)原審の判断
原々審はX弁護士の主張を容れて、Y弁護士を排除したが、これに対してY弁護士が抗告した。
原審は、破産管財人が提起した訴えの相手方の訴訟代理人である弁護士が過去に破産者から上記訴えに係る請求に関連する法律事務等の委任を受けていたとしても、破産管財人が独立した権限に基づいて財産の管理処分権を行使することなどに照らすと、上記弁護士の訴訟行為は弁護士法25条1号にいう「相手方の・・・依頼を承諾した事件」に当たらないとして、原々決定を取消した。
(2)最高裁判所の判断
最高裁判所は以下の通り判断し、Y弁護士の行為を訴訟から排除した。
「A社は,破産手続開始の決定を受ける前に,相手方Yとの間で,本件委任契約を締結していたのであるから,相手方Yは,A社の依頼を承諾して,A社の業務及び財産の状況を把握して事業の維持と再生に向けて手続を主導し,債権の管理や財産の不当な流出の防止等についてA社を指導すべき立場にあったものである。そして,本件訴訟における主たる請求の内容は,相手方YがA社から委任を受けていた間に発生したとされるA社のB社に対する各債権を行使して金員の支払を求めるもの(中略)である。したがって,本件訴訟がA社の債権の管理や財産の不当な流出の防止等に関するものであることは明らかである。
また,本件訴訟においてB社と対立する当事者はA社の各破産管財人であるXであるのに対し,本件各委任契約の依頼者はA社であるが,破産手続開始の決定により,破産者の財産に対する管理処分権が破産管財人に帰属することになることからすると,本件において弁護士法25条1号違反の有無を検討するに当たっては,破産者であるA社とその破産管財人とは同視されるべきである。
そうすると,本件訴訟は,相手方Yにとって,同号により職務を行ってはならないとされる「相手方の・・・依頼を承諾した事件」に当たるというべきである。」
(3)解説
原審と最高裁の判断を分けた点は、破産管財人と破産者の関係でした。
原審はこの関係について「破産管財人による否認権の行使は(中略)破産法によって否認の権限が付与されている趣旨に従い、破産者の意思等とは無関係に行われるものであることや、破産管財人が破産者に属していた財産の管理処分権を行使するのも、破産者の代理人等としてではなく、独立した権限に基づいて総債権者の利益のためにするものであることに照らすと、破産管財人による請求の相手方(B社)の訴訟代理人である弁護士Yが、過去に破産者から上記請求に関連する法律事務等の委任を受けていたとしても、同弁護士らによる上記請求に係る訴訟行為をもって、弁護士法25条1号にいう「相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件」に係る職務行為と同視することはできないとしていました。
これに対して最高裁は両方を同視されるべきとしています。
Y弁護士が事案を受任した経緯には理解できるところがあるないわけではないですが、少なくともA社とB社は実質的に利害対立する立場にあったので、最高裁の決定の趣旨を踏まえれば、受任を差し控えるべき事案であったということができます。
国選弁護人の辞任
1 事例
刑事事件第1審において、国選弁護人に選任された弁護士が裁判所に辞任届を提出し、そのまま公判に出廷しなかった。しかし、その状況で裁判所は実質的に審理を継続した。
この点について、控訴審において①弁護人辞任届を提出しているに裁判所が解任しなかったのは違法である②公判に弁護士が出廷していないのに実質的な審理を行ったのは訴訟手続きの法令違反であるという主張が控訴審弁護人からなされた。
(東京高判昭和50年3月27日の事案)
2 裁判所の判断
①について
「現行制度の下においては、裁判所によって選任せられた国選弁護人は、裁判所の解任行為によらなければ、原則としてその地位が消滅することはなく、また正当な理由がなければ辞任の申出をすることができないものであって(弁護士法二四条参照)、しかもその正当理由の有無の判断は、選解任権を有する裁判所がすべきものと解せられる。」としており、裁判所が解任をするまでは国選弁護人の地位は残るほか、解任するかどうかについても裁判所が判断する旨を述べました。
②について
「前記国選弁護人らの辞任の申出に正当な理由が認められないとしてこれを解任しなかった原審の措置に、所論のような違法があると認めることはできない。また国選弁護人が辞任届を提出し、出廷しなかったのは、被告人らの責に帰すべき事由によるもので、それによって生ずる不利益は被告人らがみずから甘受せざるを得ないものとして、弁護人不出廷のまま実質審理を行ない判決するに至った原審の措置は、必要的弁護事件でない本件においては、やむをえなかったものというほかはない。すなわち、被告人らが、原審のとったグループ別審理方式をはじめその他の公判運営上の措置を不満として、そのような形態による裁判の進行をあくまで阻止しようとして、国選弁護人らを辞任せざるを得ない状況に追い込み、その結果弁護人らが出廷しなくなったとしても、それは被告人らがみずから望んだところと言わざるをえない。したがって、このような事情の下において、原審が弁護人不出廷のままで審理判決したからといって、被告人の弁護人依頼権の保障を無視した措置があるということはできない。」
として、被告人らの責めに帰すべき事由により弁護人が出廷しないような場合には、弁護人不出頭を理由として公判を継続したとしても違法はない旨判示しました。
3 解説
弁護士法第24条にある通り、弁護士は正当な理由がなければ官公署から委嘱を受けた事項を辞任できないとなされています。
国選弁護人も裁判所から依頼を受けた事項であるため、正当な理由がなければ辞任できません。
そして、国選弁護人については、刑事訴訟法にその解任事由が定めてある通り、裁判所が解任をすることとなっています。そのため、弁護人の一方的意思表示のみでは辞任できないということになります。
ただ、弁護人が辞任を申し出、それに相応の理由がある場合には、刑事訴訟法第38条1項に記載の事由が当てはまるようになることが多いと思われますから、解任となる可能性はあると思われます。
紛議調停手続
1 紛議調停手続とは
弁護士法第41条は、『弁護士会は、弁護士の職務又は弁護士法人の業務に関する紛議につき、弁護士、弁護士法人又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる』と定めています。
また、弁護士職務基本規程第26条は『弁護士は、依頼者との信頼関係を保持し紛議が生じないように努め、紛議が生じたときは、所属弁護士会の紛議調停で解決するよう努める』とされています。
紛議調停手続とは、弁護士法第41条に定める調停手続きのことを指していますが、法・基本規程は具体的な手続きに関する規定を置いておらず、実際の手続きは各単位会の会則等で定められています。
2 紛議調停手続の請求者
弁護士法第41条に記載の通り、紛議調停手続は「弁護士・弁護士法人・当事者・その他関係人」が請求できるとされています。
懲戒請求が「何人」でも可能であることとは異なり、請求の主体が限定されています。
また、職務基本規程第26条に記載の通り、弁護士と依頼者の間で紛議が生じたときは、弁護士はこの調停手続で解決するよう努めることが求められています。この規定の趣旨からすると、弁護士はいきなり依頼者に対して訴訟提起を行うのではなく、まずは調停によることを求められる(但し、訴訟提起をしたからといって訴訟が不適法になるものではない)ということになります。
3 紛議調停の対象
どのような問題が紛議調停手続の対象となるかについては、弁護士法に規定があり、「弁護士の職務又は弁護士法人の業務に関する」ものが対象とされています。
弁護士費用等の金銭に関する問題だけでなく、預かった書類の帰属や、事務処理についての責任など、広く弁護士の職務等に含まれるものが対象と考えられますが、弁護士の私的な問題(たとえば、弁護士が不倫関係にあった場合に、その不倫相手からの請求等)は対象にならないと考えられます。
4 手続
手続としては、調停の手続きとなるため、当事者に強制力等はなく、最終的に合意ができなければ調停不成立となります。
しかし、職務基本規程第26条がある関係で、調停を申し立てられた弁護士が調停に出頭しないことを繰り返すような場合には、それ自体懲戒事由となる可能性があります。
また、紛議調停手続は、いわば懲戒請求の前段階(法律・規則上調停を先行させなければいけない決まりはありませんが、調停不成立の場合懲戒請求をされるおそれは上がると思われます)とも言えますから、この手続きの中で和解を成立させることには大きな意味があると言えます。