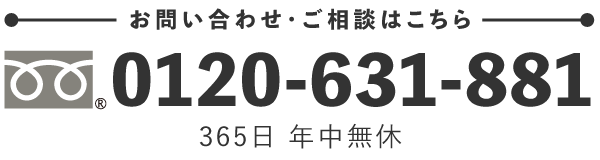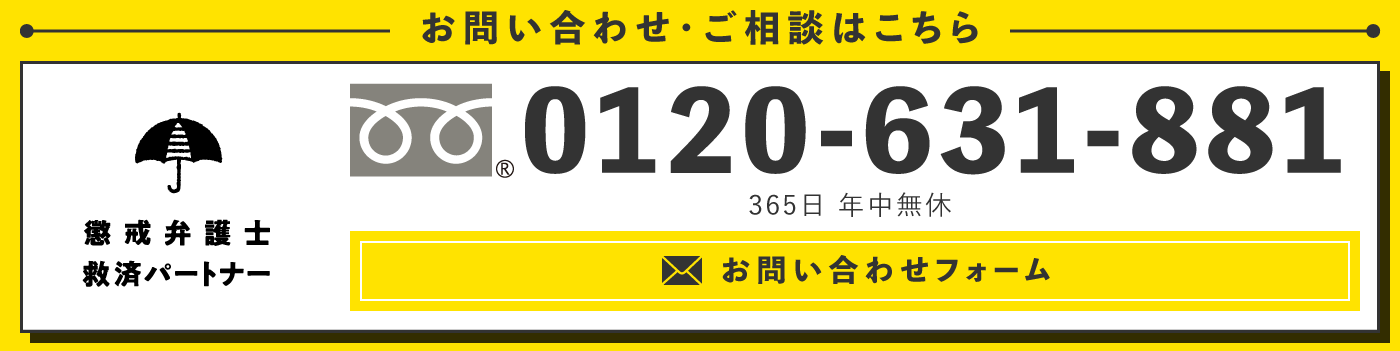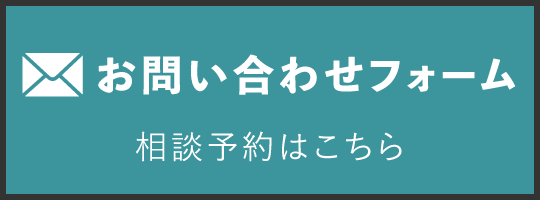Archive for the ‘懲戒事由(各論)’ Category
【弁護士が解説】国選弁護人として被疑者・被告人の家族から受け取ってもいいものとは?

【事例】
X弁護士は、Aさんの被疑者国選弁護人に選任されました。Aさんの留置されているB警察署は、X弁護士の事務所からも相当遠く、不便なところにありました。
Aさんは窃盗で逮捕・勾留されていたため、示談をする必要性があると考えたX弁護士は、示談金の用意をAさんに依頼しました。
最終的には示談が成立し、Aさんは不起訴により釈放されることとなりました。
このとき・・・
⑴示談金としてAさんの家族から現金を預かった。これは預かって問題ないだろうか。
⑵遠くのB警察署へ接見に行くことを不憫に思ったAさんの家族が、「どうせ私たちもAの接見に行きますので、一緒に車で送ってあげますよ」と提案してきた。X弁護士は車に乗っても問題ないだろうか。
⑶事例と異なり、仮にAさんが起訴されたとして、公判請求証拠の一部をコピーし、これをAさんに差し入れた。公判請求証拠のコピー代をAさんに請求することは問題ないだろうか。
【解説】
弁護士職務基本規程49条第1項は、「弁護士は、国選弁護人に選任された事件について、名目のいかんを問わず、被告人その他の関係者から報酬その他の対価を受領してはならない。」としています。
国選弁護人への報酬は法テラスを経由して国庫から支払われているので、この報酬以外を弁護士が受領することは国選弁護人の職務の公正さを疑わせ、ひいては国選弁護制度の公正さを害すると考えられています(「解説 弁護士職務基本規程第3版」142頁)。
そのため、国選弁護人は「対価の受領」を禁止されているのですが、反対に「対価」でなければ受領してよいようにも思えます。
⑴の事例は、あくまでも示談金としてお金を預かったのみです。これは私選や国選を問わず弁護士の手元に残るお金ではなく、最終的には被害者に支払われるお金ですから、これは当然「対価」には当たりません。ただ、端数などで余りが出た場合には、その余りを受領することは当然禁止されますので、返金をしなければなりません。
⑵は、車での移動という便益です。受領を禁止されているものは「対価」ですので、現金や有価証券などの金銭的な価値のあるものだけではなく、利益のようなものも含まれます。
問題は「名目のいかんを問わず(中略)報酬その他の対価」の受領を禁じていることをどのように解釈するかというところにあります。弁護活動の「対価」を受領することが問題となる場合、対価とはならない「実費」部分をどのように考えるかという問題が生じます。「名目のいかんを問わず」ということを強調するとたとえ実費であっても受領することが禁じられるという方向に解釈することとなります。反対に「報酬」が問題であると考えた場合、実費部分は受領することも許容されるという理解もあり得るところです。
⑵については、交通費相当額部分が問題となります。接見を行うと日当が法テラスから支払われますが、遠距離であるという事情がなければ、交通費という名目は別に支払われません。ただ、交通費込みで支払われていると考えると、既に法テラスから交通費部分の支払いを受けていることになりますから、重ねて交通費部分を関係者から受領することは問題となります。国選弁護士の報酬についてのQ&Aを見ると「算定基準では、近距離の交通費については基礎報酬で賄うことを前提」とすると記載されていますので、交通費部分も受領しているという考え方になるのではないかと思われます。ですので、⑵は断ることが適切であると考えられます。
対して⑶は、現在の国選弁護人の報酬体系の中では支払われない費用についての項目です。これについて実費相当額を受け取るべきかどうかが問題となりますが、厳しい考え方をとると、このような費用も受領することは禁じられるということになります。ただ、反対に弁護活動の充実ということであれば公判請求証拠を差し入れることは認められるべきでしょうし、この費用を受け取ったからといって弁護士が得をするような事態は生じません。慎重に検討し、金額の多寡なども踏まえ検討することが妥当であろうと思われます。また、事前に単位会の刑事弁護委員会やメーリングリストなどで尋ねるのも一つの手段です。
【弁護士が解説】依頼者からの要求は何でもするべきか、その危険性について解説

【事例】
X弁護士は、ある夫婦の妻Aから相談を受け、自身の夫であるBが浮気をしているので何かできることはないかと尋ねられた。
Aが持参してきた調査会社の報告書や、LINEの履歴などから見て、確かにBが不貞行為をしていることとはほとんど確実であると考えたXは、Aに対して離婚や慰謝料の請求を行うことができる旨を説明した。
しかし、Aとしてはそのようなことではとても収まりがつかず、Bの生活をめちゃくちゃにしてやりたいという希望があった。そのためAはXに対し、「あいつのことは絶対に許せない。今の生活ができないようにしてやりたいので、Bの実家や職場に先生から不貞慰謝料請求の内容証明郵便を出してもらいたい」と告げた。
Xはこのようなことに応じてよいだろうか。
【解説】
XにとってAは依頼者となりますので、弁護士職務基本規程第22条の「弁護士は、委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務を行うものとする。」という規律が当てはまります。そのため、Aが希望することについては基本的にその意思を尊重すべきであると言えます。
しかし反面、弁護士である以上、「弁護士は、事件の受任及び処理に当たり、自由かつ独立の立場を保持するように努める。」(同20条)、「弁護士は、良心に従い、依頼者の権利及び正当な利益を実現するように努める。」(同21条)、「弁護士は、名誉を重んじ、信用を維持するとともに、廉潔を保持し、常に品位を高めるように努める。」(同7条)などの規程も定められています。そのため、たとえ依頼者の希望であったとしても、何でもそのまま行ってよいということにはなりません。
今回の事例で考えると、不貞行為をしているということは通常人に知られたくないものであることは間違いありません。また、公になっているようなもでもないですので、いわゆる「秘密」に属することは明らかです。このような秘密について、第三者に口外することは当然守秘義務との関係で問題となります。弁護士職務基本規程23条の秘密保持義務は「依頼者について」の秘密と限定しているものの、弁護士法23条の守秘義務にはそのような限定はありません。この弁護士法23条の守秘義務については、依頼者の秘密に限定されるのか第三者のものも含むのか争いがありますが、日弁連では第三者のものも含むと解釈しています。そのため、今回の事例と同様のケースで、相手方勤務先に離婚事件に関する事実をメールで送信したような事案で弁護士法上の守秘義務違反を認めたケースがあります。
不貞行為があった場合、法的権利として認められるのは離婚や慰謝料の請求が基本的なものです。相手方配偶者の生活環境を破壊するということは、正当な利益ということはできないと考えられますので、これを実現することは、守秘義務違反の問題は別としても基本規程21条や7条の問題を生じさせます。ですので、X弁護士としてはAの依頼を断るべきですし、これで信頼関係が破壊されるようであれば委任契約の解約をする事案ということになります。
今回の事例では、Bの連絡先などが確実に分かっていると言えるケースでしたので、勤務先や実家に連絡をすることが問題となるケースでした。ただ、今回の事例とは異なり、Bの連絡先が勤務先や実家以外全く分からないということは十分あり得ます。そのような場合、弁護士から連絡をすることはやむを得ない場合も存在すると思われます。ただ、そのような場合であっても、事件の内容や弁護士の主張を過度に記載するなどした場合にはやはり同様の問題が生じると思われますので、「連絡が欲しい」程度の簡単な記載に留めるべきであろうと思われます。
【弁護士が解説】事件記録の取扱いについて

【事例】
X弁護士は、ある交通事件の加害者側弁護を引き受け、その事件は公判請求の後執行猶予付き判決となりました。
その後、被告人であったAから、民事の方の損害賠償請求が被害者側から来ているとのことで、その事件も受任して欲しいとの依頼があったため、別途委任契約を締結し、民事訴訟も担当することとなりました。
訴訟の中では過失割合及び傷害結果に対する因果関係が問題となりましたが、これらの問題点は既に刑事裁判の中でも問題となっていました。
X弁護士としては、捜査の過程で警察が作成し、刑事事件の公判で証拠請求された甲号証の一部が有利になると考えたため、刑事裁判の際に謄写した書証を民事裁判に提出しました。
このような行為は問題とならないのでしょうか。
【解説】
刑事事件の公判に際して謄写した記録についての規定は、刑事訴訟法にあります。
被告人若しくは弁護人(第四百四十条に規定する弁護人を含む。)又はこれらであつた者は、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、次に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供してはならない。
一 当該被告事件の審理その他の当該被告事件に係る裁判のための審理
二 当該被告事件に関する次に掲げる手続
イ 第一編第十六章の規定による費用の補償の手続
ロ 第三百四十九条第一項の請求があつた場合の手続
ハ 第三百五十条の請求があつた場合の手続
ニ 上訴権回復の請求の手続
ホ 再審の請求の手続
ヘ 非常上告の手続
ト 第五百条第一項の申立ての手続
チ 第五百二条の申立ての手続
リ 刑事補償法の規定による補償の請求の手続
と定めています。
この定めの中に民事訴訟は含まれていません。そのため、民事裁判で刑事事件の際に謄写した証拠をそのまま請求することは、この刑事訴訟法の規定に違反する違法行為となります。
実際このような証拠請求をして、懲戒処分となったケースもあります。
それでは、このように刑事裁判の証拠が使用したい場合にはどのようにすればよいのでしょうか。
方法としては、弁護士法23条の2による照会を行ったり、刑事確定訴訟記録法に基づく請求をする、民事の受訴裁判所からの送付嘱託を検討するなどが考えられます。なお、不起訴記録であっても23条照会等で開示されることがあるようです。
刑事事件の証拠は、法律の規定によらない限り外部への流出が予定されていないものです。昨今、取調べ状況に対する国賠訴訟において、取調べの録音録画影像の取扱いが問題となりました。弁護側が既に保有しているのに民事裁判に提出できないという歯がゆい取扱いではありますが、現在の規定上はやむを得ないところです。
刑事事件の記録は慎重に取り扱いましょう。
【弁護士が解説】職務上請求を違法に取得した場合にはどのような処分が予想されるか

【事例】
X弁護士は、なじみの不動産会社から、Yが所有する不動産について、近々再開発の計画があり値上がりする可能性があること、
Y自身についても末期のがんで入院中であり、余命がそう長くないということを聞かされた。
そのため、X弁護士は、不動産会社から依頼されたわけでも、Yから依頼されたわけでもないにも関わらず、Yが住む役所に対して住民票及び戸籍謄本の職務上請求を行った。
その際、目的欄に「相続人確定のための調停申し立てのため」と虚偽の内容を記載した。
【解説】
弁護士を含めた一部の士業には、戸籍や住民票といった個人情報を役所に請求し、取得することが認められています。ただ、これは無制限に認められているわけではなく、あくまでも戸籍法の範疇で認められているにすぎません。
戸籍法で弁護士が戸籍を取得することができるとされているのは、戸籍法10条の2によります。
第十条の二 前条第一項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。
③ 第一項の規定にかかわらず、弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。次項において同じ。)、司法書士(司法書士法人を含む。次項において同じ。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。次項において同じ。)、税理士(税理士法人を含む。次項において同じ。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。次項において同じ。)、弁理士(弁理士法人を含む。次項において同じ。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該業務の種類、当該事件又は事務の依頼者の氏名又は名称及び当該依頼者についての第一項各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。
④ 第一項及び前項の規定にかかわらず、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士又は弁理士は、受任している事件について次に掲げる業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該事件の種類、その業務として代理し又は代理しようとする手続及び戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。
一 弁護士にあつては、裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務(弁護士法人については弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十条の六第一項各号に規定する代理業務を除き、弁護士・外国法事務弁護士共同法人については外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第八十条第一項において準用する弁護士法第三十条の六第一項各号に規定する代理業務を除く。)
⑤ 第一項及び第三項の規定にかかわらず、弁護士は、刑事に関する事件における弁護人としての業務、少年の保護事件若しくは心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第三条に規定する処遇事件における付添人としての業務、逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐人としての業務、人身保護法(昭和二十三年法律第百九十九号)第十四条第二項の規定により裁判所が選任した代理人としての業務、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第十三条第二項及び第三項の規定により裁判長が選任した訴訟代理人としての業務又は民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三十五条第一項に規定する特別代理人としての業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、弁護士の資格、これらの業務の別及び戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。
いずれの場合であっても、弁護士であるからという理由だけで請求が認められているわけではありません。少なくとも受任している事件に関しての請求でなければなりませんし、利用目的を記載しなければなりません。同じような規定は住民基本台帳法12条の3にも存在します。
そのため、たとえ弁護士であったとしても、無制限に戸籍等の請求をしてよいわけではありません。今回のX弁護士の行為は、①誰から受任をした事件でもない点②虚偽の目的を利用目的欄に記載した点に問題があり、本来であれば住民基本台帳法、戸籍法上の取得が認められないような場合であったと言えます。
このような職務上請求の目的外使用は、法を犯すものですから厳しく処分される可能性があります。
今回の事例ではそこまでの記載がありませんが、違法に取得された住民票が第三者に交付されたり、これによって記載されている者らに何らかの損害が発生したような場合には、一層重い処分が予想されます。
単なる目的外取得だけであれば戒告で済む可能性もありますが、別の問題が生じているような場合には業務停止の可能性があります。
今回のような事例の場合、取得されたYらに対して謝罪をするほか、取得するに至った経緯(受任間近であったなど)の事情を説明して、処分の軽減を求めることが考えられます。
【最後に】
弁護士が懲戒請求を受けた場合、弁護士は代理人ではなく紛争の当事者となります。代理人として紛争にあたるのはいつもどおり出来たとしても、当事者として紛争にあたる場合には思った通りの活動が出来ないということはあり得ます。代理人を入れることで、事実をしっかりと整理し、懲戒処分の回避や軽減につながる可能性が上がります。
加えて、勤務弁護士について懲戒請求を受けた場合に、実際に懲戒処分がなされれば事務所全体の評判に関わる可能性があります。当該勤務弁護士について解雇・業務委託契約解除をしたとしても悪影響が払拭できない可能性もあります。
勤務弁護士が懲戒請求を受けている場合も含めて、懲戒請求手続について詳しく、懲戒請求に対する弁護活動経験が豊富な弁護士への相談を検討している先生方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
【弁護士が解説】訴訟上の書面等に不適切な記載をしてしまった場合にどのようにすればよいか

【事例】
X弁護士は、ある夫婦の女性の側から夫との離婚調停を依頼されました。女性曰く、夫は一切家事をせず、家にお金を入れることもなく、普段自分に暴言ばかり吐いている
とのことでした。
X弁護士が聞いていても、女性の境遇はあまりにも不憫であり、離婚をして自由になる方が幸せであろうと思えるほどでした。
そこで、X弁護士が家庭裁判所に離婚調停を申し立てたところ、夫の側から反論の書面が提出されました。
その書面には、妻が行っていることは全てうそであること、自分は妻を愛していること等が滔々と記載されていました。
これを読んで激高したX弁護士は、次の書面で「この夫は人でなしであり、人間の心を持たない化け物である」等と記載した書面を提出した。
【解説】
弁護士職務基本規程第6条によると、「弁護士は、名誉を重んじ、信用を維持するとともに、廉潔を保持し、常に品位を高めるように努める」とされています。
今回のX弁護士の書いた書面は、たとえ夫側の主張が事実に反する虚偽の主張であったとしても、虚偽であることを主張するものではなく、単にその人格を否定する内容となっています。
このような内容の書面は、いくら依頼者のためであるとしても、品位ある書面であるとは言えません。
ただ、さすがに弁護士個人の感情としてあからさまに名誉を毀損し、品位を害する書面を記載することはそれほど多くないと思われます。
実際には、依頼者から感情的な表現をすることを依頼され、弁護士もこれに同情して記載してしまうのではないかと予想されます。
それでも、たとえ依頼者からの依頼であったとしても、最終的には弁護士名義で書面を出すのですから、弁護士としての基本的なルールは遵守する必要があります。
だからと言って、依頼者自身が感情的な表現を記載した文書を、弁護士が証拠として提出することも、不法なものに加担することになりかねませんので注意する必要があります。
ですので、対外的に発出する文書や、証拠については、提出前に一旦見返し、冷静な気持ちで本当に提出してよいものかどうかを考える必要があります。
また、このような事案の場合には弁護士の側に非があることが比較的はっきりしているので、示談交渉を行い、謝罪等をして処分の軽減を目指していくことも考えられます。
【最後に】
弁護士が懲戒請求を受けた場合、弁護士は代理人ではなく紛争の当事者となります。代理人として紛争にあたるのはいつもどおり出来たとしても、当事者として紛争にあたる場合には思った通りの活動が出来ないということはあり得ます。代理人を入れることで、事実をしっかりと整理し、懲戒処分の回避や軽減につながる可能性が上がります。
加えて、勤務弁護士について懲戒請求を受けた場合に、実際に懲戒処分がなされれば事務所全体の評判に関わる可能性があります。当該勤務弁護士について解雇・業務委託契約解除をしたとしても悪影響が払拭できない可能性もあります。
勤務弁護士が懲戒請求を受けている場合も含めて、懲戒請求手続について詳しく、懲戒請求に対する弁護活動経験が豊富な弁護士への相談を検討している先生方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
【弁護士が解説】弁護士報酬を請求する際にトラブルとなった場合にはどのように対応すればよいか

【はじめに】
弁護士として事件を受任し、時間と労力をかけて、なんとか当初の見立て通りの結果が出たとします。仮に弁護活動の結果自体は満足のいくものであったとしても、法的紛争が起こっているからこそ弁護士にお金を払って依頼するのであり、事件が終了したのであれば弁護士にお金を払いたくないと考えてしまうのはある意味合理的なのかもしれません。したがって、事件終了時にトラブルになる可能性が高い問題の一つとして、報酬に関する問題が出てきます。
今回は、弁護士報酬に関してトラブルになった事例を一つ取り上げて、弁護士報酬トラブルでの懲戒請求について説明します。
【事例】
X弁護士は、登録15年程度の弁護士であり、個人事業主として法律事務所を経営していた。あるとき、依頼者男性Yから、相手方女性Zとの離婚調停、審判、裁判を受任した。離婚、財産分与、親権に関する結果についての成功報酬額は委任契約書に記載されていた。経済的利益の計算方法は法律事務所の基準による旨を説明しており、当該基準は法律事務所のホームページにも記載されていた。X弁護士の見通し説明としては、離婚を防ぐこと、子の親権をYとすることは困難であるものの、Zの不貞等の関係やZ側の財産分与に関する主張との関係で、財産分与についてはZ側の請求額から一定程度が減額される可能性があるとのことであった。着手金は、受任の時点でYからXに支払われた。
受任から約3年後、結局審判を経てYとZは正式に離婚することとなり、子の親権者はZとされたものの、YがZに支払わなければならない金額としてはZの請求額よりも1000万円程度減額された。 弁護士報酬は、着手金、成功報酬、日当を合わせると合計400万円程度となった。X弁護士から依頼者Yに上記報酬を請求したところ、Yから、財産分与については一定の結果が出たものの自分としては親権を獲得したいというのが一番の希望であって、事件解決にも時間がかかっているので報酬には不満であること、弁護士報酬についても説明が十分になかったこと、他の弁護士事務所よりも弁護士報酬が高いので弁護士報酬を払いたくないと言った不満が出た。これに対し、X弁護士は料金は契約書通りであるので必ず支払ってもらう旨Yに伝え、それから3か月ほどYに内容証明等で督促をし続けたがYは一向にZが上記弁護士報酬と着手金の差額を支払おうとしなかった。そのため、XはZに対し、弁護士報酬の合計を350万円とする旨の提案をしたが、Yはそれにも応じなかった。やむなく、Xは所属弁護士会に対して紛議調停を申し立てたところ、それに腹を立てたYがXを懲戒するよう、Xが所属する弁護士会に懲戒請求を行った。
(事例は、フィクションであり、実在の弁護士、依頼者、その他個人、会社、団体とは一切関係ありません。)
【対応方法】
弁護士として仕事をしていると、事件が終わったところになってこのように元依頼人から報酬についての不満を出されることがあるかと思います。このような場合に実際に懲戒処分がされる事案については、ある程度共通した事情があると考えられます。
本件に関係しそうな規定は以下です。
弁護士職務基本規程
(名誉と信用)
(弁護士報酬)
第二十四条 弁護士は経済的利益事案の難易時間及び労力その他の事情に照らして 適正かつ妥当な弁護士報酬を提示しなければならない。
弁護士法
(懲戒事由及び懲戒権者)
第五十六条 第1項 弁護士及び弁護士法人は、この法律(弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員又は使用人である弁護士及び外国法事務弁護士法人の使用人である弁護士にあつては、この法律又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律)又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
本記事を作成するために調べた限りだと、弁護士報酬が単に他の事務所よりも高いからといってそれだけで懲戒処分がなされる事案は多くないように思われます。懲戒処分がなされるような事案は、契約の際の説明に大きな不備があるとか、あまりにも相手方に配慮がない請求の仕方を行っている等の要素が目立っているように思います。本件について考えると、弁護士報酬や計算基準については契約書に記載されていますが、経済的利益の計算基準についてはX弁護士の法律事務所基準によるとし、実際にホームページに記載があるとはいえ、契約の際に具体的には説明を行っていません。この点については、「基準」の予測可能性がどの程度あるか、「基準」について依頼者が疑義を申し立てることが有ったかどうかが問題になりそうです。
また、弁護活動が完全に成功したわけではないところで契約書通りの請求を行っていますが、依頼人によってはそのような請求をとらえて懲戒請求において主張してくる可能性があります。弁護士報酬の説明状況等について具体的に説明出来るようにしておくことで、実際に懲戒処分を避けることができる可能性が上がるでしょう。
最後に、X弁護士側から紛議調停を申し立てた点ですが、具体的な交渉状況を説明し、これがやむを得なかったことを説明する必要があります。
【最後に】
上に挙げた事例とは異なり、弁護活動に際して契約書を作成せずに弁護活動に入り、弁護士報酬を請求して懲戒される、というパターンは非常に典型的なパターンといえます。上に挙げた事例では、契約書もありますし、依頼者に対して相当な説明をした、という主張は比較的しやすいかも知れません。しかし、懲戒処分は厳密な証拠裁判主義にのっとって行われる民事・刑事裁判とは異なりますので、懲戒対応の経験やノウハウを持つ弁護士が代理に入ることで、納得のいかない処分を回避出来る可能性は上昇すると考えられます。
加えて、勤務弁護士が懲戒処分を受ければ、当該勤務弁護士について解雇・業務委託契約解除をしたとしても法律事務所への悪影響が生じるのを防げない可能性があります。
勤務弁護士が懲戒請求を受けている場合も含めて、懲戒請求手続のノウハウを持つ弁護士への相談を検討している先生方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
【弁護士が解説】会費の滞納により懲戒処分となるのはなぜか

【事例】
A弁護士は、B県弁護士会に所属している弁護士です。
B県でも、弁護士数がかなり増えてきたことから、A弁護士の売上自体は年々減少していました。
弁護士である以上、毎月の会費の支払いが必要となってきます。
しかし、A弁護士はなかなかその費用が捻出できず、支払が滞りがちになっています。
【解説】
弁護士会は強制加入団体となっています。
法律上の制度でいえば、「弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない。」(弁護士法8条)とされていますので、弁護士は全員日弁連に備えている名簿に登録されていることになります。
ただ、直接日弁連に登録を求めることはできず、「弁護士となるには、入会しようとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録の請求をしなければならない。」(弁護士法9条)となっており、必ずいずれかの弁護士会を経由して日弁連に登録の請求をする必要があります。
そのため、全ての弁護士は①どこかの単位会に入会し②日弁連の名簿に登録される必要があります。
この結果というわけではないですが、弁護士会の「会費」と呼ばれるものには、日弁連等の会費と単位会の会費の2種類があることになります。
この会費支払いの根拠となっているものですが、日弁連については「日本弁護士連合会会則」第95条で「弁護士である会員は、本会の会費として月額一万二百円を、所属弁護士会を経て、本会に納めなければならない。」とされており、会則上会費の支払いが義務となっています。また日弁連ではこのほかに特別会費(会則95条の3)についての規定があり、こちらも支払いが義務となっています。
これに対し、単位会の会費については、各単位会の会則により支払いが義務付けられているところです。
弁護士には、「所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会則を守らなければならない」(弁護士法22条)という義務があります。会則により会費の支払いが義務付けられている以上、会費を支払わないという行為は会則違反行為となります。
そのため、弁護士法56条の懲戒事由としての「会則違反」に該当し、何からの懲戒を受けるということになってしまいます。
ただ、会費の滞納をしたからと言ってすぐに懲戒処分を受けるわけではありません。日弁連の会則上は6か月以上の会費の滞納があった場合に懲戒することができると定めています(会則97条)。
実際に懲戒事例として公告されているようなものは、それなりの期間の滞納があったり、未納が繰り返されている事案の他、手続の最中に会費を支払わなかった例が目立ちます。
そのため、会費滞納の事案におけるもっとも最良の行為は、速やかに未納分の会費を支払うということになります。
それでも金銭的にどうしても会費が支払えない等という場合には、やむを得ず処分を受けるということになります。
処分の内容は滞納している金額(月数)によるところですが、何回も未納で処分を受けていたり、未納金が大きくなるような場合には、退会命令の処分となってしまいます。
弁護士として活動を継続するためには速やかに納付することが必要です。
【最後に】
弁護士が懲戒請求を受けた場合、弁護士は代理人ではなく紛争の当事者となります。代理人として紛争にあたるのはいつもどおり出来たとしても、当事者として紛争にあたる場合には思った通りの活動が出来ないということはあり得ます。代理人を入れることで、事実をしっかりと整理し、懲戒処分の回避や軽減につながる可能性が上がります。
加えて、勤務弁護士について懲戒請求を受けた場合に、実際に懲戒処分がなされれば事務所全体の評判に関わる可能性があります。当該勤務弁護士について解雇・業務委託契約解除をしたとしても悪影響が払拭できない可能性もあります。
勤務弁護士が懲戒請求を受けている場合も含めて、懲戒請求手続について詳しく、懲戒請求に対する弁護活動経験が豊富な弁護士への相談を検討している先生方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
【弁護士が解説】弁護士が委任契約を行う際、意思能力の点で注意しなければならない点があるか

【事例】
X弁護士は、ある高齢の女性Aから、親族間の財産争いについて相談を受けました。
Aが話すところによると、自身の長女Bとある土地をめぐってトラブルになっており、Aは自分の所有権を主張しているものの、Bは自身の夫の所有権を主張しているとのことでした。
ただ、最終的にAが死亡すると、相続人はBだけということもあり、いずれはBのものになる土地でもありました。
それでもAとしては、自身が生きている間に子どもと争いになることは望んでおらず、何とか穏当に解決できないかということでXのところに相談に来たのでした。
これを聞いたXは、自身が代理人となってBと交渉することを提案し、Aとの間で委任契約書を作成し、Aの代理人として土地所有権の主張を行いました。
これに対しBから「XはAから弁護士費用をだまし取っている」という懲戒請求が出されました。X弁護士としてはどうすればよいのでしょうか。
【解説】
親子間の財産争い自体は、それほど珍しいものではなくなりました。特に、子どものうち、親に味方する子どもと、争う子どもに別れるということもよくあります。
このような場合に、争っている子どもの側から、親側代理人弁護士に対して懲戒請求がなされることがあります。
その際よくなされる主張が「自身の親(委任契約者)は認知症であるから、委任契約を締結できるはずがない」という主張です。
ただ、成年後見人がいるなら当然後見人との間で契約する必要がありますが、成年後見制度を利用していない状況で、認知症であるから直ちに弁護活動を依頼できないということになってしまうと、その方の防御権を極めて制約してしまうことになります。
反対に、だからと言って自由に契約することを許してしまうと、委任契約の内容を全く理解できていないような場合であっても問題がないということになってしまい、依頼者保護の観点から適当ではありません。
最終的には弁護士の判断で契約するかどうかを決定することになりますが、その際ポイントとなるのは以下のような点です。
①まず、相談時の話の内容として、話の筋や内容に問題がないかです。もちろん過去のことを話すような場合に時系列が前後してしまうことは誰でもあるところですが、全く脈絡のない話が続いたり、およそ信じがたいような話がなされているような場合には意思能力を疑う必要があります。
②次に、どのような場所で相談を受けるかです。法律事務所の方に来てもらえるような場合や、役所などの窓口で相談をする場合はよいですが、相談者の体調面などから病院、施設で相談を受けるような場合は注意が必要となります。
③最後に、実際に認知症の診断がなされているかも問題となります。もちろん、人によっては知られたくない情報であるため、直接的に聞き出すことは困難な面はあります。ただ、周囲の人(味方となる親族)に聴取したり、本人の要介護度などを参考にすると判断能力について参考にすべき情報が得られることがあります。
【最後に】
弁護士が懲戒請求を受けた場合、弁護士は代理人ではなく紛争の当事者となります。代理人として紛争にあたるのはいつもどおり出来たとしても、当事者として紛争にあたる場合には思った通りの活動が出来ないということはあり得ます。代理人を入れることで、事実をしっかりと整理し、懲戒処分の回避や軽減につながる可能性が上がります。
加えて、勤務弁護士について懲戒請求を受けた場合に、実際に懲戒処分がなされれば事務所全体の評判に関わる可能性があります。当該勤務弁護士について解雇・業務委託契約解除をしたとしても悪影響が払拭できない可能性もあります。
勤務弁護士が懲戒請求を受けている場合も含めて、懲戒請求手続について詳しく、懲戒請求に対する弁護活動経験が豊富な弁護士への相談を検討している先生方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
係争権利の譲り受け
1 係争権利の譲受の禁止
弁護士法第28条は、「弁護士は、係争権利を譲り受けることができない。」としています。
これは、弁護士が事件に介入することで利益を上げることが、弁護士としての品位を失い、格子柄性を害すると考えられたからです。
そして、本条に違反した行為については、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金という刑事罰が科されています。
2 係争権利
係争権利としてどのようなものが対象となるかについては学説が分かれています。
1つ目は、現に訴訟、調停等紛争処理機関に係属中の権利であるとする考え方であり、もう一つはそれに限らず紛争中の全ての権利を指すとする考え方です。
裁判例には前者の説が多く、大審院時代の裁判例では「係争権利とは訴訟の目的と為りたる権利にして現に其訴訟中に係るものを指称し権利実行の為めに申立てられたる競売の目的と為りたるものは訴訟の目的物に非さる」と判断し、競売物件を譲り受けても違法ではないとしました。
先ほど述べた通り、本条違反の行為には刑事罰が科せられる以上、罪刑法定主義を前提に検討しなければならないため、より制限的に解釈する方が妥当であろうと思われます。
3 譲り受け
条文上の譲り受けには、有償無償の区別がありませんでの、いずれの場合でも本条に該当すると思われます。
また、売買、交換、贈与等の法形式も問われていませんので、いずれの形式であるかも問題となりません。
ただ、弁護士が、別の者を代理して係争権利を譲り受けた場合、双方代理の問題が生じる可能性はありますが、このような場合には本条に該当しないと思われます。
4 本条違反の行為
弁護士法28条に違反してなされた行為は、公序良俗に違反するような事情があれば無効となりますが、そうでなければ直ちに効力を否定されるものではないとされています。
【弁護士が解説】事件の相手方に対する言動で懲戒請求を受けるのか

【はじめに】
弁護士として民事訴訟、刑事訴訟、その他対手方との交渉事をやっていれば、事件の相手方や、関係者、裁判官、検察官等に対して様々な思いを持つことがあるでしょう。自分の中で思っているだけであり、実際の行動や言葉に出ることがなければ、弁護士懲戒の問題になることは通常考えられません。
しかし、もし実際に相手方や関係者に対して何らかの行為に出てしまった場合や、自分の思っていることをそのまま言ってしまったような場合には、品位を欠く言動をしたと言うことで懲戒処分の対象になってしまう可能性があります。
今回は、相手方に対して発した言葉が原因で懲戒請求をされた場合をモデルにして、解説していきたいと思います。
【事例】
A弁護士は、登録4年程度の弁護士であり、法律事務所に勤務しています。勤務している法律事務所は、交通事故や債務整理のほか、私選の刑事弁護などもある勝っています。
A弁護士は、登録4年程度ということで、民事事件、刑事事件共に様々な種類の事件を経験し、自分でも「一通りの事件をやってきたな」という認識でいました。依頼人との関係で何かクレームが出るというようなこともなく、書面の起案など普段の仕事に関しても事務所内からの評判は良かったようでした。そのため、A弁護士は、「自分もなかなか成長した。それにしても、周りの弁護士はなかなか仕事が出来ない人が多い。自分の事務所以外の弁護士と来たら期日は守らないし書面もスカスカだ。よくそれで依頼人から弁護士報酬を領収できるものだ。自分事務所の弁護士にしたって、自分より全然働かないくせして自分とそう変わらない給料をもらっている。全く不公平なものだ」等と普段から考えるようになっていました。
ある日の法廷で、A弁護士は、弁護士登録をしてから30年ほど経った相手方代理人Bから、「貴職の主張はなかなか法的構成が見えてこない。やはり君のバッジの色がまだ金ピカみたいだし、経験が浅いみたいだね」というようなことを言われました。
それに対してA弁護士は、「どこに目付けてんだクソジジイ。純金バッジだ。そんなことも見抜けねえから証拠もスカスカだし敗訴同然の和解勧奨をされるんだ。」と言ったところで、裁判官が「それくらいで」とA弁護士に対して注意をしました。その後もA弁護士は、「何だお前は。弁護士バッジが酸化して真っ黒になっているから偉いとでもいうのか?そんなものは登録して1年の新人だって家にあるもので作れる。お前はカネがないから真っ黒の弁護士バッジでがんばってるんじゃねえのか?」と続けました。法廷には傍聴人の姿はありませんでした。
後日、A弁護士は相手方のB弁護士から懲戒請求をされました。
なお、A弁護士が言う通り、A弁護士は実際に純金バッジの貸与を受けています。また、当該訴訟で相手方代理人B弁護士は、ほとんど敗訴といえるような和解勧奨を受けています。
(事例は、フィクションであり、実在の弁護士、依頼者、その他個人、会社、団体とは一切関係ありません。)
【対応方法】
このように訴訟活動の当否とは直接関係がない弁護士の言動に関する事案では、基本的に全く同じ言動で懲戒を受けることはありません。
しかし、懲戒処分を受ける可能性が高いか低いかを判断するに当たって、ある程度共通する判断要素があるように考えられます。
関係すると思われる規定は以下です。
弁護士職務基本規程
(名誉と信用)
第六条 弁護士は、名誉を重んじ、信用を維持するとともに、廉潔を保持し、常に品位を高めるように努める。
弁護士法
(懲戒事由及び懲戒権者)
第五十六条 第1項 弁護士及び弁護士法人は、この法律(弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員又は使用人である弁護士及び外国法事務弁護士法人の使用人である弁護士にあつては、この法律又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律)又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
訴訟活動等にあたって必要性がない言動での弁護士懲戒の事例は複数ありますが、懲戒処分がなされている事例で共通しているのは、相手方が特に何もしておらず、相手方に全く落ち度がないような事例です。特に、相手方から侮辱的言動を受けていないのに上記のような言動を行った場合や、唐突に上記のA弁護士のような言動を行った場合は懲戒処分を受けやすいと考えられます。また、相手方から「懲戒請求をせざるを得ないかも知れない」と言われたのに侮辱的言動を続けた場合も懲戒処分の可能性が高まりやすいと考えられます。
また、周囲の状況も考慮されている可能性が高いです。法廷で傍聴人が一定数いるような場合や、裁判長からの注意や訴訟指揮が有ったような場合で侮辱的言動を行い、懲戒処分を受けている事例が散見されます。
特に訴訟活動等にあたって必要性がない言動での懲戒請求を受けた場合は、当該言動が行われた経緯や、状況についての主張をよく検討することが、懲戒処分を受ける可能性を下げる上で重要となってくると考えられます。
【最後に】
弁護士が懲戒請求を受けた場合、弁護士は代理人ではなく紛争の当事者となります。代理人として紛争にあたるのはいつもどおり出来たとしても、当事者として紛争にあたる場合には思った通りの活動が出来ないということはあり得ます。代理人を入れることで、事実をしっかりと整理し、懲戒処分の回避や軽減につながる可能性が上がります。
加えて、勤務弁護士について懲戒請求を受けた場合に、実際に懲戒処分がなされれば事務所全体の評判に関わる可能性があります。当該勤務弁護士について解雇・業務委託契約解除をしたとしても悪影響が払拭できない可能性もあります。
勤務弁護士が懲戒請求を受けている場合も含めて、懲戒請求手続について詳しく、懲戒請求に対する弁護活動経験が豊富な弁護士への相談を検討している先生方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。