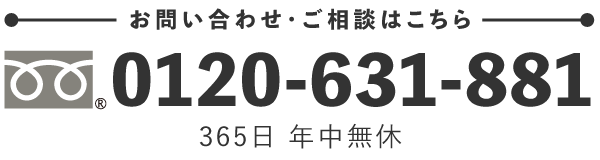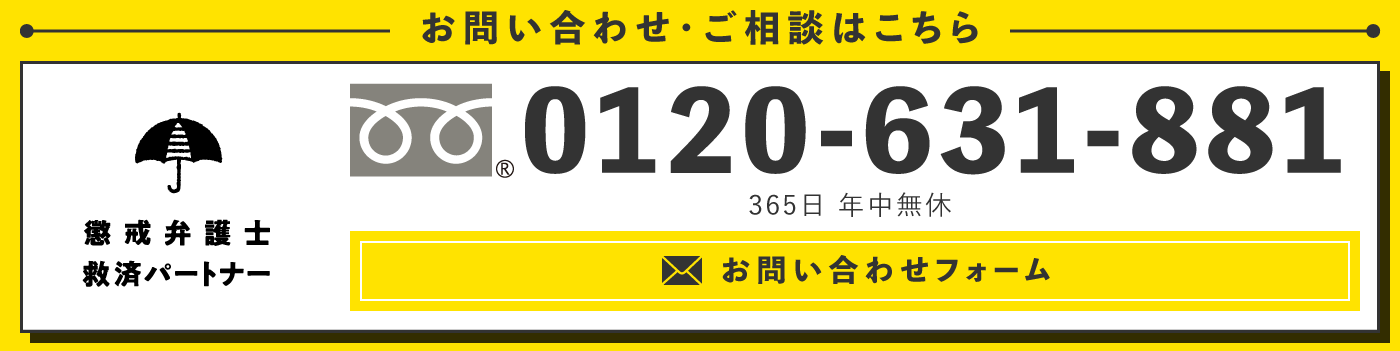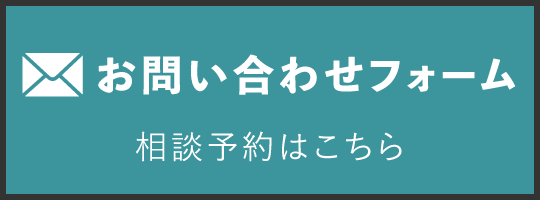Archive for the ‘過去の懲戒事例’ Category
【弁護士が解説】弁護士費用の未精算はどのような問題を生じさせるか
【事例】
X弁護士は、Aさんから交通事故損害賠償事件(被害者側)の依頼を受け、保険会社との交渉に当たり、保険会社から保険金を受領しました。
X弁護士がAさんから依頼を受けた当初、Aさんが被害者であることは明らかであり、それなりまとまった金額を受領できることが予想されたことから、委任契約締結時にはX弁護士は費用を貰わず、保険会社から取得出来た金額に対する一定の割合を報酬として差し引き、残った金額をAさんに渡すという契約を締結していました。
X弁護士は、保険会社との示談交渉が完了し、保険金の受領が終了したにもかかわらず、Aさんに保険金の一部の支払いをしないままでいました。このようなことはどのような問題を生じさせるでしょうか。
【解説】
「自由と正義」の末尾に、懲戒の事例が掲載されていますが、事案のように預かったお金を返金しないというケースは度々登場します。
弁護士職務基本規程45条によれば、「弁護士は、委任の終了に当たり、委任契約に従い、金銭を清算した上、預り金及び預り品を遅滞なく返還しなければならない。」とされています。保険会社からの保険金は、依頼者のために第三者あら預かったお金ですから、預り金に該当し、終了時に速やかに返金する必要があります。
事例のケースのように、保険金や遺産等のまとまったお金を返金しなかった場合、業務停止などの重い処分も十分予想されます。そのため、速やかに返金をする必要があります。
ところで、仮に返金できない何らかの事情が発生した場合はどうでしょうか。たとえば、依頼者から「今、妻と離婚しそうで、このまま自分の口座に保険金が流れ込んでしまうと、この保険金も遺産分割の対象となってしまう可能性がある。そのため、先生がしばらく預かっておいてください」等と言われた場合には、どうすればよいでしょうか。
この依頼者の述べている内容が法的に正確かどうかは別として、返金ができない事情(病気や行方不明など)がない以上、仮に依頼者側に事情があったとしても規程上は返金すべきでしょう。
【弁護士が解説】保証人と主債務者の両方の代理人となることは許されるか

【事例】
X弁護士は、Aさんから貸金返還請求をされている旨の相談を受けました。見ると、Aさんを被告として訴えが提起されており、Aさん自身も金銭を借りた事実や、現時点で返済をしていないことを認めています。
ところで、この借金をするにあたり、Aさんは自身の兄のBさんを連帯保証人としていました。Aさん自身には支払い能力はなく、今後Bさんも訴えられる可能性は相当高い状況にあると思われました。Aさんからは「兄も一緒に受けてあげて欲しい」と依頼されています。
X弁護士として、Bさんの事件も受任することに問題はないでしょうか。
【解説】
今回の問題は、主債務者の代理人が、連帯保証人の代理人を兼ねることが許されるかという問題になります。主債務者と保証人の関係では、どちらかが返金すれば、その分相手方が返金を免れるという形になりますので、一方の出捐で他方が得するという関係を見ると、利益相反思想にも思われます。ただ、時効の援用や弁済の抗弁など、双方に共通する主張ができる可能性もあります。
しかし、主債務者と保証人は、求償の場面以外では「相手方」という立場にはなりません。そのため、弁護士職務基本規程28条3号が問題となり「依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件」に該当することになります。
そのため、同条の柱書にある「第三号に掲げる事件についてその依頼者及び他の依頼者のいずれもが同意した場合」には、受任をすることができることになります。
もっとも、途中で利益相反が顕在化した場合には、双方の代理人を辞任することになります。そのため、最初に委任を受ける際には、場合によっては双方辞任になる可能性を十分伝えた上、受任をする必要があります。
【弁護士が解説】相手方との交渉の際、許される言動はどの程度であるか

【事例】
X弁護士は、Aから、自身の配偶者BがCと不貞関係にあるとの相談を受けた。相談の結果、AはCに対して慰謝料請求をするということになったが、その時点でもAとBの間の婚姻関係は破綻しているとはいえなかったほか、BとCの間に不貞行為があるという証拠が具体的にある状況ではなかった。
このような状況で、X弁護士は、Cの1000万円の慰謝料を請求する旨の受任通知を送るとともに、Cの携帯電話に複数回電話をした上で、Cの勤務先にも電話をした。そして、折り返しをしてきたCに対して、1000万円の慰謝料を請求した上で、仮に応じなかった場合にはCの上司に通告する旨を伝えるなどした。
X弁護士の対応に問題はないか。
【解説】
1 弁護士の義務
弁護士である以上、法令や証拠に基づき主張をするべきなのは半ば当然です。もちろん、相談時点では事実関係が明らかではなく、当事者の一方の主張を聞いた結果、(結果的に見れば)一方的な主張となってしまうこともありますが、これはあくまでも結果論であり、やむを得ない面もあります。
ただ、明らかに証拠が不足している状況で、断定するような形で主張をするということは許されません。
今回のX弁護士の例の場合、婚姻関係の破綻がない以上、不貞慰謝料請求をすることになり、不貞の証明をする必要があります。ただ、Aの一方的な主張のみであり、他に根拠がないという状況では、慰謝料請求が認められる可能性はほとんどありません。せめて、婚姻関係が破綻していないのであれば、Bから話を聞き、不貞の事実を確認することは可能であったはずです。にもかかわらず、この段階で不貞慰謝料請求権の存在を前提としてCに交渉していくことは不適切と評価される可能性があります。
2 不安をあおる言動
さて、X弁護士は、Cに対して1000万円の慰謝料請求を行っています。
婚姻関係が破綻したという事例での慰謝料請求であったとしても、この金額が裁判所によって認定されるとは通常考えられません。もちろん、算出方法等によって金額が高めになったり低めになったりすることはあり得ますが、今回の金額はあまりにも高額です。このような高額の請求を受けたCからすれば、相当不安を感じるはずです。
また、X弁護士は何度もCに電話をしています。もちろん交渉のために電話をすることは否定できませんが、あまりにも回数が多いようであれば、着信履歴の状況からしてもCは不安を感じると思われます。
弁護士として相手方と交渉をすることは当然ですし、一方の代理人の立場として交渉をする以上、客観的な事実や、当然予想される帰結(たとえば「裁判になったら、弁護士さんを通常雇うことになり、お金と手間と時間がかかります」など)を告げることには問題がないと思われますが、それ以上のことについては余程の証拠がなければ告げること自体も危険であると言えます。
3 脅迫的言辞
最後に、X弁護士は、Cの勤務先の上司に通告する旨を述べています。Cの行為は当然私生活上の行為であり、Cの仕事とは関係ありません。にもかかわらずこれを職場に告げるというのは、脅迫的な下農であり、弁護士として許されるようなものではありません。
このような脅迫的言辞は、弁護士として当然認められるものではありませんし、悪質なものであると認定されます。もちろん、事実としてそういうことになるということを告げることは問題ありません。たとえば、(今回の事案では問題がありそうですが)「慰謝料の支払いを裁判所に命じられることになり、それを支払わなかった場合には、給与について裁判所から差押えの命令が会社に行き、会社に裁判を起こされたことが分かってしまう」というのはあり得る結末の1つであり、弁護士であれば通常想定する手段だとは思いますが、一般の方からすると脅されているように感じると思われます。このような言動まで脅迫であると認定されることはないと思われますが、それでも表現や言い方などの点には注意を要します。
弁護士同士でも注意が必要ですが、そうでない方を相手に交渉を行う場合、弁護士の世界の常識が当然通用するわけではありません。表現や言葉遣いには十分注意をして交渉を行う必要があります。
【弁護士が解説】依頼者からの要求は何でもするべきか、その危険性について解説

【事例】
X弁護士は、ある夫婦の妻Aから相談を受け、自身の夫であるBが浮気をしているので何かできることはないかと尋ねられた。
Aが持参してきた調査会社の報告書や、LINEの履歴などから見て、確かにBが不貞行為をしていることとはほとんど確実であると考えたXは、Aに対して離婚や慰謝料の請求を行うことができる旨を説明した。
しかし、Aとしてはそのようなことではとても収まりがつかず、Bの生活をめちゃくちゃにしてやりたいという希望があった。そのためAはXに対し、「あいつのことは絶対に許せない。今の生活ができないようにしてやりたいので、Bの実家や職場に先生から不貞慰謝料請求の内容証明郵便を出してもらいたい」と告げた。
Xはこのようなことに応じてよいだろうか。
【解説】
XにとってAは依頼者となりますので、弁護士職務基本規程第22条の「弁護士は、委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務を行うものとする。」という規律が当てはまります。そのため、Aが希望することについては基本的にその意思を尊重すべきであると言えます。
しかし反面、弁護士である以上、「弁護士は、事件の受任及び処理に当たり、自由かつ独立の立場を保持するように努める。」(同20条)、「弁護士は、良心に従い、依頼者の権利及び正当な利益を実現するように努める。」(同21条)、「弁護士は、名誉を重んじ、信用を維持するとともに、廉潔を保持し、常に品位を高めるように努める。」(同7条)などの規程も定められています。そのため、たとえ依頼者の希望であったとしても、何でもそのまま行ってよいということにはなりません。
今回の事例で考えると、不貞行為をしているということは通常人に知られたくないものであることは間違いありません。また、公になっているようなもでもないですので、いわゆる「秘密」に属することは明らかです。このような秘密について、第三者に口外することは当然守秘義務との関係で問題となります。弁護士職務基本規程23条の秘密保持義務は「依頼者について」の秘密と限定しているものの、弁護士法23条の守秘義務にはそのような限定はありません。この弁護士法23条の守秘義務については、依頼者の秘密に限定されるのか第三者のものも含むのか争いがありますが、日弁連では第三者のものも含むと解釈しています。そのため、今回の事例と同様のケースで、相手方勤務先に離婚事件に関する事実をメールで送信したような事案で弁護士法上の守秘義務違反を認めたケースがあります。
不貞行為があった場合、法的権利として認められるのは離婚や慰謝料の請求が基本的なものです。相手方配偶者の生活環境を破壊するということは、正当な利益ということはできないと考えられますので、これを実現することは、守秘義務違反の問題は別としても基本規程21条や7条の問題を生じさせます。ですので、X弁護士としてはAの依頼を断るべきですし、これで信頼関係が破壊されるようであれば委任契約の解約をする事案ということになります。
今回の事例では、Bの連絡先などが確実に分かっていると言えるケースでしたので、勤務先や実家に連絡をすることが問題となるケースでした。ただ、今回の事例とは異なり、Bの連絡先が勤務先や実家以外全く分からないということは十分あり得ます。そのような場合、弁護士から連絡をすることはやむを得ない場合も存在すると思われます。ただ、そのような場合であっても、事件の内容や弁護士の主張を過度に記載するなどした場合にはやはり同様の問題が生じると思われますので、「連絡が欲しい」程度の簡単な記載に留めるべきであろうと思われます。
懲戒委員会の独立性が問題となった事案
1 事案の概要
A弁護士は、B弁護士会に所属する弁護士であるが、B弁護士会ではA弁護士に対して1年間の業務停止とする処分が決定した。
これに対してA弁護士が日弁連に審査請求したところ、日弁連は不服を入れ、処分を戒告に変更した。
ただ、この戒告処分に対してA弁護士が東京高裁に対して取消訴訟を提起した。
取消訴訟の中でA弁護士が主張したのは、B弁護士会懲戒委員会が開かれた際、そこに本件懲戒請求の請求者でもあるB弁護士会会長が出席し、意見を述べるなどしたことが、委員会の公正を疑わせるのではないかという点である。
(東京高判昭和42年8月7日の事案)
2 裁判所の判断
懲戒は弁護士にとつて刑罰にも比すべき重大なことがらであつて、その審理、判断に特に公正が要求されることはいうまでもないところであり、法は、弁護士会が所属弁護士を懲戒するには必ず懲戒委員会の議決に基づくことを要求し(弁護士法五六条二項)、弁護士会長その他の理事者に裁量の余地を与えず、かつ、右懲戒委員会は、その委員に弁護士のほか裁判官、検察官および学識経験者を加えてこれを組織すべきものとし、その弁護士委員も弁護士会の総会の決議に基づくべきものとして(同法六九条、五二条三項)、つとめて理事者の影響から独立した機関としている。こうした法の趣旨にかんがみると、懲戒委員会における具体的事件の審査に、理事者が故なく出席して意見を述べることは、当該審査の公正を疑わしめるものとして、許されないものと解するのが相当であり、その点において、B弁護士会の懲戒委員会が本件事案についてした審査手続にはかしがあるものといわねばならない。
しかし、その点については、原告の異議申立に基づき、被告の懲戒委員会においてさらに事案の実体につき適法公正な審査を遂げ、その議決に基づき、被告はB弁護士会のした業務停止一年の懲戒処分を重きに失するものとして取消し、懲戒として最も軽い戒告処分に変更しているのであるから、ほかに特段の事由がない限り、B弁護士会の懲戒委員会における右審査手続のかしは、これをもつて被告のした本件懲戒処分を取消すべき事由とするに足りないものと解する。
3 解説
懲戒委員会は、弁護士の身分を剥奪する可能性のある重要な委員会であるため、この委員会は弁護士会と独立している必要があると考えられました。
そのため、弁護士会の会長が懲戒委員会に出席して発言した場合、委員の意見が会長の意見に引っ張られる可能性も否定できず、このようなことを行うことは、懲戒委員会の独立性を害することと考えられました。
実際、法律上は明文の規定はありませんが、弁護士会の役員、常議員が、懲戒委員会の委員を兼任することは不適切である旨の日弁連の通知等が存在し、これに基づいて委員は選任されるようになっています。
除斥期間の始期が問題となった事例
1 事案の概要
X弁護士は、事件当時A法律事務所に所属しており、同事務所の代表はB弁護士であった。
ある年、Xは、A法律事務所B弁護士名義で、Cらから多数の土地の明け渡し、売却等の手続の委任を受け、報酬は土地の売却価格の3~5%ほどと決定された。
X弁護士は、問題となった土地を約4億円で売却し、その報酬として1300万円を受領した。
この金額が不当に高額ではないかということで懲戒請求がなされ(なお、本請求にはほかに書類のみ返却という問題も含まれている)、単位会では不当に高額であるとのことで懲戒事由に該当するとの判断を受けた。
この結果、X弁護士には戒告の処分がなされたため、Xはこの取消訴訟を提起した。
この報酬に関する問題として、X弁護士は除斥期間の主張を行った。実際、報酬を受領した日から、懲戒請求がなされた日まで5年ほどが経過していた。
(東京高判平成15年3月26日の事例 なお、旧報酬規程があった頃の事案である)
2 判旨
弁護士法六四条は、「懲戒の事由があったときから三年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない。」と規定しているところ、Xは、処分理由〔1〕(注 弁護士報酬が不当に高額であるという主張)に係る同条の「懲戒の事由があったとき」とは、XがCから最終的に報酬を受け取った平成七年二月二八日であると主張し、他方、被告(日弁連)は、これを適正な報酬を超える金額を返還した時点か、委任契約が終了した時点のいずれかであるとした上、本件ではXないしCの受任事務が終了した平成九年一一月二七日であると主張するので、まず、この点について検討する。
弁護士法六四条にいう「懲戒の事由」は、同法五六条に規定する同法あるいは弁護士会の会則違反行為、所属弁護士会の秩序又は信用を害する行為、品位を失うべき非行を意味するものである。処分理由〔1〕は、不当に高額の報酬を受け取ったことを懲戒の事由とするものであるから、その不当性が報酬を受け取った以後の事務処理をみなければ判断できないような事情、あるいは報酬契約が公序良俗に反するほどの暴利行為で、受領した報酬を返還しないこと自体も弁護士としての品位を失うべき非行であると評価される等の特段の事情のない限り、処分理由〔1〕に係る「懲戒の事由があったとき」とは、現に報酬を受け取ったときと解するのが相当である。
3 解説
この判決は、継続的に見える非行事由に関し、不当に高額な報酬の受領という点については原則報酬受領時に非行が終了し、除斥期間の始期は報酬を受領したときが原則であると判断したものになります。
この一般的な判旨の後、裁判所は「特段の事情」が存在しないことを認定し、この不当な報酬の点については懲戒手続が開始できなかったということを認めました。
ただし、他の事由が懲戒に値することを理由に、Xの請求自体は棄却しています。
利益相反が問題となった事例③
1 事案
X弁護士は元裁判官であったが、裁判官時代にある刑事事件の再審請求審の判断に関与をしていた。
その後Xは裁判官を辞職して弁護士となり、刑事事件の方は再審無罪が確定した。
この刑事事件において、捜査官に違法な取調べがあったとする国家賠償訴訟について、Xが原告(元被告人)の代理人となることについて、弁護士法第25条4号に違反しないかが問題となった。
(高松高判昭和48年12月25日の事案)
2 判旨
弁護士法二五条四号が、弁護士が公務員として在職中取扱った事件を退職後に弁護士として取扱うことを禁止しているのは、弁護士の職務の公正を担保し、弁護士に対する一般の信頼を確保するにあることは云うまでもないところ、右の立法目的から考えると、公務員として在職中に取扱った事件(以下単に前件と云う)と退職後に弁護士として取扱う事件(以下単に後件と云う)とが、形式的に同一である場合でも、右在職中の職務の内容等から考え事件の実質に関与していなかった如き場合には、未だ右法条に該当しないと云うべきである反面、前件と後件とが、その件名を異にし或いは刑事々件と民事々件と云うが如く形式的には同一性がないとみられる場合でも、両事件が共に同一の社会的事実の存否を問題とする如き場合に於ては、後件につき、なお弁護士としてこれを取扱うことを禁止されているものと解するのが相当である。
本件についてみるに、前記再審請求の理由とするところは前認定の通り捜査官による、不法、不当な逮捕、勾留とこの間の誘導、強制、拷問に基づく自白及び右自白を裏付ける為に捜査官によって偽造された証拠書類、証拠物によって原告が犯人に仕立て上げられたことを主張するものであって、捜査官の違法行為を主たる理由とするものであるところ、本訴の請求の趣旨及び原因も、要するに、右●●事件の捜査に当り、捜査官である検事及び警察官らが、原告を不法に長期間●●の留置場に拘禁し、拷問を加えて原告に虚偽の自白を強要し、右自白を裏付ける為手記五通を偽造し、証拠物たる国防色ズボンもすり替えて公判廷に提出する等の不法行為があったとし、これに基因して無実の原告が死刑と云う極刑判決を受けたことによる慰藉料を請求すると云うものであって、前者は刑事判決に対する再審であり後者は民事々件と云う意味では形式的には同一性がないとみられるけれども、共に捜査官の同一違法行為の存否を問題とする点で、実質的には同一事件と云うを妨げないものである。そしてX弁護士は右再審事件について実質的な審理をなしていること前認定の通りであるから、同弁護士による本訴の提起は、弁護士法二五条四号に該当するものと云わねばならない。
而して右法条四号に違反する訴の提起に対し、相手方より異議が述べられた場合は、右訴提起行為が無効となることは既に最高裁判所の判例の存するところであるから(最判昭和四二年三月二三日、同昭和四四年二月一三日)本訴は不適法な訴として却下すべきものである。
3 解説
本件については、元々の事件は再審請求審、新しい事件は国家賠償訴訟という、刑事・民事というレベルで異なる事件ではありました。
しかし、争点が同一であることなどから、社会的に同じ事実を対象とする事件であるということで、結果的に弁護士法第25条4号に該当し、職務を行い得ない事件であるということになりました。
利益相反が問題となった事例②
1 事例
X弁護士は、Aの依頼を受け、昭和31年3月23日にBを相手として土地の所有権確認訴訟を提起した。
この訴訟は昭和35年5月12日に終了するが、その終了前にX弁護士はBの訴訟代理人としてCを相手とする建物収去土地明渡請求訴訟を提起した。
問題は、X弁護士の行為が利益相反行為に該当するとして、そのBC間の訴訟での訴訟行為が無効となるかという点である。
(最判昭和41年9月8日の事例)
2 判旨
「右事実関係のもとにおいては、Bの訴訟代理人であるX弁護士らの訴訟行為は、弁護士法二五条一、二号に違反するものではなく、同条三号に違反するものというべきである。ところで、本件のように、受任している事件の相手方からの依頼による他の事件の相手方が、受任している事件の依頼者と異なる場合には、当該弁護士らの「他の事件」における訴訟行為は、「受任している事件」の依頼者の同意の有無にかかわりなく、これを有効と解するのが相当である。けだし、当該弁護士らの同条三号違反の職務行為により不利益を蒙むる虞れのある者は「受任している事件」の依頼者であつて「他の事件」の相手方ではなく、同条三号は、もつぱら、「受任している事件」の依頼者の利益の保護を目的とするものと解すべきだからである。
したがつてBの訴訟代理人であるX弁護士らの訴訟行為は、別件の依頼者であるA、またはその相続人の同意の有無を問わず、これを有効と解すべきであり、その他、右訴訟行為を無効とすべき根拠はないから、これを有効とした原審の判断は、結論において正当である。
3 解説
本判決は、結論としてBC間の訴訟におけるX弁護士の訴訟行為を有効と判断しました。
理由は本文中に記載のある通りで、あくまでも弁護士法第25条第3号の規定は元の依頼者であるAを保護する規定であるので、BCとの関係では訴訟行為を無効とする理由がないからです。
ですのでX弁護士の訴訟行為自体の効力に影響は出ないところですが、判決が認定する通り弁護士法25条第3号の規定に当てはまっていますから、きっちりと同意を取るか、もしくは受任をしないという判断を行わない限りは弁護士法上の懲戒処分を受ける可能性が十分にあります。
業務停止中の行為が問題となった事例
1 事案の概要
元々の事案は、信用組合が個人に対し、約束手形に基づいて金銭の請求をした事件でした。
第1審は原告(信用組合)の勝訴、控訴審は第1審被告(個人)の勝訴でした。
この控訴審までは、弁護士の資格について特に争われた形跡はありません(手形の振り出しなどが問題となっていました)。
この控訴審判決について、第1審原告(信用組合)が上告しました。
ところで、この事件の第1審判決期日は昭和38年11月7日、控訴審判決期日は昭和40年2月16日で、その間に控訴審の訴訟手続きが行われています。
第1審被告の控訴審での代理人弁護士は、昭和39年3月18日に弁護士会で業務停止3月の懲戒処分を受けているところでしたが、昭和39年4月15日、控訴審における口頭弁論期日が開かれていました。
この口頭弁論期日での訴訟行為につき、上告人(信用組合)代理人弁護士が、無効な弁論であると主張して絶対的上告理由がある旨を主張しました。
(最判昭和42年9月27日の事例)
2 判旨
「裁判所が右の事実〔注:業務停止の事実〕を知らず、訴訟代理人としての資格に欠けるところがないと誤認したために、右弁護士を訴訟手続から排除することなく、その違法な訴訟行為を看過した場合において、当該訴訟行為の効力が右の瑕疵によつてどのような影響を受けるかは自ら別個の問題であつて、当裁判所は、右の瑕疵は、当該訴訟行為を直ちに無効ならしめるものではないと解する。いうまでもなく、業務停止の懲戒を受けた弁護士が、その処分を無視し、訴訟代理人として、あえて法廷活動をするがごときは、弁護士倫理にもとり、弁護士会の秩序をみだるものではあるが、これについては、所属弁護士会または日弁連による自主・自律的な適切な処置がとられるべきであり、これを理由として、その訴訟行為の効力を否定し、これを無効とすべきではない。けだし、弁護士に対する業務停止という懲戒処分は、弁護士としての身分または資格そのものまで剥奪するものではなく、したがつて、その訴訟行為を、直ちに非弁護士の訴訟行為たらしめるわけではないのみならず、このような場合には、訴訟関係者の利害についてはもちろん、さらに進んで、広く訴訟経済・裁判の安定という公共的な見地からの配慮を欠くことができないからである。」「本件を検討するに、一件記録によれば、弁護士Aが原審において被上告人の訴訟代理人として引き続き訴訟行為をしたこと、しかも裁判所が同人の訴訟関与を禁止した事実のないことがうかがわれるのであつて、同人に対し、所論のような懲戒がされ、しかもその処分が前示のようにすでにその効力を生じていたとしても、以上述べた理由により、同人が原審でした訴訟行為が無効となるものではない」
3 解説
本判決は、訴訟経済等の理由から、業務停止中の弁護士の訴訟行為を有効と取り扱いました。
なお、本判決中でも指摘されていますが、訴訟行為が有効であるからといって、その行為に何らの問題もないというわけではなく、この行為自体も再び懲戒の事由となります。
ですので、業務停止を受けた弁護士としては、速やかに辞任等の措置をとる必要があります。
品位を失うべき非行の事例
1 事例
A弁護士は、ゴルフのプレー後、飲酒をした上で車で帰宅した。
その帰宅途中、警察の検問があり、酒気帯び運転の基準値を上回るアルコールが検出されたため、
酒気帯び運転の罪で現行犯逮捕された後、罰金を支払った。
(複数の事例を混ぜたもの)
2 解説
今回問題となっている行為は、ゴルフのプレー後の出来事であるため、私生活上の行為であると言えます。
しかし、弁護士法に定める懲戒事由は「その職務の内外を問わず」品位を失う行為とされていますので、弁護士としての職務上の行為に留まらず、私生活上の行為であっても懲戒の対象とされています。
今回のような飲酒運転は、道路交通法に違反する犯罪行為ですから、弁護士として犯罪を行うことは、通常の人以上にその責任が大きいといえると思われます。特に、飲酒運転については昨今の社会情勢上絶対に許されないものとなっており、その様な面でも重い処分が下されやすい事例となっています。
そのため、飲酒運転のような略式罰金で終了するような事件であっても、戒告に留まらず業務停止の処分を受けることが通常であろうと思われます。
単なる飲酒運転だけであれば短期間の業務停止で留まりますが、これに加えて事故が発生しているような場合や、救護義務違反を犯しているような場合には、さらに業務停止期間が長くなります。