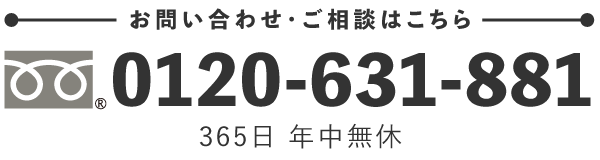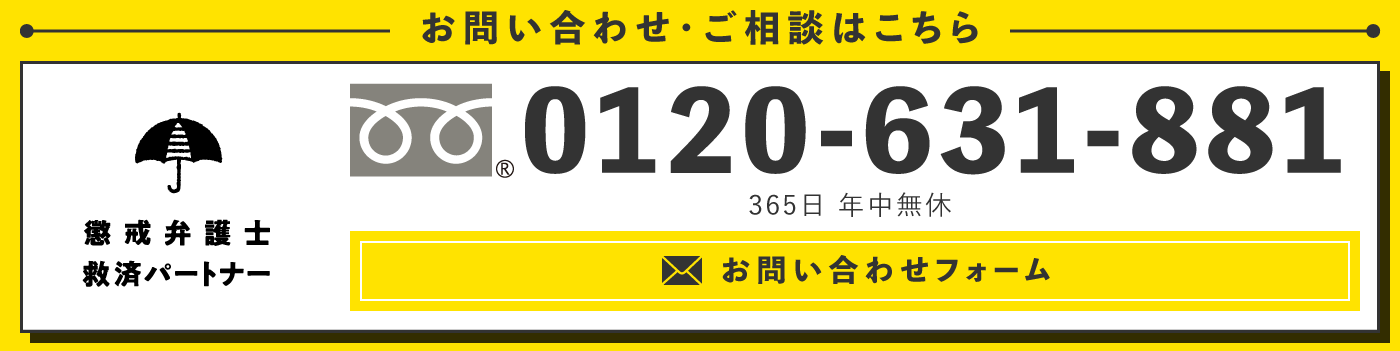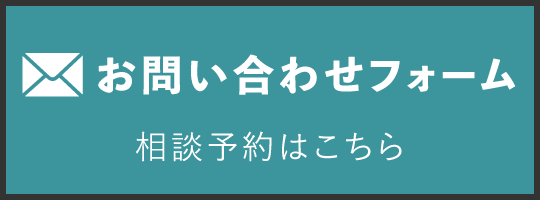Archive for the ‘過去の懲戒事例’ Category
守秘義務違反が問題となった事例⑵
1 事例
X弁護士は、横領事件で被疑者であるYの弁護人として選任された。
このYには、同種事件の余罪があり、その件についても既に捜査が開始されていた。
捜査機関はYの親族に対し、余罪についての証拠となるようなものの任意提出を求め、提出しない場合には強制捜査を行う旨を告げたが、Yの親族はこれを提出しなかった。
証拠物の扱いに困ったYの親族は、Xに相談を行い、Xは証拠物を自らのところに送るよう指示した。
そして、Xはこの証拠物を、Yの承諾なく捜査機関に提出した。
(日弁連綱紀委員会平成24年8月28日議決事案を改変したもの。実際には証拠物提出の承諾の有無に争いがあり、原弁護士会は事前の同意があったことが推認されるとしていた。)
2 判断
(1)原弁護士会
Yからの懲戒請求に対し、単位会は以下の通り判断しました。
「(中略)一方弁護人としては全方位に目配りしながら弁護活動に当たらねばならない。
弁護人であっても、刑事訴訟法の基本理念でもある真実発見に目をつぶる事は許されない。
更に、被疑者と関係を有する者についても、弁護人の認知する限り法令違背なきよう配慮しなければならない。ところで、本件業務上横領事件〔事例でいう余罪事件のこと〕については、前記の通り既に捜査が開始されていたこと、警察は本件証拠物の所在を認知し提出を求めていたこと等を考慮すると、弁護人といえどもこのような事実を認識しながら証拠物を保持したままこれを捜査機関に提出しないことは証拠隠滅罪にも問われかねない事態になること、本件証拠物を受領した弁護人としても真実発見という基本理念に目をつぶるべきではないこと、証拠物の提出は請求人の情状にも資することなどを総合的に考慮すれば(中略)弁護士としての判断で任意提出していたとしても、そのことで弁護士法の言う品位を失うべき非行には該当しないというべきである。」
(2)日弁連綱紀委員会の判断
原弁護士会の判断に対して、Yが異議申出を行い、事案は日弁連綱紀委員会に係属しましたが、綱紀委員会は以下の理由で、原弁護士会懲戒委員会に事案の審査を認めることを相当としました。
「刑事弁護人たるXは、「積極的真実義務」を課せられているものではないのであるから、仮に、自身の依頼者であるYの余罪の証拠である本件証拠物の所在を覚知したとしても、その事実を捜査機関に通報する義務はないし、ましてやその証拠物を自身に送付させ入手したうえで捜査機関に任意提出しなければならない義務のないことは明らかである。Xが、積極的に本件証拠物を入手して、Yの同意を得ないで、これを捜査機関に提出した行為は、明らかにXの正当な防御権を侵害する行為であり、刑事弁護人に求められる、被疑者及び被告人の権利及び利益を擁護するため最善の弁護活動に努める、という基本的誠実義務に著しく反する行為と言わざるを得ない。」
3 解説
弁護人が守秘義務を負い、捜査機関に対して証拠物を提出する義務がないことは明らかなところです。
ただ、依頼者(被疑者)が余罪を認めているような場合には、早めに進んで証拠を提出し、追加の身体拘束を回避したり、公判出の情状を良くするということは、弁護活動として考えられないも野であるとは言えません。
そのため、この証拠を提出すべきかどうかという点が問題となるところですが、いずれにせよ依頼者の同意を明確にする必要があります。
仮に依頼者に有利である面があるとしても、前述の通り守秘義務を負っていますから、勝手に提出することは許されないと考えるべきでしょう。
守秘義務違反が問題となった事例⑴
1 事案
Xは、自身の問題についてA弁護士とB弁護士に依頼をしていたが、Xと両弁護士との間で、事件に対する解決方針等で温度差があった。
ところで、Y弁護士が開設する「○○被害サイト」というサイトには、Xが抱えている問題についての情報提供を呼びかける文言や、「秘密を守ります」との文言と共に、メールフォームが設置され、被害の情報に提供を呼びかける文言があった。
そこでXは、メールフォームにAB弁護士の実名を挙げ、自身の被害の内容や、弁護士の対応状況等を記載したほか、「和解するしかないのでしょうか」「誰も引き受けなければ私法では解決できないでしょうか」との内容を記載した。
Y弁護士は、メール内にあるA弁護士の名前が旧知の弁護士であったことから、A弁護士に電話をし、メールを送ってきた人物が実際の依頼者であるかどうかや、メールに対する返信をどうするべきか相談したところ、A弁護士から自身で対応する旨告げられたので、そのままメールに対して返信を行わなかった。
Y弁護士がA弁護士に電話をし、メールの内容などを伝えたことが守秘義務違反となるかが争点である。
(大阪高判平成19年2月28日の事案を改変したもの)
2 判旨
「弁護士法23条は,弁護士はその職務上知り得た秘密を保持する権利を有し,義務を負うと規定し,弁護士倫理20条(現行弁護士職務規程23条)にも正当な理由がないのに職務上の秘密を漏らすことを禁じる旨の規定がある。上記の規定にいう「職務上知り得た」とは,弁護士がその職務を行うについて知り得たという意味であり,弁護士が弁護士法3条の依頼者から依頼を受け,訴訟事件等その他一般的法律事務を処理する上で知り得た事項についての守秘義務が課せられ,また,将来依頼を受ける予定で知り得た事項にも及ぶが,他方,そのような弁護士としての一般的法律事務を行うものではない,例えば,弁護士会の会務を行う際に知り得た事実については弁護士としての守秘義務は及ばないと解される。
上記認定のとおり,Xは,サイトの共同主催者であるYに対し,いきなり本件メールを送信したものであって,サイトは,○○被害を取り扱い,○○被害の情報を得ようとしていたことは,ホームページに明示されており,サイトの活動に関係して,サイトの○○問題の情報提供の範疇に入らない内容が記載された本件メールが突然Yに送られたに過ぎない。
確かに,Yは弁護士の資格を有するものであることを明らかにしてサイトを共同主催するものであるが,これは,サイトの信頼を高めるためのものであって,一般的な法律事件について事務を処理しようとする意思が表示されたものであるとは認めることはできないし,Yにそのような意思があったことを認めることはできない。したがって,Yの受けた本件メールは,サイトの活動に関して一方的に送信されたものであって,Yが弁護士として職務を行う上で知り得た事項とはいえないものである。
そして,上記認定の事実によると,XがYに一方的に送信した本件メールの内容もYに対し,積極的な解決や相談を持ちかけた内容ではなく,Xが本件○○問題に遭遇した具体的経過,依頼した弁護士との意見の相違があり悩んでいるなどの単なる心情を吐露したものに過ぎないものであって,上記のとおり,積極的に何らかの法律上の意見や判断を求めているものではないから,これを直ちに法律相談であると認めることはできない。」
「仮に,本件メールがXから弁護士であるYに対してなされた法律相談であり,弁護士が職務上知り得た事項であるとしても,以下の説示のとおり,Yの行為は,弁護士としての守秘義務に違反する違法な行為などということはできない。すなわち,Xも全く面識のない弁護士にそのような内容の本件メールを送信すれば,弁護士であるYにおいて,本件メールがいたずらではないかとの疑問を抱くのは当然であり,Xが実在の人物であるか,書かれた内容が事実であるか,本件○○問題の相手方の主張や証拠及び紛争処理に関する態度が不明であることに加え,Xの回答がいかなる使われ方をするのかなどYの意図などについて懸念を抱き,必要な範囲で裏付けの調査をする必要が生じてくることは容易に推測できる。そうすると,仮に,Xにおいても,Yが本件メールが単なる心情吐露したメールではなく,Yが弁護士であることに着眼した法律相談であるとの認識であれば,Yが本件メールの内容について,Xのプライバシー権などに配慮した上で,何らかの手段で裏付け調査した上で,回答することを予測し得たものと認めることができる。上記認定の事実によると,Yは,受任弁護士であるA弁護士が信頼できる弁護士であると判断した上で,Xの実在を確かめる趣旨で電話を架け,A弁護士の返事から少なくともXの実在を確認でき,Yが本件メールの相談について回答する必要のないものであると判断したにすぎないのである。
したがって,本件メールがYと全く面識のないXによる突然の一方的なメールの送信である以上,その際,Yが受任弁護士にXから本件メールがあったことを告げ,Xが実在の人物であるかどうかを確かめることは,正当な弁護士活動であるといえ,これに加え,尋ねた相手も弁護士であって,互いに守秘義務を負う者であって,それ以上第三者に伝播されるものではないことを考慮すると,少なくとも弁護士としての正当な行為であるといえ,Yに課せられた守秘義務に違反するものではない。」
「ところで,秘密とは,世間一般に知られていない事実で,本人が特に秘匿しておきたいと考える性質を持つ事項(主観的意味の秘密)に限られず,一般人の立場から見て秘匿しておきたいと考える性質を持つ事項(客観的意味の秘密)を意味すると解される。上記認定の事実によると,本件メールには,Xが○○被害を受けたことや受任弁護士の対応に関するXの不満などの心情を伝えたうえ,Xが不満足と考える内容の和解で解決するほかないのか,司法の場で解決することはできないのかと述べるものであって,詳細な事実関係の記載に加え,受任弁護士が取った助言等についての不満や悩みを訴えるものであって,それ自体は一応上記の秘密に該当すると認められる。
しかし,上記認定の事実によると,Xは,本件メールの内容については,集会などにおいて,同様の内容を述べ,他の弁護士にも同様の内容を相談したことがあるのであるから,本件メールの内容が秘密性を有するとしても,X自ら秘匿性を開放し,明らかにしているといえ,サイトのホームページに送信フォームを用いて本件メールをYに送信したことを考慮しても,Xが本件メールの内容を秘匿しておきたいと考えていたとみることは困難である。
そして,本件では,XがYに本件メールを送信したこと自体が秘密にあたるかということが問題となるが,XがB弁護士,A弁護士に事件処理を委任しているときに,Xが受任弁護士との関係悪化を懸念することがあり得ることは当然であるとしても,他方,突然本件メールを送信されたYとしては,少なくとも送信者が実在するのかについて確かめる必要があり,その相手方がXの受任弁護士である場合には,XからYに対し,突然本件メールがあったことを伝えなければ,受任弁護士からXの実在の有無についての回答を得られないことになりかねないのであるから,その限度では,XからYに本件メールがあったことを告げる行為は,上記のとおり,Yの正当な理由によって守秘義務を免れる行為といえ,弁護士が守秘義務に違反するとはいえないと解すべきである。
3 解説
守秘義務の対象となる「秘密」の意義を明らかにした裁判例です。
守秘義務の対象となる秘密には、一般人が知らない事項のうち、①本人が秘密にしておきたいと
考える事項だけでなく②一般人であれば秘密にしたいと考えるような性質の事項も含まれると考えらえます。
例えば、「弁護士に依頼している」という事実は、本人が秘密にしておきたいかどうかは別としても、一般人であれば紛争の当事者になっているということが知られてしまうことになりますから、秘匿しておきたいと考える事項であろうと思われます。
ただ、本件では受任をしている弁護士当人に対して確認がなされたこと(第三者へ広がっていない)や、法律事務所ではない一般のメールフォームという形式などの点を踏まえ、守秘義務違反を否定しています
弁護士法第20条違反の事例⑶
事例
①
Ⅹ弁護士はY県において「P法律事務所」を開設していたが、別の特許事務所に勤務していた友人のZ(弁護士、弁理士資格を持たない)がその職を辞めざるを得なくなったことから、自身で特許業務を行うことを考え、Zを事務として雇用することを考えた。
そこで、既存のP法律事務所とは別の場所(同じY県内)に事務所を借り、事務所名を「P法律特許事務所」と変更する届出を弁護士会に出したうえで、新しく借りた事務所を「P法律特許事務所特許部」と案内した。
Y県弁護士会会長がXに対して複数事務所の禁止に抵触する可能性を告げたところ、Xは新しい事務所をZの調査事務所と変更することにしたが、実際は約5か月間事務所を閉鎖しなかった。
②
A弁護士は本来B県に法律事務所を開設していたが、C県にいるDから依頼をされ、C県のビル1室を借り、そこに「A法律事務所C連絡所」の名称を付したうえ、そこで1か月に3回程度法律相談を受けるなどした。
また、その際Dに対し、「A法律事務所事務員」の名刺を使用させた。
(いずれも自由と正義掲載の事案を改変したものである)。
判断
①については戒告、②については業務停止2か月の処分がなされた。
解説
いずれの事案も、複数事務所を開設することを禁ずる弁護士法第20条3項に抵触します。
複数事務所の禁止は、所属する単位会の管轄外の場所に事務所を開設することが許されないだけではなく、仮に同一単位会管轄内であっても禁止されます。
複数事務所の開設が禁止されている趣旨は、1つには弁護士が所属する単位会の監督権を十分に発揮させるためですが、それだけに尽きるものではなく、弁護士のいない事務所が開設され、非弁行為が横行することのないようにするためというものも含まれます。
そのような意味で、①の事案が戒告であるにもかかわらず、②の事案が業務停止となったのは、②の事案ではDがC県で弁護士の代理のような活動をして、非弁行為と思われるようなものが含まれていたことがされた重視されたものと思われます。
弁護士法第20条違反の事例⑵
1 事案
X弁護士はある理由により一度弁護士登録を取り消していたところ、再出発のためにA弁護士会に再登録をした。
しかし、再登録する際に法律事務所として届け出たB弁護士の事務所は事実上閉鎖中であったため、
X弁護士は再開まで待機をしていた。ただ、そうこうしているうちにX弁護士の家庭の事情により全く別の地方に引っ越す必要が生じてしまったため、C弁護士管内に自宅を転居したうえで、C県において弁護士業務を行うようになった。
このような状況生じて比較的すぐの段階でX弁護士がC弁護士会に登録換えをしようとしたのであるが、C弁護士会は登録換えを認めない決定をした。
そのため、もとのA弁護士会登録のまましばらく弁護士業務を続けていたのだが、X弁護士は再びC弁護士会に登録換えの請求を行ったところ、再び登録換えが認められなかったのでX弁護士が取消訴訟を提起した。
(東京高判決昭和50年1月30日を一部改変した事例)
2 判旨
X弁護士の行為は「法律事務所を設置すべき場所を地域的に制限し、かつ二重事務所の設置を禁止した弁護士法第二〇条の規定に違反したものであることは否定できないところである。しかし、右禁止規定の実質的な理由は、弁護士が二箇以上の法律事務所を設置して法律事務の執務を行えば、責任の所在が不明確となり、ひいては非弁護士と提携する弊害を招く虞があることに存するものと解されるところ、前記認定の事実によれば、原告はA弁護士会に入会後届出をした法律事務所においては全然執務できなかつたのであり、原告がC近辺に転居したのもやむを得ない生活事情によるものと考えられ、しかも、C近辺で法律事務の執務に当るようになつてから間もなく、C弁護士会に登録換の請求をしているのであるから、たとえ原告の行為が形式的に弁護士法第二〇条の規定に違反するとしても、その実質的な違法性は軽微というべきである。第一回目の登録換の請求が拒絶された以上は、A県の届出事務所において執務すべきであるとの被告の見解にも一理あることは否定できないが、右見解は原告に対し再度Aに転居することを要求するに等しいものであり、原告の生活事情に照らし酷に過ぎるものというべきである。従つて右事由をもつて原告の本件登録換の請求を認容することが弁護士会の秩序若しくは信用を害する虞があるとする被告の主張は採用できない。
3 説明
弁護士法第20条3項では二重事務所を禁止しています。
ここで問題となる「事務所」は、弁護士が法律事務を取り扱う施設を指しており、かつこの
事務所は所属弁護士会の管轄内に設置することが求められるほか、弁護士会に事務所として
届け出なければなりません。
もちろん、弁護士は事務所外で執務を行うこともありますし、これが禁止されるわけではありません。特に弁護士の自宅の場合は、自宅で執務をする弁護士も多数いると思われます。
しかし、専ら自宅で執務を行い、本来の法律事務所にほとんどいないという場合には、二重事務所の禁止に抵触すると思われます。
今回の事例では、弁護士の側にも理由があり、やむを得ないと認められる点があったことから、自宅での執務が続いていたことを理由とした弁護士会の秩序や信用を害するおそれがあるという主張は認められませんでした。
弁護士法第20条違反の事例⑴
事例
X弁護士は、Y弁護士会に登録をしていた弁護士であったが、Y県内には居住せず、Z県内にある自宅で弁護士の業務を営んでいた。
Y弁護士会は、X弁護士に対して業務停止6月の懲戒処分を科したが、X弁護士は日弁連に異議申立を行った。
しかしこの異議申立も棄却されたため、X弁護士は東京高等裁判所に対して処分取り消しを求める訴訟を提起した。
(東京高判昭和32年2月12日の事例を一部改変した)
1 弁護士法第20条違反
X弁護士の行為の中で問題となっている行為は、弁護士法第20条2項です。
弁護士法第20条2項は、「法律事務所は、その弁護士の所属弁護士会の地域内に設けなければならない」としており、単位会の管轄地域内に法律事務所を設けることが求められています。
ここで設置が求められている「法律事務所」とは、そのような名称を付された事務所という意味ではなく、当該弁護士が主として執務を行う場所です。
X弁護士やY弁護士会に登録をしていますから、Y県内で執務を行うことが求められます。しかし、実際にはZ県内にある自宅内で執務を行っていたということであれば、弁護士法第20条2項に違反する行為ということになります。
2 裁量権の濫用があったかどうか
X弁護士は、弁護士会からの聴聞や高等裁判所での主張において、以下のような主張をしたようです。
Z県内の自宅は、第二次世界大戦による戦災による居宅の消失等が原因で、あくまでも一時的に親族から借りていたものであった。
そして、その一時的な住居に居住している際、近隣の人々から法律相談を受けるようになったため、そこを拠点に訴訟の対応などをしていただけである。
戦前Y件に事務所を設け、事務員を置いていたが、戦時中の困難から事務員からの連絡も途絶えるようになり(その連絡が途絶している間に事務員の方は亡くなられていたようです)、これらの事情が分からないままZ県内の自宅で執務を行っていた。
弁護士法に定める懲戒事由は、「この法律〔弁護士法〕・・・・に違反し」たときに懲戒する旨を定めています。
しかし、現在の実務上の取り扱いでは、単に法律・会則違反であるからという理由でただちに懲戒をするのではなく、実質的に懲戒をするに値するほどの非行があるかどうかという点を審査し、懲戒処分を行っているとされています。
そのため、仮に弁護士法違反の事由があったからといって、必ず懲戒を受けるとも限りません。その意味では、法律違反の点が認められるとしても、なお弁護士会が裁量権を逸脱したと主張する余地はあります。
しかし、この事例では、X弁護士が主張するような事由があったとしても、Y弁護士会側はX弁護士に対して「再度反省を促し、進んで義務を履行するよう十分な期間を提供して来たにも拘らず、原告〔X〕は口に善処を約しながら、何ら理由なくこれを実行しなかった」という事情があるようですから、裁判所も裁量権の逸脱・濫用はなかったと判断しています。
Newer Entries »