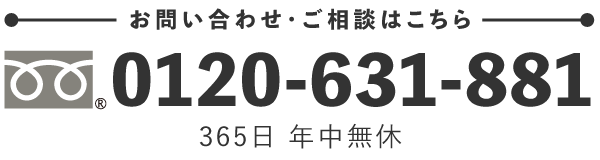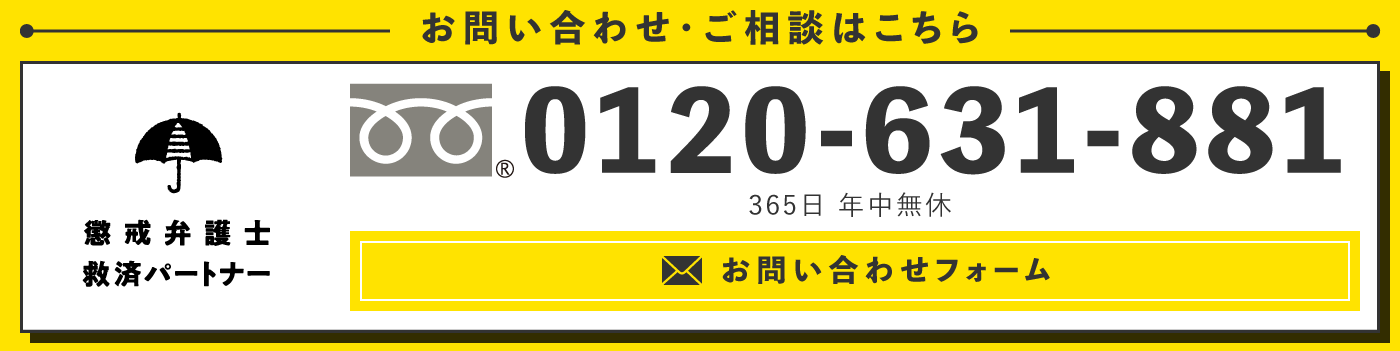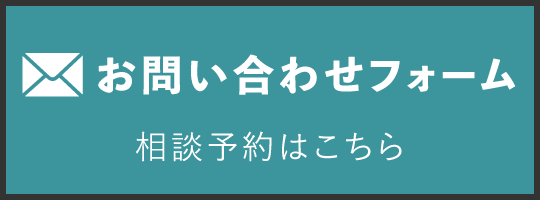Archive for the ‘懲戒手続’ Category
【弁護士が解説】職務上請求を違法に取得した場合にはどのような処分が予想されるか

【事例】
X弁護士は、なじみの不動産会社から、Yが所有する不動産について、近々再開発の計画があり値上がりする可能性があること、
Y自身についても末期のがんで入院中であり、余命がそう長くないということを聞かされた。
そのため、X弁護士は、不動産会社から依頼されたわけでも、Yから依頼されたわけでもないにも関わらず、Yが住む役所に対して住民票及び戸籍謄本の職務上請求を行った。
その際、目的欄に「相続人確定のための調停申し立てのため」と虚偽の内容を記載した。
【解説】
弁護士を含めた一部の士業には、戸籍や住民票といった個人情報を役所に請求し、取得することが認められています。ただ、これは無制限に認められているわけではなく、あくまでも戸籍法の範疇で認められているにすぎません。
戸籍法で弁護士が戸籍を取得することができるとされているのは、戸籍法10条の2によります。
第十条の二 前条第一項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。
③ 第一項の規定にかかわらず、弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。次項において同じ。)、司法書士(司法書士法人を含む。次項において同じ。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。次項において同じ。)、税理士(税理士法人を含む。次項において同じ。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。次項において同じ。)、弁理士(弁理士法人を含む。次項において同じ。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該業務の種類、当該事件又は事務の依頼者の氏名又は名称及び当該依頼者についての第一項各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。
④ 第一項及び前項の規定にかかわらず、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士又は弁理士は、受任している事件について次に掲げる業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該事件の種類、その業務として代理し又は代理しようとする手続及び戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。
一 弁護士にあつては、裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務(弁護士法人については弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十条の六第一項各号に規定する代理業務を除き、弁護士・外国法事務弁護士共同法人については外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第八十条第一項において準用する弁護士法第三十条の六第一項各号に規定する代理業務を除く。)
⑤ 第一項及び第三項の規定にかかわらず、弁護士は、刑事に関する事件における弁護人としての業務、少年の保護事件若しくは心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第三条に規定する処遇事件における付添人としての業務、逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐人としての業務、人身保護法(昭和二十三年法律第百九十九号)第十四条第二項の規定により裁判所が選任した代理人としての業務、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第十三条第二項及び第三項の規定により裁判長が選任した訴訟代理人としての業務又は民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三十五条第一項に規定する特別代理人としての業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、弁護士の資格、これらの業務の別及び戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。
いずれの場合であっても、弁護士であるからという理由だけで請求が認められているわけではありません。少なくとも受任している事件に関しての請求でなければなりませんし、利用目的を記載しなければなりません。同じような規定は住民基本台帳法12条の3にも存在します。
そのため、たとえ弁護士であったとしても、無制限に戸籍等の請求をしてよいわけではありません。今回のX弁護士の行為は、①誰から受任をした事件でもない点②虚偽の目的を利用目的欄に記載した点に問題があり、本来であれば住民基本台帳法、戸籍法上の取得が認められないような場合であったと言えます。
このような職務上請求の目的外使用は、法を犯すものですから厳しく処分される可能性があります。
今回の事例ではそこまでの記載がありませんが、違法に取得された住民票が第三者に交付されたり、これによって記載されている者らに何らかの損害が発生したような場合には、一層重い処分が予想されます。
単なる目的外取得だけであれば戒告で済む可能性もありますが、別の問題が生じているような場合には業務停止の可能性があります。
今回のような事例の場合、取得されたYらに対して謝罪をするほか、取得するに至った経緯(受任間近であったなど)の事情を説明して、処分の軽減を求めることが考えられます。
【最後に】
弁護士が懲戒請求を受けた場合、弁護士は代理人ではなく紛争の当事者となります。代理人として紛争にあたるのはいつもどおり出来たとしても、当事者として紛争にあたる場合には思った通りの活動が出来ないということはあり得ます。代理人を入れることで、事実をしっかりと整理し、懲戒処分の回避や軽減につながる可能性が上がります。
加えて、勤務弁護士について懲戒請求を受けた場合に、実際に懲戒処分がなされれば事務所全体の評判に関わる可能性があります。当該勤務弁護士について解雇・業務委託契約解除をしたとしても悪影響が払拭できない可能性もあります。
勤務弁護士が懲戒請求を受けている場合も含めて、懲戒請求手続について詳しく、懲戒請求に対する弁護活動経験が豊富な弁護士への相談を検討している先生方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
【弁護士が解説】訴訟上の書面等に不適切な記載をしてしまった場合にどのようにすればよいか

【事例】
X弁護士は、ある夫婦の女性の側から夫との離婚調停を依頼されました。女性曰く、夫は一切家事をせず、家にお金を入れることもなく、普段自分に暴言ばかり吐いている
とのことでした。
X弁護士が聞いていても、女性の境遇はあまりにも不憫であり、離婚をして自由になる方が幸せであろうと思えるほどでした。
そこで、X弁護士が家庭裁判所に離婚調停を申し立てたところ、夫の側から反論の書面が提出されました。
その書面には、妻が行っていることは全てうそであること、自分は妻を愛していること等が滔々と記載されていました。
これを読んで激高したX弁護士は、次の書面で「この夫は人でなしであり、人間の心を持たない化け物である」等と記載した書面を提出した。
【解説】
弁護士職務基本規程第6条によると、「弁護士は、名誉を重んじ、信用を維持するとともに、廉潔を保持し、常に品位を高めるように努める」とされています。
今回のX弁護士の書いた書面は、たとえ夫側の主張が事実に反する虚偽の主張であったとしても、虚偽であることを主張するものではなく、単にその人格を否定する内容となっています。
このような内容の書面は、いくら依頼者のためであるとしても、品位ある書面であるとは言えません。
ただ、さすがに弁護士個人の感情としてあからさまに名誉を毀損し、品位を害する書面を記載することはそれほど多くないと思われます。
実際には、依頼者から感情的な表現をすることを依頼され、弁護士もこれに同情して記載してしまうのではないかと予想されます。
それでも、たとえ依頼者からの依頼であったとしても、最終的には弁護士名義で書面を出すのですから、弁護士としての基本的なルールは遵守する必要があります。
だからと言って、依頼者自身が感情的な表現を記載した文書を、弁護士が証拠として提出することも、不法なものに加担することになりかねませんので注意する必要があります。
ですので、対外的に発出する文書や、証拠については、提出前に一旦見返し、冷静な気持ちで本当に提出してよいものかどうかを考える必要があります。
また、このような事案の場合には弁護士の側に非があることが比較的はっきりしているので、示談交渉を行い、謝罪等をして処分の軽減を目指していくことも考えられます。
【最後に】
弁護士が懲戒請求を受けた場合、弁護士は代理人ではなく紛争の当事者となります。代理人として紛争にあたるのはいつもどおり出来たとしても、当事者として紛争にあたる場合には思った通りの活動が出来ないということはあり得ます。代理人を入れることで、事実をしっかりと整理し、懲戒処分の回避や軽減につながる可能性が上がります。
加えて、勤務弁護士について懲戒請求を受けた場合に、実際に懲戒処分がなされれば事務所全体の評判に関わる可能性があります。当該勤務弁護士について解雇・業務委託契約解除をしたとしても悪影響が払拭できない可能性もあります。
勤務弁護士が懲戒請求を受けている場合も含めて、懲戒請求手続について詳しく、懲戒請求に対する弁護活動経験が豊富な弁護士への相談を検討している先生方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
懲戒委員会④
1 懲戒委員会の審査手続
懲戒委員会は、弁護士会からの求めに応じて審査を開始します。そのため、独自に事件を立件することはできません。
また、弁護士会が懲戒委員会に審査を求めるのは、綱紀委員会が「懲戒委員会に付する」決定をした場合に限られますので、弁護士会の会長なり常議員会が、何らの決定もなくいきなり懲戒委員会に事案の審査を求めるということも許されません。
事案が適法に懲戒委員会に付されることになると、対象弁護士、懲戒請求者、日弁連(付されたのが弁護士法人で、他の所属会があればその会にも)に対し、懲戒委員会の審査に付された旨と事案の内容を通知することとなっています。
2 審査期日
懲戒委員会は、事案の審査を求められたときは、速やかに、審査の期日を定め、対象弁護士等にその旨を通知しなければならないこととされています(弁護士法第67条1項)。
そして、その審査期日には、対象弁護士は出頭し、陳述をすることができます(同条2項)。
3 審査方法
懲戒委員会は、審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができます(同条3項)。
懲戒委員会の求めに対しては、対象弁護士については会則により協力が義務付けられているものの、その他の者についてはこれを強制する手段などはなく、協力を求めるものということになります。また、対象弁護士がこの手続きに協力しなかったことについては、協力しなかったことを理由に懲戒事由の存在を推認するというような証明妨害の規定はありませんので、これを不利益に考慮することはできないものの、会則に定められた協力義務に違反するものであることとを理由に別途懲戒事由を構成する可能性があります。ただし、この場合でもいきなり懲戒委員会が懲戒事由に協力しなかったことを挙げることは許されないと考えるべきであり、懲戒委員会の委員長から弁護士会会長に対して請求の対象外の事実があった旨を報告し、別途会長等の機関が会立件を行うという手続きを経る必要があると考えられます。
4 刑事訴訟との関係
懲戒委員会は、同一の事由について刑事訴訟が係属する間は、懲戒の手続を中止することができるとされています(弁護士法第68条)。
刑事手続はあくまでも国家の刑罰権行使であり、懲戒手続は弁護士たる身分への処分ということになりますので、別々の手続きということにはなりますが、刑事裁判を経ることでより事案の真相が解明される可能性があるということでこのような規定が設けられたと考えられています。
ただ、法文から明らかなとおり、必ず中止しなければならないものではありませんので、懲戒委員会で事案ごとに判断して手続きを中止するかどうかを検討するということになります。
弁護士法人の懲戒②
1 弁護士法人への懲戒
⑴退会命令
弁護士法57条2項3号によると、退会命令ができるのは、当該弁護士会の地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対するものに限るとされています。そのため、従たる法律事務所だけは退会させることが可能です。
これに対し、主たる法律事務所については、退会命令を出すことができません。これは、弁護士法人については自然人である弁護士と異なり、入会審査の手続きが存在せず、弁護士法人が設立されると、その登記した所在地に対応する弁護士会に入会することになると考えられていることから、退会命令を仮に出したとしても、弁護士法人の所在地を移転さえさせてしまえば別の弁護士会に入会してしまうため、退会命令の実効性がないとされているからです。
⑵除名
反対に、弁護士法人を除名できるのは、当該地域内に主たる法律事務所を有する弁護士会のみです。
弁護士法人に対する除名は、弁護士法人を一方的に解散させる効果を有します。そのため、弁護士法人自体は清算手続に入ることになりますが、所属する弁護士の弁護士としての身分には影響しません。
2 法律事務所の移転禁止等
弁護士法人は、特定の弁護士会の地域内にあるすべての法律事務所について業務停止の懲戒処分を受けたときは、その期間中、その地域において法律事務所を設け、移転することはできません。このようなことを許せば、新しく隣に事務所を設置することができてしまい、業務停止の潜脱となるからです。
また、退会命令を受けた場合には、3年間その地域内に法律事務所を設置することができなくなります。
先述の通り、弁護士法人には入会審査がなく、登記をすれば直ちにその弁護士会に登録した状態になりますので、退会命令後すぐ法律事務所を設置できてしまいます。このようなことが起きないよう、3年間は事務所を設置できないこととしています。
懲戒委員会③
1 除斥・忌避・回避
訴訟法上、裁判官には除斥、忌避の制度があり、そうでなくとも裁判官自らが回避することもあります。
これに対して、弁護士法上は、懲戒委員会の委員について除斥、忌避、会費の制度は定められていません。
しかし、懲戒委員会は、裁判と同様、弁護士の身分を剥奪する重要な委員会ですから、中立性がないような委員が評議、議決に加わるべきではありません。そのため、多くの単位会では会則等に除斥、忌避、回避に関する規定が置かれています。
なお、本来除斥されるべき委員が、そのまま評議、議決に加わった状態でなされた懲戒をする旨の議決については、会則に違反する状態でなされた議決ということができますので、無効と判断される可能性があります。
2 部会制度
懲戒委員会では、事案の審査を行うため、部会を設置することができます(弁護士法66条の5)。
このような部会の設置を認めるのは、毎回委員会を開くために多数の委員を参集することとなれば、多数の事案を処理しなければならない単位会での議事が困難になると考えられたからです。
そのため、少人数の部会を設置し、部会で審査した事案については部会の議決をもって委員会の議決とすることができるようにされています(弁護士法第6条の5第5項)。
ただし、懲戒委員会は、身内びいきにならないよう、外部の委員を選任することとされている関係で、この部会にも裁判官・検察官・弁護士・学識経験者の各種類の委員が少なくとも1名はいるようにしなければなりません。
弁護士法人の懲戒①
1 弁護士法人の懲戒
弁護士法人は、弁護士同様弁護士会に所属をしており、弁護士会による監督を受ける存在です。
そのため、所属弁護士とは別に弁護士法人自体についても懲戒を行うことが可能となっています(弁護士法30条の2以下)。
もちろん、弁護士法人に所属する弁護士自体に懲戒処分を出すことも可能ですが、仮に弁護士法人自体に懲戒ができないとすれば、所属弁護士を入れ替えるだけで業務を継続できることになってしまい、組織的に行われた非違行為等に対応できなくなる可能性があります。ですので、弁護士法は弁護士だけではなく弁護士法人にも懲戒処分を行うことができるようにしています。
2 懲戒事由
弁護士法人に対する懲戒事由は、弁護士に対するものと同じです。
⑴戒告
これについては全く自然人たる弁護士と同じです。
⑵業務停止
弁護士法人は、主たる法律事務所と従たる法律事務所を有している場合があります。
この場合、従たる法律事務所を監督する弁護士会は、その従たる法律事務所のみを業務停止にすることが可能です。
これに対し、主たる法律事務所を監督する弁護士会は、その弁護士法人自体に対する監督権限を有していますから、主たる法律事務所だけではなく、他の管轄区域にある従たる法律事務所の業務の停止も命ずることが可能です。
弁護士法人が業務停止の処分を受けた場合でも、そこの所属する社員弁護士や使用人弁護士自体は、弁護士としての業務停止を受けたものではありませんから、個人として弁護士業務を行うことは可能です。
この点については「被懲戒弁護士法人の業務停止期間中における業務規制等について弁護士会及び日本弁護士連合会の採るべき措置に関する基準」(平成13年12月20日理事会議決)があります。弁護士法人自体が業務停止となった場合、基準第2第1項16号ロによると「被懲戒弁護士法人の社員等は、被懲戒弁護士法人が第一号又は第二号の規定により解除すべき、又は解除した法律事件等を、自己の業務として引き継いで受任することができない。」とされていますので、個人として受けていた業務は継続できるものの、事務所として受任した事件については、これを個人に引き継いで受任することはできないとされています。
懲戒委員会の独立性が問題となった事案
1 事案の概要
A弁護士は、B弁護士会に所属する弁護士であるが、B弁護士会ではA弁護士に対して1年間の業務停止とする処分が決定した。
これに対してA弁護士が日弁連に審査請求したところ、日弁連は不服を入れ、処分を戒告に変更した。
ただ、この戒告処分に対してA弁護士が東京高裁に対して取消訴訟を提起した。
取消訴訟の中でA弁護士が主張したのは、B弁護士会懲戒委員会が開かれた際、そこに本件懲戒請求の請求者でもあるB弁護士会会長が出席し、意見を述べるなどしたことが、委員会の公正を疑わせるのではないかという点である。
(東京高判昭和42年8月7日の事案)
2 裁判所の判断
懲戒は弁護士にとつて刑罰にも比すべき重大なことがらであつて、その審理、判断に特に公正が要求されることはいうまでもないところであり、法は、弁護士会が所属弁護士を懲戒するには必ず懲戒委員会の議決に基づくことを要求し(弁護士法五六条二項)、弁護士会長その他の理事者に裁量の余地を与えず、かつ、右懲戒委員会は、その委員に弁護士のほか裁判官、検察官および学識経験者を加えてこれを組織すべきものとし、その弁護士委員も弁護士会の総会の決議に基づくべきものとして(同法六九条、五二条三項)、つとめて理事者の影響から独立した機関としている。こうした法の趣旨にかんがみると、懲戒委員会における具体的事件の審査に、理事者が故なく出席して意見を述べることは、当該審査の公正を疑わしめるものとして、許されないものと解するのが相当であり、その点において、B弁護士会の懲戒委員会が本件事案についてした審査手続にはかしがあるものといわねばならない。
しかし、その点については、原告の異議申立に基づき、被告の懲戒委員会においてさらに事案の実体につき適法公正な審査を遂げ、その議決に基づき、被告はB弁護士会のした業務停止一年の懲戒処分を重きに失するものとして取消し、懲戒として最も軽い戒告処分に変更しているのであるから、ほかに特段の事由がない限り、B弁護士会の懲戒委員会における右審査手続のかしは、これをもつて被告のした本件懲戒処分を取消すべき事由とするに足りないものと解する。
3 解説
懲戒委員会は、弁護士の身分を剥奪する可能性のある重要な委員会であるため、この委員会は弁護士会と独立している必要があると考えられました。
そのため、弁護士会の会長が懲戒委員会に出席して発言した場合、委員の意見が会長の意見に引っ張られる可能性も否定できず、このようなことを行うことは、懲戒委員会の独立性を害することと考えられました。
実際、法律上は明文の規定はありませんが、弁護士会の役員、常議員が、懲戒委員会の委員を兼任することは不適切である旨の日弁連の通知等が存在し、これに基づいて委員は選任されるようになっています。
懲戒委員会②
1 懲戒委員会の委員
懲戒委員会の委員の定数は4名以上であることは定められていますが、それ以上に何人選任するかについては会則で委ねることとされています(弁護士法66条)。
また、懲戒委員会の委員は弁護士、裁判官、検察官及び学識経験者の中から弁護士会の会長が委嘱するとされています。このうち裁判官・検察官については出身母体である裁判所・検察庁の長の推薦に基づき、弁護士委員については弁護士会の総会で決定することが定められています(弁護士法66条の2第1、2項)。学識経験者については特に定めがありませんが、多くの場合は近隣の大学の法学部の教授などが選ばれているようです。
委員の任期は2年とされており、懲戒委員会の職務を行うにあたっては、委員は法令により公務を従事する職員とみなされています(3、4項)。
2 予備委員
懲戒委員会の委員は、その選任方法が法定されており、弁護委員については総会を開く必要があるなど大掛かりであることから、委員が欠けた場合にすぐに補充することができません。
そのため、委員については予め予備委員を選任することとされています(弁護士法66条の4)。そして、たとえば裁判官出身の委員が除斥、忌避等で欠けることになった場合には、同じく裁判官出身の予備委員が代理してその職務を行うということなっています。
3 懲戒委員会の運営
懲戒委員会の委員長は、委員の互選により決定することとされていますので(弁護士法第66条の3)、どの出身母体の委員が委員長になると決まっているわけではありません。
先述の通り、委員の職務は公務とみなされることになっていますので、懲戒委員会の委員が作成する文書については公文書となりますし、超過委員会の委員の職務を妨害した場合には公務執行妨害罪が成立します。
懲戒委員会の定足数について法律上の定めはありませんが、半数以上の出席が必要であると会則で定められている例があります。ただし、この半数の中に、法律上定められている裁判官・検察官・弁護士・学識経験者の4種類の委員が必ず存在しなければならないかについては見解が定まっていません。検察官委員が欠席であったとしても、裁判官委員や学識経験者委員が出席していれば、懲戒委員会の外部性は担保されているとも言えますし、外部委員が1名しかいない場合に、その1名が出席しなければ議事が滞るというのでは問題が多いですから、必ずしも4種類の委員すべてがいなければならないとまでは考えられていないようです。
懲戒処分を受けた者がした行為の効力
1 業務停止以上の処分を受けた場合
業務停止、退会命令、除名の処分を受けた場合、業務停止中はその期間弁護士の業務を行うことができなくなりますし、退会命令、除名の処分を受けた場合には効力発生後からは弁護士登録がなされていない状態となりますから、当然弁護士としての業務を行うことはできなくなります。
そのため、このような弁護士としての業務が行えない状態になっている期間に弁護士としての業務を行った場合、これが弁護士法上違法なものであることは明らかだと思われますが、それ以外(たとえば民事訴訟や刑事訴訟など)の場面ではどのように扱うべきかが問題となります。
2 民事訴訟における行為の効力
民事訴訟の代理人として、弁護士たる業務を行えない者がなした行為は、訴訟法上どのように解釈されるべきでしょうか。
民事訴訟法上は、一定の例外は存在するものの、弁護士代理の原則が存在します(民事訴訟法54条1項)。これを厳格に解釈すると、弁護士ではない者が代理して行った訴訟行為は、一切無効なものであると考えることになります。
しかし、これを厳密に考えすぎると、それまでに訴訟が進行し、相手方や裁判所が対応してきた訴訟行為も含めて一切無効という解釈になり、手続の安定性を害することになってしまいます。
そのため、弁護士たる業務を行えない者を訴訟から排除しなければならないことには異論はないものの、これまでに行ってきた訴訟行為を有効と判断するかについては解釈が分かれています。
この点について、最判昭和42年9月27日では、その代理人が弁護したる資格を喪失している状態(業務停止中)を看過してなされた訴訟行為について、直ちに無効になるものでない旨判示されました。この事例は、業務停止中の訴訟行為であったため、期間が経過すれば再び弁護士に戻る者ということになりますので、除名や退会命令の場合に同様の判断を行うことができるかどうかは判然としません。ただ、最高裁は、手続の安定性確保のため、上記のような結論を採用しました。
3 刑事訴訟
憲法37条により、被告人には弁護人を依頼する権利が与えられています。このような弁護人の地位は相当公益性が高く、弁護士資格が当然の前提となるように思われます。
そのため、たとえ業務停止中であっても、弁護士業務が行えない状態でなされた訴訟行為等については無効であると考えるべきですし、被告人の追認も同様であると思われます。
なお、被疑者については弁護人選任権が憲法上付与されているわけではありませんが、憲法31条に基づき刑事訴訟法が制定されていると考えられますので、同様に理解してよいのではないかと思われます。
4 訴訟外の行為
除名、退会命令を受けた元弁護士が弁護士同様有償で法律上の業務を行うことは、弁護士法72条に違反することになります。そして、この弁護士法72条は、公益性の高い規定であると考えられますので、弁護士法72条に違反してなされた行為については民法90条により無効となる可能性があります。
反対に、業務停止中の弁護士が代理して行った訴訟外の行為については、あくまでも業務停止中には弁護士たる資格を喪失するわけではないので、そのような代理行為は懲戒事由とはなるものの、弁護士法72条に違反するものではありません。しかし、国民を非弁護士から保護するという弁護士法72条の規定の趣旨からすると、懲戒の処分により業務を停止された弁護士に代理行為を行わせるのは適当ではないと思われますので、このような場合にも無効となる可能性はあるように思われます。
懲戒委員会①
1 懲戒委員会
弁護士会が、当該単位会に所属する弁護士又は弁護士法人を懲戒する場合には、弁護士会の懲戒委員会による議決に基づく必要があります(弁護士法第58条5項)。
弁護士法は、弁護士(弁護士法人)を懲戒するかどうかについて、会長の独断や弁護士会の総会等の意思決定機関ではなく、懲戒委員会に判断させることにしていますので、この懲戒委員会は独立性を保つ必要があります。
そのため、法の明文はないものの、懲戒委員会の弁護士委員としては、会長副会長等の役員、常議員会の常議員、綱紀委員会の委員と兼職することは適当でないと考えられています(日弁連会長通知等)。
2 懲戒委員会の設置等
弁護士法65条1項により、懲戒委員会は日弁連及び単位会に設置されることとされています。綱紀委員会と共に弁護士法上設置することが定められている委員会ですので、「弁護士法上委員会」などと整理している単位会も存在します。その他弁護士会には人権擁護委員会や刑事弁護委員会なども設置されていますが、これらの委員会は会則等で設置されることとなっているものですので、綱紀・懲戒委員会は設置根拠からしても全く別のものということになります。
懲戒委員会は「その置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の求めにより、その所属の弁護士又は弁護士法人の懲戒に関して必要な審査をする。」(弁護士法65条2項)とされており、懲戒に関して必要な審査をすることがその任務となっています。
ここでの「必要な審査」とは、綱紀委員会が懲戒委員会に付することを相当と議決した事件の審査を指していますので、懲戒委員会が独自で事件を立件するということは想定されていません。
最終的に懲戒委員会で事案の審査を行い、懲戒をするべきか否か、懲戒するとすれば除名、退会命令、業務停止、戒告のいずれの処分が妥当であるのかを決定することとなります。
3 権限
懲戒委員会は、「審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。」(弁護士法67条3項)というように、対象弁護士等に説明などを求めることができます。
対象弁護士は、弁護士である以上綱紀・懲戒の手続きに協力する義務を負っていますので(日弁連会則第72条)、これに応じなかった場合に罰則等の手段はありませんし、これを説明や回答等を強制する法的手段はありませんが、応じなかったことそれ自体が会則違反であるということを理由に懲戒事由となる場合があります。