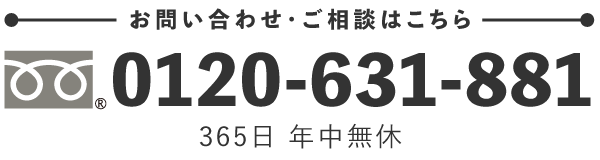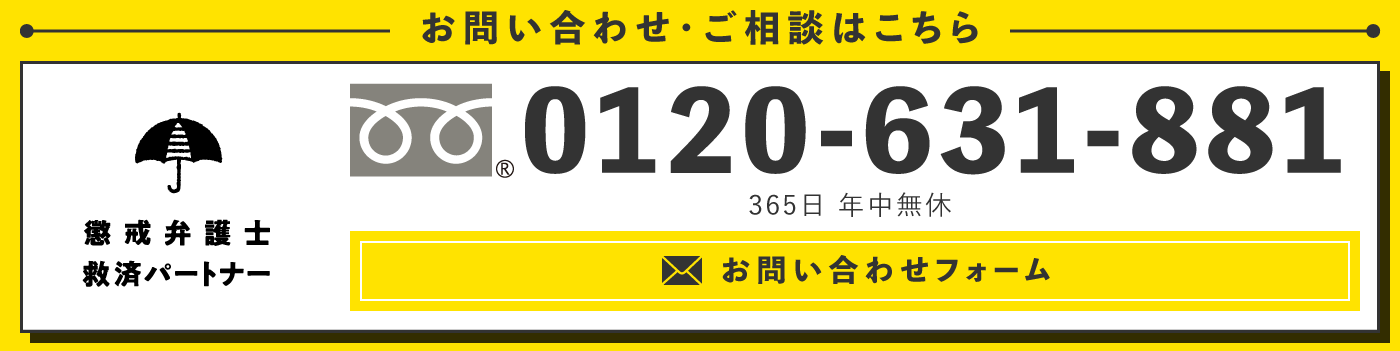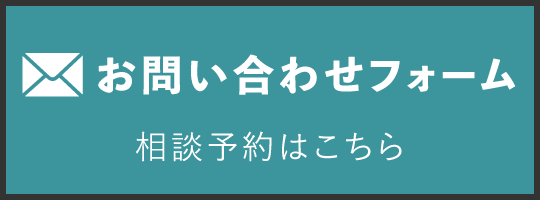Archive for the ‘懲戒処分’ Category
【弁護士が解説】利益相反規定に直接は当てはまらないような場合に受任をすることは可能か
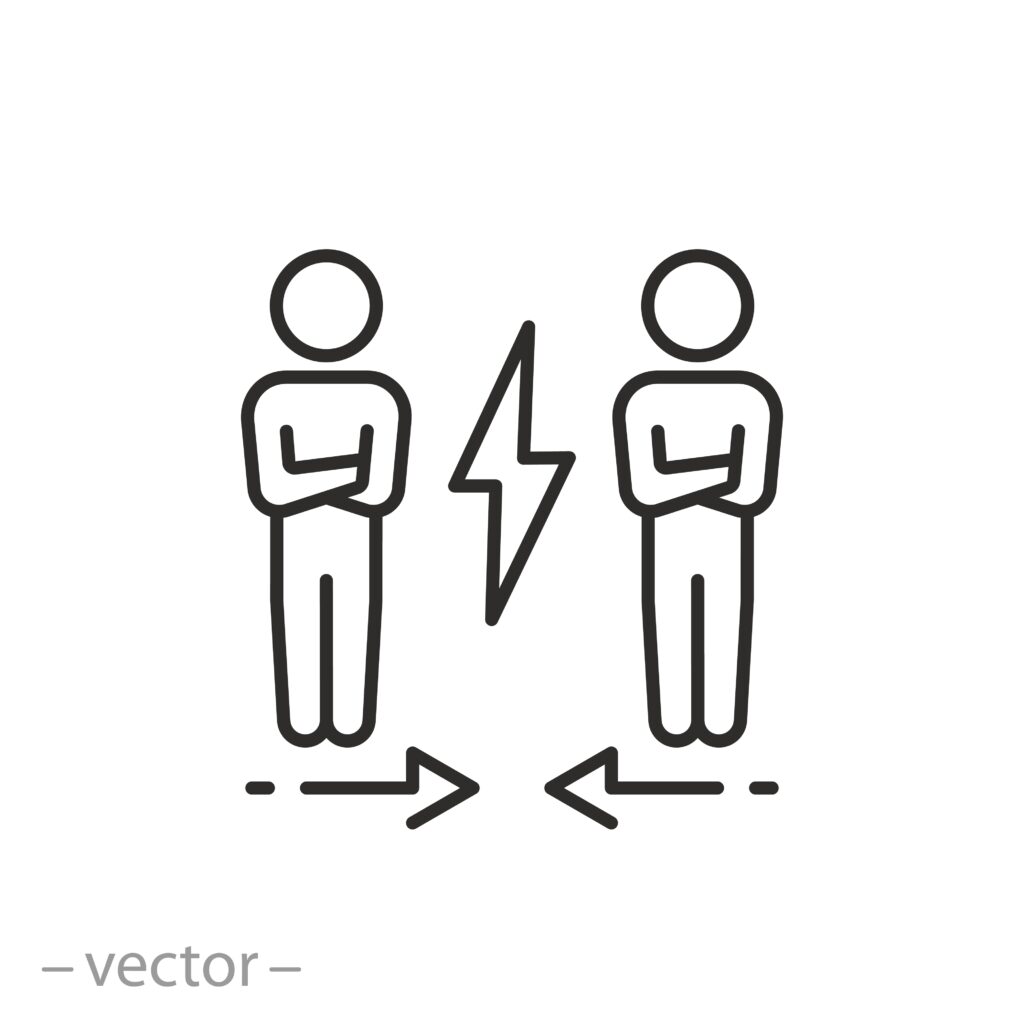
【事例】
X弁護士は、亡Aの遺産相続に関して遺言執行者に選任され、遺言執行を終えた。
ただ、その遺産の中にあった不動産について、Aの相続人のBとCの間で対立があり、Aの遺言上はBが相続するということになっていたのでXもその通り手続きを進め、登記上はBが所有者となったのだが、実際にはCが占有を継続しているような状況となった。
X弁護士は、遺言執行が終了した後、Bから「先生、Cがまだ建物を占拠しているのは納得できないので、先生が私の代理人となってCを訴えてください」との依頼を受けた。
そこで、X弁護士は、Bを代理して、Cに対して明け渡し訴訟を提起した。
【解説】
X弁護士が最初に請け負っていた事件は、遺言執行であり、依頼者はいうなれば亡Aでした。しかし、遺言執行者は特定の相続人の代理人というわけではありませんので、相続人間では公平であるべきです。
実際、東京高判平成15年4月24日によると「遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の権利義務を有し(民法一〇一二条)、遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない(同一〇一三条)。すなわち、遺言執行者がある場合には、相続財産の管理処分権は遺言執行者にゆだねられ、遺言執行者は善良なる管理者の注意をもって、その事務を処理しなければならない。したがって、遺言執行者の上記のような地位・権限からすれば、遺言執行者は、特定の相続人ないし受遺者の立場に偏することなく、中立的立場でその任務を遂行することが期待されているのであり、遺言執行者が弁護士である場合に、当該相続財産を巡る相続人間の紛争について、特定の相続人の代理人となって訴訟活動をするようなことは、その任務の遂行の中立公正を疑わせるものであるから、厳に慎まなければならない。」とされており、中立性が要求されています。
本事例と同様の事例において、戒告の処分とした例があります。遺言執行者としての任務が終了したからといって直ちにどのような事件でも受任可能になるというわけではなく、特定の相続人に偏ったものではないかどうかを検討したうえで、弁護士の公平さ(弁護士職務基本規程第5条)に反しないかを検討するべきであると言えます。形式的には利益相反の規程に反しませんが、注意を要します。
【弁護士が解説】弁護士が受任をしてはいけない事件にはどのようなものがあるか
【事例】

X弁護士は、A株式会社の顧問弁護士を長らく務めており、会社の代表取締役Bからの信任も厚かった。
ある日、X弁護士のもとへ、Bから「大変だ。うちの従業員が何かをして逮捕されたらしい。先生が弁護活動してもらえませんか」という連絡があり、実際に警察署に行ってみると、A社に勤務しているCが盗撮の疑いで逮捕されていた。Cに話を聞き、弁護人をどうするのか尋ねたところ、社長の意向に従うということであったので、そのままXがCの弁護人となることになり、AとXの間で委任契約が締結されることとなった。
1 X弁護士として気を付けるべきことはなんでしょうか。
2 後にA社において、Cを懲戒処分とするべきかの議論が行われました。Xのところへも、Bから「C君について、懲戒解雇相当だと思うのが、どうだろう」という質問がありました。Xとしてはどのように対応するべきでしょうか。
【解説】
刑事事件の被疑者、被告人の方に、勤務先の顧問弁護士が面会を行い、そのまま弁護人として選任されるということはそれほど珍しくありません。しかし、注意すべき点があります。
1 守秘義務違反
まず、弁護士には弁護士法上の守秘義務が課せられます。弁護士職務基本規程では「依頼者について」という文言となっていますが、一般的な解釈としてはこの対象は限定されていません。
今回でいえば、委任契約者はBということになりますが、基本的に秘密にしたい事項が多いのはCとなります。また、委任契約の当事者でなかったとしても、XはCの弁護人となりますので、Cに関する秘密は守秘義務の対象となります。
そうすると、Cの秘密は、たとえ委任契約を締結しているのがBであったとしても、Bに対しても口外してはならないということになります。
会社の顧問弁護士が従業員の事件を受けること自体は否定されるものではありませんが、守秘義務の点が問題となりますので注意が必要です。特に、このようなケースでは、C自身が「お金を払ってもらっているのだから話をしなければならない」と勘違いしている可能性も相応にあります。ですので、Cと面会する際には、守秘義務の存在や会社に伝えていい範囲などを十分に確認しておく必要があります。
2 利益相反
Cの性的姿態等撮影被疑事件の弁護人であったXですが、今度はCに懲戒解雇の話が持ち当たっています。
Cの刑事事件と、Cを解雇するという話では、当事者は同じCではあるものの、事件の種類や手続きは全く異なります。このような場合、Xは後の事件である解雇に関わってよいのでしょうか。
弁護士法25条及び弁護士職務基本規程27条、28条には、職務を行い得ない事件が記載されています。いわゆる「利益相反」に関する規制です。
弁護士法25条1項は「相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件」を受任することを禁じています。
今回の事例で見ると、X弁護士は、①A社の顧問弁護士②Cの弁護人の順番で受任をしていますので、後から出てくるのはCの事件です。しかし、Cを解雇するかどうかという問題は、X弁護士がCの弁護人になってから生じた問題であると言えます。そうすると、契約の順番とは反対となりますが、「Cの弁護人であったXが、Cの解雇について助言できるか」という問題が設定されることになります。
Cの解雇に関する問題の「相手方」は、Cを指しています。ただ、解雇という労働問題と、刑事事件は全く異なる手続きですので、一見すると受任可能なように見えます。しかし、過去の日弁連の決定の中には、事件の同一性は、単なる訴訟物の同一等のみで判断するのではなく、実施的な判断するべきであることが指摘されています。
Cの刑事事件もCの解雇も、いずれもCが盗撮をしたことに端を発しています。そうすると、事実上事件は同一であるといえ、Cの弁護人であったXは、Cの解雇に関する事件について関与しない方が適切であると考えられます。
【弁護士が解説】共犯者双方の弁護人を引き受けるとどのような問題が生じるか
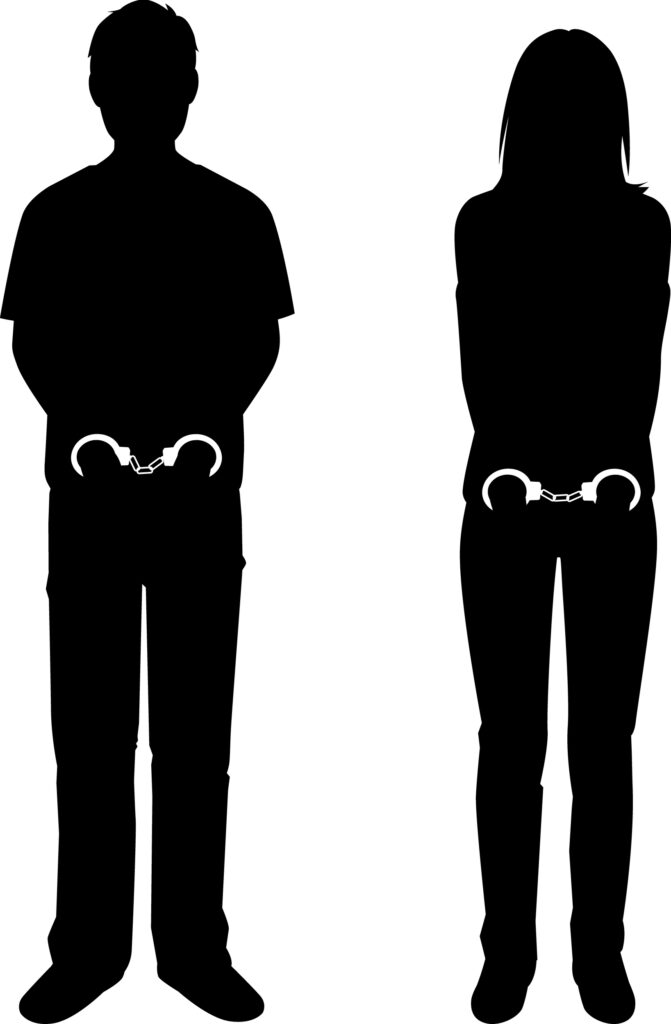
【事例】
X弁護士は、ある窃盗事件を起こしたAから私選の刑事弁護の委任を受け、弁護人として活動していた。窃盗事件の内容は、Aが別の共犯者Bと共謀してカードショップに忍び込み、高価なカードを盗むというものであった。
この事件でAは逮捕されていたが、同時にBも逮捕されているようであった。また、報道によるとAもBも両方とも事件について認めている様子であった。
AとBは元々地元の先輩後輩の間柄であり、AはBの先輩であった。本件事件についても、AがBを誘い、分け前を分配するということでBはしぶしぶ応じるような形で現場についてきていた。
ある日X弁護士がAの面会に行くと、Aから「Bも逮捕されていると聞いている。Bは自分の後輩だし、もとはと言えば自分が誘ったようなものだから、自分が迷惑をかけてしまっている。お金については自分が負担するので、先生がBの弁護士もやってください」と依頼された。
X弁護士はこの依頼に応じるべきであろうか。
【解説】
今回は、共犯事件において、共犯者相互の弁護人になることができるのかという問題となります。
弁護士法や弁護士職務基本規程では、同時に複数人の弁護士となることについて「利益相反」の規定があります。ただ、たとえば弁護士法25条1号では「相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件」のような定め方をしており、ある事件において依頼者と相手方と双方を受けることなどは禁じていますが、刑事事件共犯者相互についてどのように考えるのかは明らかではないところもあります。
そもそも、刑事訴訟規則29条5項では「被告人又は被疑者の利害が相反しないときは、同一の弁護人に数人の弁護をさせることができる。」と定めており、1人の弁護士が複数人の弁護をすることが想定されています。ただ、こちらでも「利害が相反しないとき」という条件が付されています。
それでは、刑事の場合に「利害が相反する」とはどのような場合を指すのでしょうか。
典型的に問題になりそうなのは、共犯者の一方は認め、片方は否認というケースです。認め事件と否認事件では、事件への対応方針も大きく異なり、特に認めている共犯者の方が否認している共犯者についての関与を自白するような場合には、明らかに一方の行動が他方に不利になっていると言えます。
次に、共犯者双方が認めていたとしても、その間に上下関係や主従関係がある場合です。一方が主導的な役割を果たし、他方が従属的な場合、従属的な者の弁護人となった場合には当然主犯に従っただけであるという弁護活動を展開します。ただ、これは主犯に責任を多く負担させるという主張ですので、主犯から見れば不利益になっているとも言えます。
それでは、両方とも否認をする場合はどうでしょうか。この場合、否認の内容にもよります。たとえば、お互いが「相手方が1人でやった」というような主張であれば利益相反は明らかですが、双方黙秘の場合には表面上は利益相反は明らかではありません。
一般的に、複数人の弁護人を同時に引き受けることには慎重であるべきとされています。それは、弁護活動が時間の経過によりさまざまな変化を見せる以上、たとえ現時点で利益相反の問題が生じていなくとも、将来的に利益相反となる可能性は常に存在するからです。そして、いったん利益相反が顕在化してしまうと、どちらか一方の弁護人を辞任するだけでは足りず、双方の弁護人を辞任するべきであると考えられているため、どちらの依頼者にも迷惑をかけることになってしまいます。
今回の事例では、AとBの間に主従関係があるようです。また、Bの弁護士費用はAが負担すると述べています。このようにお金をAが負担していると、BとしてはAに反抗するような主張をしにくくなる可能性があります。以上のような理由から、X弁護士としては受任を差し控える方が好ましいと言えます。
【弁護士が解説】法令調査義務違反をした場合どのような処分となるのか

【事例】
X弁護士は、Aから労働トラブルについての相談を受けたが、その際同僚からの名誉毀損行為についての相談も受けた。
X弁護士としては、Aが受けた被害が、公衆の面前でAの様子などをバカにするような内容であったため、名誉毀損罪は成立するであろうと考えた。そこで、Aに対して慰謝料の請求ができるということのほか、刑事告訴が可能であるということを伝えました。なお、この名誉毀損発言があった時期は、令和5年4月3日、相談を受けた日は令和6年4月3日であるとします。
X弁護士の行為にはどのような問題があるのでしょうか。
【解説】
前提として、X弁護士の法的判断は正しく、名誉毀損罪は成立するとします。
名誉毀損罪は、親告罪となっています(刑法232条)。そのため、告訴がなければ公訴を提起することはできません。
しかし、「親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。」とされています。そのため、名誉毀損罪においては、公訴時効とは別に告訴できる期間に制限があるということになります。
冒頭の設例では、Aが犯人を知ったのは、当然同僚であるため事件日です。しかし、Aが相談に訪れたのは、事件から1年後になっています。そのため、親告罪の告訴期限を経過しており、現時点から受任したとしても、告訴をすることはできません。ですので、X弁護士はAに対して誤った説明をしたことになります。
弁護士職務基本規程第37条1項によると、「弁護士は、事件の処理に当たり、必要な法令の調査を怠ってはならない。」とされています。その他に、同規程7条には「弁護士は、教養を深め、法令及び法律事務に精通するため、研鑽に努める。」とされているほか、弁護士法2条にも「弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。」とされています。
このように、弁護士は法律の専門家として、法令に精通し、法律を調査する義務を負っています。なお、弁護士職務基本規程37条2項は「弁護士は事件の処理に当たり必要かつ可能な事実関係の調査を行うように努める。」となっており、事実調査については努力義務の規程となっていますが、1項は義務づけられているところに違いがあります。
X弁護士は、法律的に誤った回答をしていますので、この法令調査義務に違反していると考えられます。事案の趨勢や勝ち負け等といったことは法令に基づくものではありませんので、見通しが誤っていたこと等はこの規程との関係では問題となりません。しかし、X弁護士のように、法律上不可能(かつ不変)な回答をしてしまったり、上訴等の期限を徒過してしまったような場合には、純粋に法律上の判断でありかつ裁量の余地もないようなものなので法令調査義務違反となってしまいます。
このような場合、戒告以上の処分となる可能性が否定できません。特に、今回のような刑法犯、親告罪の告訴というような比較的単純な法律についての問題であれば、その分処分が重くなってしまいます。
このような事態に陥った場合には、すぐに依頼者に正しい法律の解釈を伝えたうえで、場合によっては委任契約の解除や依頼者との和解等の手段をとる必要があります。また、そもそもこのような事態に陥らないためには、日常的に接する分野以外については直ちに回答せず法令調査をしてから改めて回答する旨伝える等、慎重に対応する必要があります。
弁護士において、法令調査義務は相当重い義務です。ただ、弁護士の信用の源泉となっていますので、処分としても比較的重いものが下されます。依頼者からの懲戒請求があったり、紛議調停申し立てがあったような場合には、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
【弁護士が解説】依頼者からの要求は何でもするべきか、その危険性について解説

【事例】
X弁護士は、ある夫婦の妻Aから相談を受け、自身の夫であるBが浮気をしているので何かできることはないかと尋ねられた。
Aが持参してきた調査会社の報告書や、LINEの履歴などから見て、確かにBが不貞行為をしていることとはほとんど確実であると考えたXは、Aに対して離婚や慰謝料の請求を行うことができる旨を説明した。
しかし、Aとしてはそのようなことではとても収まりがつかず、Bの生活をめちゃくちゃにしてやりたいという希望があった。そのためAはXに対し、「あいつのことは絶対に許せない。今の生活ができないようにしてやりたいので、Bの実家や職場に先生から不貞慰謝料請求の内容証明郵便を出してもらいたい」と告げた。
Xはこのようなことに応じてよいだろうか。
【解説】
XにとってAは依頼者となりますので、弁護士職務基本規程第22条の「弁護士は、委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務を行うものとする。」という規律が当てはまります。そのため、Aが希望することについては基本的にその意思を尊重すべきであると言えます。
しかし反面、弁護士である以上、「弁護士は、事件の受任及び処理に当たり、自由かつ独立の立場を保持するように努める。」(同20条)、「弁護士は、良心に従い、依頼者の権利及び正当な利益を実現するように努める。」(同21条)、「弁護士は、名誉を重んじ、信用を維持するとともに、廉潔を保持し、常に品位を高めるように努める。」(同7条)などの規程も定められています。そのため、たとえ依頼者の希望であったとしても、何でもそのまま行ってよいということにはなりません。
今回の事例で考えると、不貞行為をしているということは通常人に知られたくないものであることは間違いありません。また、公になっているようなもでもないですので、いわゆる「秘密」に属することは明らかです。このような秘密について、第三者に口外することは当然守秘義務との関係で問題となります。弁護士職務基本規程23条の秘密保持義務は「依頼者について」の秘密と限定しているものの、弁護士法23条の守秘義務にはそのような限定はありません。この弁護士法23条の守秘義務については、依頼者の秘密に限定されるのか第三者のものも含むのか争いがありますが、日弁連では第三者のものも含むと解釈しています。そのため、今回の事例と同様のケースで、相手方勤務先に離婚事件に関する事実をメールで送信したような事案で弁護士法上の守秘義務違反を認めたケースがあります。
不貞行為があった場合、法的権利として認められるのは離婚や慰謝料の請求が基本的なものです。相手方配偶者の生活環境を破壊するということは、正当な利益ということはできないと考えられますので、これを実現することは、守秘義務違反の問題は別としても基本規程21条や7条の問題を生じさせます。ですので、X弁護士としてはAの依頼を断るべきですし、これで信頼関係が破壊されるようであれば委任契約の解約をする事案ということになります。
今回の事例では、Bの連絡先などが確実に分かっていると言えるケースでしたので、勤務先や実家に連絡をすることが問題となるケースでした。ただ、今回の事例とは異なり、Bの連絡先が勤務先や実家以外全く分からないということは十分あり得ます。そのような場合、弁護士から連絡をすることはやむを得ない場合も存在すると思われます。ただ、そのような場合であっても、事件の内容や弁護士の主張を過度に記載するなどした場合にはやはり同様の問題が生じると思われますので、「連絡が欲しい」程度の簡単な記載に留めるべきであろうと思われます。
【弁護士が解説】委任契約書の不作成はどのような処分となるのか

【事例】
X弁護士は、高校時代からの同級生であるAから債務整理の依頼を受けました。
X弁護士としては、無償で債務整理をするわけではないものの、旧来の友人であるAからの依頼であることから、堅いことはしたくないと考え、委任契約書を作成せず、現金を預り、委任状を作成しました。
X弁護士の行為に問題はないでしょうか。
【解説】
弁護士職務基本規程30条によれば、「弁護士は、事件を受任するに当たり、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。」とされています。そのため、基本的に事件を受任する場合には委任契約書を作成しなければなりません。
ただし、委任契約書を作成しなくてもよい場合もあります。
1つ目は「委任契約書を作成することに困難な事由があるとき」です。この場合、事由が止んだ後作成しなければなりませんが、当面は作成しなくてもよいことになります。どのような場合が「困難な事由」であるかについて特段の解説などは付されていませんが、たとえば病院に入院中でプライバシーが確保できない場合などが考え得ると思われます。
2つ目は、「法律相談、簡易な書面の作成」の場合です。簡単なものである場合には、その場で業務が終了してしまい、報酬も支払われると考えられるので契約書の作成が免除されています。ただ、書面の作成でも複数回の打ち合わせが必要となるもの等の場合には「簡単な」と評価されない可能性がありますので注意が必要です。
3つ目は「顧問契約その他継続的な契約に基づくもの」です。継続的な依頼関係があれば、あえて個別の契約を作成しなくてよいということに基づきます。ただし、顧問契約の対象から外れるようなことを行う場合には、委任契約書の作成を要すると思われます。
いずれにしても「合理的な理由」があれば委任契約書を作成しなくてもよいとされていますが、『解説 弁護士職務基本規程』に明示されているように、旧知の間柄である場合には委任契約書の作成義務は免除されないとされています。ですので、今回のX弁護士の場合には委任契約書の作成義務があることになります。
その上で、契約書作成義務違反に対する処分ですが、弁護士報酬等が明示されるべき契約書作成義務の違反は比較的問題のある違反類型であるとされているようです。ただ、委任契約書を作成しない事例は、比較的期の上の弁護士にみられることや、委任契約書作成義務違反のみで処分を受けることは多くなく、何か他の義務違反も付随している例が多いこともあって、単発でどのような処分になるかは明確ではありません。
ただ、委任契約書作成は基本的な義務ですので、この義務に違反している場合にはほかにも何らかの違反を犯している可能性が高いとも言えます。そのような場合には戒告や業務停止といった処分も十分ありうるところです。
委任契約書の作成が免除されている場合であっても、委任契約書の作成を禁じられているわけではありません。委任契約書であるかどうかは書面の標題のみで決まるものではないので、契約書作成に迷った場合には安全策として何らかの書面を用意しておいた方が良いと思われます。
【弁護士が解説】刑事弁護活動中に被疑者・被告人から依頼をされた場合にはどのように対応すればよいか

【事例】
X弁護士は、窃盗で逮捕、勾留中のAの弁護人です。
ある日、X弁護士が接見に行くと、Aから次のようなことを言われました。X弁護士としてはどのように対応するとよいでしょうか(各設定は独立です)。
①Aから、「実は自分は真犯人ではなく、本当の犯人はBなのだが、Bには義理もあるし、今後もあるから自分が犯人だということで裁判を受けたいと思う」と言われた場合
②Aから、「示談金が必要になるのだが、身寄りもないし、自分の持っているキャッシュカードを先生に渡して、暗証番号も伝えるので、それで示談金を引き出してきて欲しい」と言われた場合
③Aから、「自宅に猫がいるので、猫に毎日餌やりに行って欲しい。」と言われた場合
④現行犯逮捕の事案であり、証拠上もAが犯人であると考えるのが合理的な事件であるが、Aから
犯人性を否認して争って欲しいと言われた場合
⑤保護観察付執行猶予中のAから、再度の執行猶予を付けて欲しいと言われた場合
【解説】
身体拘束中の被疑者、被告人からは様々な依頼を受けることがあります。ご家族など第三者の協力が期待できるような状況であれば協力をしてもらうことになりますが、そうでない場合には弁護人がある程度までは対応することとなります。それではどこまで弁護人が対応するべきなのか、また対応してはいけないと考えられるのはどのようなことなのか、事例ごとに検討していきます。なお、今回は国選であるか私選であるかを明記していません。私選であれば最終的に進退窮まれば辞任をするという方法がありますが、国選弁護人の場合にはそうもいきません。国選弁護人でこのような問題に直面した場合、メーリングリストや単位会の刑事弁護委員会に相談するなど、かならず1人で対応しないようにすることが肝要です。
①いわゆる身代わり犯人の問題です。身代わり犯人を立てること自体、犯人隠避罪に該当するものですので、まずはその点について本人に十分に説明する必要があります。ただ、それでもなお考えが変わらないような場合に、どのような弁護活動をするべきかが問題となります。これについては『解説 弁護士職務基本規程』15頁に詳しい説明がありますが、①私選の場合辞任する②認否をせず情状弁護のみする③被疑者、被告人の意向通りに弁護活動をするという考え方があります。③の場合は弁護士自身も犯人隠避罪の共犯となるわけですが、これについては正当業務行為として違法性阻却されると考えることになります。ただ、③の説を採用した裁判例があるわけではないので、本当に違法性阻却をされるのかは明らかではないところです。また、③の線で進め、仮に被害者と示談交渉をするようなことがあった場合、被害者に対する詐欺になりかねません。そうすると、③でどこまで弁護活動ができるのかということも考えものですから、できる限り本人の説得に努める方が良いと思われます。
②現金の引き出しもよく問題となります。認めている事件の場合には示談交渉が中心となり、特に身体拘束事件では早期に示談をすることが必要です。また、被害者の側からしても本当に支払いを受けられるのかという点が不安ですので、示談書交付時に同時に支払う方が好ましいとも言えます。しかし、協力者が外にいなければ、どうしても拘束中に現金を用意することができません。このとき、弁護人が本人のキャッシュカードを使うかどうかについては、弁護士によって考え方が様々だと思われます。少なくとも使用するとしても、引き出し前と引き出し後の通帳記帳を行い、引き出し行為についての同意などを書証化したうえで行うべきであり、口頭での合意のみで行うことは控えるべきです。
③①②はまだ弁護活動に関する悩みでしたが、③は直接弁護活動に関係することではありません。このような場合、だれか世話をしてくれる第三者を探すなどして、弁護人が直接餌やりを行うということは断るということも考えられます。また、弁護士が被疑者被告人の自宅に1人で入ること自体、後にトラブルになる可能性もあります。ですので、弁護士としては避けたいところではありますが、反面生き物のことですので、無碍にできないところもあります。これについてもどこまでやるかは弁護士それぞれですが、上述のようにトラブルの可能性もありますから、記録に残したうえで対応するべきであるとは言えます。
④弁護士から見て、主張が不合理であり争いようのないと感じられる事件はあると思います。ただ、これについては、弁護士は本人の主張を前提に弁護活動をすべきであると考えられますので、たとえ無理だと思ったとしても本人の意向通りに犯人性否認をするべきです。ただ、やみくもに否認をするのではなく、本人と証拠を検討する中で、厳しい主張となるという心証を伝えることは、信頼関係を害さない範囲であれば問題ないと思われます。
⑤④と異なり、こちらは法律上不可能であるという話です。保護観察付執行猶予中に再度の執行猶予を付することはできませんので、本人の意向はどうしても叶えられません。窃盗罪であれば罰金刑の主張をすることができるのでその方向性で本人を説得することができると思いますが、詐欺のように罰金刑のない罪名の場合には、そのような方向も取れません。ひとまずは本人に法律上の制度を説明し、それでも納得しなかった場合にどのような方向性をとるかが問題となります①法律を無視したうえで主張する②刑法の規定を憲法違反であると主張し、違憲無効であると述べたうえで主張する③寛大な処罰を求めるとする、など考えられるところです。ただ、①の場合には法律精通義務違反になっているように見えるところでもありますので、後から本人からこの点を指摘される可能性もあります。ひとまず②の主張をするか③も本人の意向に含まれると考えて主張するかというところですので、よく本人と協議のうえで弁論をする必要があります。
【弁護士が解説】弁護士自身の犯罪はどのような影響を及ぼすか

【事例】
X弁護士は、ある日の会食で飲酒をし、その後帰宅する際に自家用車を運転して帰宅してしまいました。
途中、ハンドル操作を誤ったX弁護士は、前方に停車中の車両に衝突してしまい、運転者に全治1週間のけがを負わせてしまいました。
すぐに警察を呼んだのですが、アルコールの匂いがするということで呼気検査が行われ、基準値を上回る数値が計測されたことから、酒気帯び運転の罪で逮捕されることとなりました。
弁護士が酒気帯び運転で逮捕されたということで、このニュースはX弁護士が所属するA県で大きく報道され、A弁護士会の会長が謝罪する事態となりました。
このとき、X弁護士にはどのような処分が科されるのでしょうか。
【解説】
今回のX弁護士の行為は、道路交通法違反(酒気帯び運転)、過失運転致傷罪に該当することになります。もちろん、飲酒の程度や直前の運転行為などから危険運転致傷となる可能性も否定できませんが、今回はひとまず道路交通法違反、過失運転致傷罪ということで検討を進めます。
弁護士の資格と刑事罰に関しては、明確なものとして弁護士法7条1号があります。同号は
第七条 次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者
と定めており、禁錮以上の刑に処せられた者については弁護士となる資格を有しないこととなっています。この条文では、刑の執行の猶予の有無などは問われていません。そのため、仮に執行猶予付きの判決であったとしても、判決確定と同時に弁護士となる資格を喪失することとなります。
たとえ怪我の程度が軽かったとしても、酒気帯びの上での交通事故であれば公判請求の可能性もありますから、弁護士となる資格を喪失する可能性があります。
そこで、何とか交通事故の被害者の方とは示談交渉を行い、宥恕を得られたとします。そうすると、過失運転致傷については不起訴となる可能性が出てきます。
ただ、それでも道路交通法違反については何らかの処罰がなされる可能性が高いと言えます。
酒気帯び運転の初犯の場合には、多くの場合には罰金刑となります。そして、罰金刑自体は、「禁錮以上の刑」ではありませんので、明示的な資格喪失要件ではありません。
しかし、法を守るべき弁護士が法を犯したということ自体が品位を失う非行であると考えられているため、懲戒処分の対象となります。
昨今飲酒運転の撲滅が叫ばれ、公務員であれば一発で懲戒免職となる時代です。そのため、弁護士に対しても厳しい目が向けられていますから、戒告などではなく、業務停止1~3か月程度(事情により期間は前後します)となる可能性が高いと言えます。
飲酒運転で事故を起こしてしまった場合、まずは被害者の方との示談交渉を成立させなければ、弁護士資格自体を喪失してしまいます。ですので、これが最も大切な活動です。
次に、道路交通法違反での処罰をできる限り回避するような弁護活動が必要なところですが、どうしても避けられない場合には、できる限り弁護士会への処分が軽くなるよう、被害者の方からの嘆願書を提出したり、再犯防止のための取り組みを書証化するなどできる限りのことをする必要があります。
このような事態になってしまった場合には、自分で対処しようとするのではなく、専門の弁護士に依頼する方が事態に対する冷静かつ客観的な評価が可能であると思います。このような事態になってしまった場合には、あいち刑事事件総合法律事務所へご連絡下さい。専門の弁護士が相談の対応をさせていただきます。
【弁護士が解説】職務上請求を違法に取得した場合にはどのような処分が予想されるか

【事例】
X弁護士は、なじみの不動産会社から、Yが所有する不動産について、近々再開発の計画があり値上がりする可能性があること、
Y自身についても末期のがんで入院中であり、余命がそう長くないということを聞かされた。
そのため、X弁護士は、不動産会社から依頼されたわけでも、Yから依頼されたわけでもないにも関わらず、Yが住む役所に対して住民票及び戸籍謄本の職務上請求を行った。
その際、目的欄に「相続人確定のための調停申し立てのため」と虚偽の内容を記載した。
【解説】
弁護士を含めた一部の士業には、戸籍や住民票といった個人情報を役所に請求し、取得することが認められています。ただ、これは無制限に認められているわけではなく、あくまでも戸籍法の範疇で認められているにすぎません。
戸籍法で弁護士が戸籍を取得することができるとされているのは、戸籍法10条の2によります。
第十条の二 前条第一項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。
③ 第一項の規定にかかわらず、弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。次項において同じ。)、司法書士(司法書士法人を含む。次項において同じ。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。次項において同じ。)、税理士(税理士法人を含む。次項において同じ。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。次項において同じ。)、弁理士(弁理士法人を含む。次項において同じ。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該業務の種類、当該事件又は事務の依頼者の氏名又は名称及び当該依頼者についての第一項各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。
④ 第一項及び前項の規定にかかわらず、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士又は弁理士は、受任している事件について次に掲げる業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該事件の種類、その業務として代理し又は代理しようとする手続及び戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。
一 弁護士にあつては、裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務(弁護士法人については弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十条の六第一項各号に規定する代理業務を除き、弁護士・外国法事務弁護士共同法人については外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第八十条第一項において準用する弁護士法第三十条の六第一項各号に規定する代理業務を除く。)
⑤ 第一項及び第三項の規定にかかわらず、弁護士は、刑事に関する事件における弁護人としての業務、少年の保護事件若しくは心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第三条に規定する処遇事件における付添人としての業務、逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐人としての業務、人身保護法(昭和二十三年法律第百九十九号)第十四条第二項の規定により裁判所が選任した代理人としての業務、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第十三条第二項及び第三項の規定により裁判長が選任した訴訟代理人としての業務又は民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三十五条第一項に規定する特別代理人としての業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、弁護士の資格、これらの業務の別及び戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。
いずれの場合であっても、弁護士であるからという理由だけで請求が認められているわけではありません。少なくとも受任している事件に関しての請求でなければなりませんし、利用目的を記載しなければなりません。同じような規定は住民基本台帳法12条の3にも存在します。
そのため、たとえ弁護士であったとしても、無制限に戸籍等の請求をしてよいわけではありません。今回のX弁護士の行為は、①誰から受任をした事件でもない点②虚偽の目的を利用目的欄に記載した点に問題があり、本来であれば住民基本台帳法、戸籍法上の取得が認められないような場合であったと言えます。
このような職務上請求の目的外使用は、法を犯すものですから厳しく処分される可能性があります。
今回の事例ではそこまでの記載がありませんが、違法に取得された住民票が第三者に交付されたり、これによって記載されている者らに何らかの損害が発生したような場合には、一層重い処分が予想されます。
単なる目的外取得だけであれば戒告で済む可能性もありますが、別の問題が生じているような場合には業務停止の可能性があります。
今回のような事例の場合、取得されたYらに対して謝罪をするほか、取得するに至った経緯(受任間近であったなど)の事情を説明して、処分の軽減を求めることが考えられます。
【最後に】
弁護士が懲戒請求を受けた場合、弁護士は代理人ではなく紛争の当事者となります。代理人として紛争にあたるのはいつもどおり出来たとしても、当事者として紛争にあたる場合には思った通りの活動が出来ないということはあり得ます。代理人を入れることで、事実をしっかりと整理し、懲戒処分の回避や軽減につながる可能性が上がります。
加えて、勤務弁護士について懲戒請求を受けた場合に、実際に懲戒処分がなされれば事務所全体の評判に関わる可能性があります。当該勤務弁護士について解雇・業務委託契約解除をしたとしても悪影響が払拭できない可能性もあります。
勤務弁護士が懲戒請求を受けている場合も含めて、懲戒請求手続について詳しく、懲戒請求に対する弁護活動経験が豊富な弁護士への相談を検討している先生方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
【弁護士が解説】訴訟上の書面等に不適切な記載をしてしまった場合にどのようにすればよいか

【事例】
X弁護士は、ある夫婦の女性の側から夫との離婚調停を依頼されました。女性曰く、夫は一切家事をせず、家にお金を入れることもなく、普段自分に暴言ばかり吐いている
とのことでした。
X弁護士が聞いていても、女性の境遇はあまりにも不憫であり、離婚をして自由になる方が幸せであろうと思えるほどでした。
そこで、X弁護士が家庭裁判所に離婚調停を申し立てたところ、夫の側から反論の書面が提出されました。
その書面には、妻が行っていることは全てうそであること、自分は妻を愛していること等が滔々と記載されていました。
これを読んで激高したX弁護士は、次の書面で「この夫は人でなしであり、人間の心を持たない化け物である」等と記載した書面を提出した。
【解説】
弁護士職務基本規程第6条によると、「弁護士は、名誉を重んじ、信用を維持するとともに、廉潔を保持し、常に品位を高めるように努める」とされています。
今回のX弁護士の書いた書面は、たとえ夫側の主張が事実に反する虚偽の主張であったとしても、虚偽であることを主張するものではなく、単にその人格を否定する内容となっています。
このような内容の書面は、いくら依頼者のためであるとしても、品位ある書面であるとは言えません。
ただ、さすがに弁護士個人の感情としてあからさまに名誉を毀損し、品位を害する書面を記載することはそれほど多くないと思われます。
実際には、依頼者から感情的な表現をすることを依頼され、弁護士もこれに同情して記載してしまうのではないかと予想されます。
それでも、たとえ依頼者からの依頼であったとしても、最終的には弁護士名義で書面を出すのですから、弁護士としての基本的なルールは遵守する必要があります。
だからと言って、依頼者自身が感情的な表現を記載した文書を、弁護士が証拠として提出することも、不法なものに加担することになりかねませんので注意する必要があります。
ですので、対外的に発出する文書や、証拠については、提出前に一旦見返し、冷静な気持ちで本当に提出してよいものかどうかを考える必要があります。
また、このような事案の場合には弁護士の側に非があることが比較的はっきりしているので、示談交渉を行い、謝罪等をして処分の軽減を目指していくことも考えられます。
【最後に】
弁護士が懲戒請求を受けた場合、弁護士は代理人ではなく紛争の当事者となります。代理人として紛争にあたるのはいつもどおり出来たとしても、当事者として紛争にあたる場合には思った通りの活動が出来ないということはあり得ます。代理人を入れることで、事実をしっかりと整理し、懲戒処分の回避や軽減につながる可能性が上がります。
加えて、勤務弁護士について懲戒請求を受けた場合に、実際に懲戒処分がなされれば事務所全体の評判に関わる可能性があります。当該勤務弁護士について解雇・業務委託契約解除をしたとしても悪影響が払拭できない可能性もあります。
勤務弁護士が懲戒請求を受けている場合も含めて、懲戒請求手続について詳しく、懲戒請求に対する弁護活動経験が豊富な弁護士への相談を検討している先生方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。