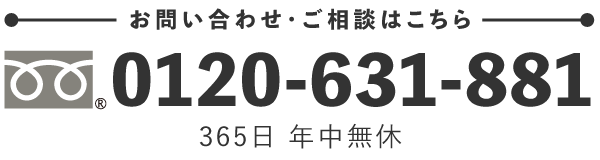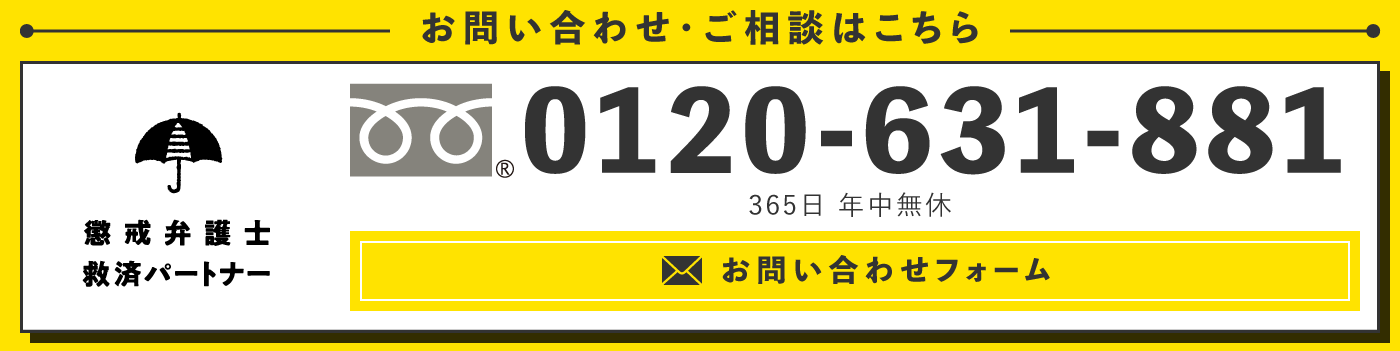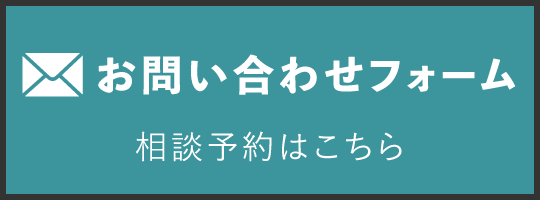Archive for the ‘懲戒手続’ Category
各委員会の判断に対する不服申立て
それでは、ここで各委員会の判断についての不服申し立てについて整理したいと思います。
第1 単位会からスタートする懲戒事件
1 単位会綱紀委員会の判断
⑴事案を懲戒委員会に付するとの判断
対象弁護士は、これに対して不服申し立てを行うことはできません。
⑵事案を懲戒委員会に付さないとの判断
懲戒請求者は、日弁連綱紀委員会に対して異議の申出を行うことができます。
2 単位会懲戒委員会の判断
⑴懲戒処分をするとの判断
対象弁護士は、日弁連懲戒委員会に審査請求を行うことができます。
懲戒請求者は、単位会がした処分が「不当に軽い」と考える場合には、異議申出を行うことができます。
⑵懲戒処分をしないとの判断
懲戒請求者は、日弁連懲戒委員会に異議の申出を行うことができます。
3 日弁連綱紀委員会の判断
単位会綱紀委員会が、事案を懲戒委員会に付さないとした判断に対し、懲戒請求者が異議の申出
を行った場合
⑴異議を棄却・却下する場合
懲戒請求者は、日弁連綱紀審査会に綱紀審査の申出を行うことができます。
⑵異議に理由があると考える場合
この場合、日弁連綱紀委員会は、自ら対象弁護士を処分することはせず、事案を単位会懲戒委員会に送る決定をします。この場合、単位会綱紀委員会の「事案を懲戒委員会に付さない」とした判断が取り消され、単位会懲戒委員会に事案が送られるということになりますので、この決定に対して対象弁護士が不服申し立てを行うことはできないと考えられます。
4 日弁連懲戒委員会の判断
⑴対象弁護士が、単位会懲戒委員会が行った懲戒処分に対して審査請求をした場合
ア 審査請求棄却・却下の場合
この場合、対象弁護士は東京高等裁判所に対して処分の取消しを求める行政訴訟を提起することができます。
イ 審査請求に理由がある場合
審査請求を認め、対象弁護士を懲戒しないとした判断に対しては、懲戒請求者は不服申立てできません。
審査請求を認め、対象弁護士の処分を軽くする場合には、対象弁護士は処分されている状態なので、行政訴訟を提起できます。また、処分が軽くなったことに対しては、懲戒請求者は不服申し立てを吸うrことはできません。
⑵懲戒請求者が、単位会懲戒委員会が行った、懲戒処分をしないという決議に対して異議申出をした場合
ア 異議申出を棄却・却下する場合
このとき、懲戒請求者に対して「綱紀審査」手続きは認められていません。
また、懲戒請求者が訴訟提起をして処分を求めることも認められていません。
イ 異議に理由があると考える場合
この場合、対象弁護士に対して何らかの処分を行うことになります。なお、弁護士法64条の5の規定により、日弁連懲戒委員会は、事案を単位会に差し戻すことはできません。
日弁連懲戒委員会が行った懲戒処分に対しては、対象弁護士は行政訴訟を提起することができます。
⑶懲戒請求者が、単位会懲戒委員会が行った懲戒処分が不当に軽いという理由で異議申出をした場合
ア 異議申出を棄却・却下する場合
この場合も、綱紀審査のような手続きはなく、行政訴訟もできません。
イ 異議申出に理由がある場合
この場合、日弁連懲戒委員会は、処分を変更し、自ら重い処分を行うことになります。
処分を重く変更された対象弁護士は、行政訴訟を提起することができます。
第2 日弁連による懲戒
1 日弁連綱紀委員会の判断
⑴事案を日弁連懲戒委員会に付するとの判断
対象弁護士はこれに対して不服申し立てを行うことはできません。
⑵事案を日弁連懲戒委員会に付さないとの判断
日弁連綱紀委員会が原審として調査を行うのは、「日弁連」が懲戒の事由があると判断した場合に限られます。
一般の懲戒請求者が懲戒請求を行うことができるのは、弁護士又は弁護士法人の「所属弁護士会」に限られますので、
一般の懲戒請求者が日弁連に懲戒請求を行うことはできません。
そのため、事案を懲戒委員会に付さないとした判断に、日弁連自身が拘束されますので、不服申し立てをされることはありません。
2 日弁連懲戒委員会の判断
⑴懲戒処分をするの判断
これに対しては、対象弁護士は行政訴訟を提起することができます。
⑵懲戒処分をしないとの判断
1⑵と同じで、日弁連自身が拘束される以上、これに対して不服申し立てをされることはありません。
懲戒委員会④
1 懲戒委員会の議決
懲戒委員会では、審査後議決を行います。
議決の種類は除名、退会命令、業務停止、戒告、懲戒しないのいずれか(対象弁護士の死亡、資格喪失を除く)となり、業務停止の場合には、併せてその期間を定めることとなります。
弁護士法には議決のための定足数などの決まりはないものの、実際には単位会の会則によって
定足数などが決められています。なお、日弁連懲戒委員会では、委員の半数以上の出席がなければ
会議を開くことができません。また、出席者の過半数で決議されることとなっていますので、除名などの場合だけ要件が加重されているということはありません。
2 議決後
懲戒委員会の決議は、弁護士会・会長を拘束するため、弁護士会は速やかに対象弁護を懲戒する(もしくはしない)こととなります。
懲戒をする場合には、書面によりその処分の内容と理由を通知することになっており、実際上は「懲戒書」が作成されることとなります。
この懲戒書を、本人に言い渡す必要があるのか、書面で郵送すれば足りるのかについては、各単位会毎に定めがあり、異なるようです。ただ、言い渡しが必要であっても、言渡し期日さえ対象弁護士に伝えれば、当日不出頭でも言い渡しは可能と考えられているため、不出頭でも効力は生じます。
反対に、懲戒をしない場合には、懲戒請求者にその旨と理由を通知するほか、対象弁護士にも通知することとなります。この際、懲戒請求者には議決書の謄本を添付して通知し、対象弁護士に対しても議決書の謄本が交付されることが多いと思われます。
3 不服申立て
単位会が行った懲戒処分をするという決定に対して、対象弁護士は日弁連懲戒委員会に対して審査請求を行うことができます(弁護士法59条)。
反対に、単位会懲戒委員会が、懲戒をしないとした決定に対しては、日弁連懲戒委員会に対して異議の申出を行うことができます(弁護士法64条の5)
【弁護士が解説】職務上請求書で取得した相手方の住民票を依頼者に交付してよいか
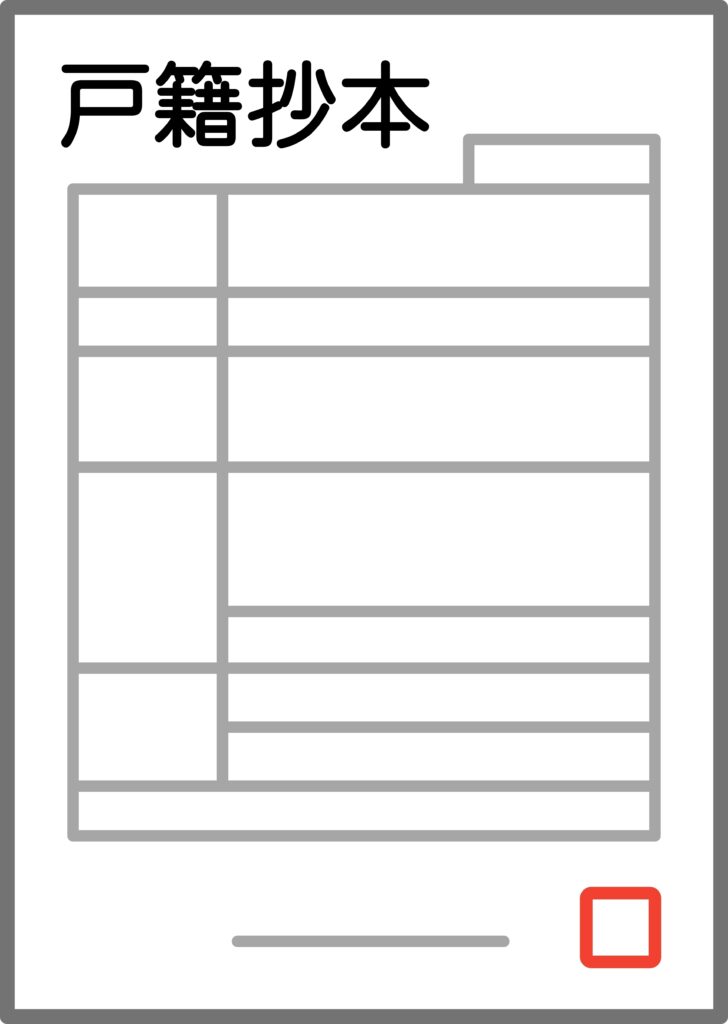
【事例】
X弁護士は、Aから依頼を受けた相続をめぐる事件に関し、調停を申し立てるために他の相続人Bの住民票を職務上請求用紙を用いて取得した。
そのことをXがAに言うと、Aは「長らく音信不通だったBがどこに住んでいるのか知りたいので、先生その住民票もらえませんか?」と依頼してきた。
XはAに住民票を交付してよいのだろうか。
【解説】
1 規則について
弁護士が、弁護士である地位に基づいて住民票等を取得できるのは、戸籍法や住民基本台帳法にその定めが存在するからです。
ただ、実際に弁護士が住民票等を職務上請求する際には、日弁連が定める規則等に従う必要があります。
日弁連では「戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則」を定めています。それ以外に、単位会でも実際の購入方法などを定めた規則が定められている例が多いものと思われます。
ただ、これらの規則でも、おそらくは取得した戸籍謄本や住民票についてどのような取扱いをするかについては定めがないものと思われます。
2 守秘義務
戸籍や住民票の記載事項は、本来であれば記載されている者や直系親族などでなければ見ることができないものです。
そうすると、これらの記載内容を第三者に漏らすことは、弁護士の「守秘義務」の関係で問題があるのではないかという問題が生じます。
弁護士法23条では、「弁護士(中略)は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。」とされており、弁護士職務基本規程23条でも「弁護士は、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は利用してはならない。」とされています。
特に弁護士職務基本規程では「依頼者について」という文言がある関係で、弁護士法23条の主義ヒムについても、今回のBのような「第三者」については守秘義務の対象外ではないのではないかとの解釈も成り立ちうるところです。しかし、日弁連綱紀委員会では「守秘義務の対象・範囲は、依頼者はもとより第三者の秘密やプライバシーにも及ぶことでは当然とされている」と判断しており、第三者の秘密も守秘義務の対象であると考えられています。
今回のBの住民票についても、通常であれば他人が見られるようなものではないため、秘密に該当します。そのため、職務上請求で取得したBの住民票をAに交付することは守秘義務違反に該当する可能性があります。特に、B以外の家族の名前などが同じ住民票に記載されている場合、違反となる可能性は一層高まります。
もっとも、調停申立書には当然Bの住所を記載します。そのため、調停申立書の写し等をBに交付すると、Bの住所をAに知られることになります。このことの是非も当然問題となります。
これまでのAの言動などからして、仮にBの住所を教えてしまうと、Aが直接押しかけたり郵便を送るなどして問題が生じる可能性があると感じられるのであれば、住所をマスキングするなどして交付したほうが安全であると言えます。
少なくとも、今回のケースで取得した住民票そのものを交付することは極めて危険であり、差し控えるべきであると言えます。
【弁護士が解説】薬剤師が交通事故を起こすとどのような処分が待っているか②

【事例】
薬剤師の資格を持ち、ある病院で勤務しているAさんは、ある日通勤途中、自家用車を運転している際に前方の車に追突してしまいました。
Aさんはすぐに110番と119番をしたのですが、前方の車に乗っていたBさんが全治1週間程度のけがをしてしまったようでう。
Bさんが診断書を出したことにより、Aさんに対する過失運転致傷罪の捜査が開始しました。
このあとAさんにはどのような処分が待っているのでしょうか。
【解説】
前回に引き続き、今回は薬剤師免許に対する行政処分について解説していきます。
まず、薬剤師法8条により、行政処分は免許の取消し・3年以内の業務停止・戒告の3種類と定められています。ですので、処分を受ける場合にはこのいずれかの処分となります。
ただ、仮に薬剤師が刑事罰を受けた場合であっても、薬剤師法8条が「薬剤師が、第五条各号のいずれかに該当し、又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。」と定めており、必ず処分をされるわけではありません。たとえば、弁護士法7条は「次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。一 禁錮以上の刑に処せられた者」としており、禁錮以上の刑(執行猶予付きも含む)を受けてしまうと、どのような理由であれ弁護士となる資格を喪失することになっていますので、違いが分かるのではないかと思います。
次にどのような手続で処分を行うかです。薬剤師法8条を見ると「厚生労働大臣は・・・・」となっています。ですので、最終的な処分は厚生労働大臣名でなされます。このことは薬剤師免許が厚生労働大臣名であることの裏返しです。
ただ、実際には厚生労働大臣が個人で決めているわけではありません。厚生労働省内に医道審議会という審議会が設置されており、そのなかの「薬剤師分科会薬剤師倫理部会」により答申がなされ、それに従って厚生労働大臣が処分をするということになっています。たとえば、直近であれば、準強制わいせつ未遂と傷害罪を起こした薬剤師に関して免許取消となっています。
とはいえ、この医道審議会も東京で開かれているだけですから、全国にいる薬剤師に聞き取りを行えるわけではありません。そのため、薬剤師法8条5項により、都道府県知事が聞き取りを行い、これを厚生労働大臣が行ったことに代えることとされています。しかし、都道府県知事が聞き取りをしているわけではなく、実際には都道府県の担当部局がこれを行うということになっています。
ですので、個々の薬剤師の方には、都道府県の医政担当部局から呼び出しがあり、そこで聴聞という手続きが開かれ、その内容が知事→医道審議会→大臣と上がっていくという仕組みになっています。
今回のような交通事故の場合、どのような処分となるかは「行政処分の考え方」が事前に公表されています。過失運転致傷については、基本的には戒告の取扱いにするとされています(⑹ア)。ただ、情状が軽ければ処分がなされないこともあり得ると思われますし、反対に飲酒運転や危険運転、ひき逃げといった重い場合には処分がより重い処分となることが予想されます。
処分の軽減を図るためには、最初の都道府県への聞き取りへの対応が必須です。むしろ、ここでしか話を聞かれませんので、都道府県での対応が鍵となります。有利な処分を得るためには、まずは刑事事件でより軽い処分を得て、それをもって都道府県の聞き取りに臨む必要がありますので、刑事の段階から処分を目標に示談交渉等を行う必要があります。これらの交渉には難しい点もありますので、まずは弁護士にご相談ください。
【弁護士が解説】薬剤師が交通事故を起こすとどのような処分がなされるのか①

【事例】
薬剤師の資格を持ち、ある病院で勤務しているAさんは、ある日通勤途中、自家用車を運転している際に前方の車に追突してしまいました。
Aさんはすぐに110番と119番をしたのですが、前方の車に乗っていたBさんが全治1週間程度のけがをしてしまったようでう。
Bさんが診断書を出したことにより、Aさんに対する過失運転致傷罪の捜査が開始しました。
このあとAさんにはどのような処分が待っているのでしょうか。
【解説】
Aさんは交通事故を起こしてしまいました。このような場合、Aさんにはいろいろな方面から処分がなされます。今回は、どのようなところから何を言われるのかを概観します。
1 刑事
まずは刑事事件です。これは警察が捜査し、その後検察庁に送検され、最終的には懲役・禁錮・罰金といった刑罰を受けるような手続きです。ただし、検察庁が「今回限りは処罰しません」という風に決定した場合には、いわゆる「起訴猶予」となります。
交通事故の場合には、過失運転致傷罪が成立するかが問題となります。
刑事事件では、警察官・検察官とやり取りをすることになります。後から述べる「免許」の手続きでも警察官が出てきますが違う部門の警察官ですし、免許の手続きは免許センターで行われることが多いのに対し、刑事事件で対応する警察官は事故現場を管轄する警察署の警察官となります。
2 民事事件
次に民事事件です。
⑴損害賠償
交通事故を起こした以上、民法709条、自動車損害賠償保障法3条に基づき、加害者は被害者に対して賠償をする義務が生じます。これを「損害賠償」等と呼んでおり、治療費や慰謝料の支払いなどを行います。
ただし、多くの場合は任意保険に入られていると思いますので、そのような場合には保険会社が代わりに賠償をしてくれることになっています。もし任意保険に入っていない場合でも、自賠責保険は強制加入ですから、人身事故に関する損害については、一定額までは自賠責保険会社が対応してくれることになっています。
⑵雇用関係
仮にAさんが民間病院に勤務している場合、勤務先の法人等から交通事故を起こしたことにより何らかの処分を受ける可能性があります。戒告や訓告、けん責、減給、停職、解雇など、処分の種類は様々です。処分の内容については、各法人により異なりますので、就業規則を確認する必要があります。仮にこの処分に不服がある場合には、労働審判や民事訴訟といった法的手段により争うことになりますが、これも民事事件に分類されます。
3 行政事件
最後に行政事件です。
⑴雇用関係
仮にAさんが公立病院に勤務している場合、先ほどの民間病院とは異なる場合があります。
Aさんが公務員の地位を有している場合には、Aさんの労働者の地位に対する処分は「行政処分」となります。
地方公務員の場合、その処分は地方公務員法27,28条で定められています。「降任、免職、休職、降給」と法定されており、それ以外の処分は許されていません。なお、所属によっては「文書注意」や「所属長注意」というような注意がなされることもありますが、これは法律の定める処分ではなく、あくまでも内部的なものということになります。
⑵運転免許に対する処分
交通事故を起こした場合、運転免許の点数が引かれることになります。また、事故態様や累積の点数次第では、免許停止や免許取消の処分を受ける場合もあります。
これらの処分は、各都道府県の公安委員会が行います。運転免許証の右下には各公安委員会の印が押してありますが、反対に処分を行うのも公安委員会となります。ただ、実際には運転免許センターに呼び出され、センターの警察官により対応されるため、実質的には警察官により免許の処理もされているように見えます。
⑶薬剤師免許に対する処分
最後に、薬剤師の国家資格について解説します。
薬剤師の国家資格は、一定の理由があると取り消されるなどの処分を受けることとなっています。
薬剤師法8条がその処分を決めており、取消し、業務停止、戒告の3つの処分が定められています。
薬剤師に対する処分は、法文上厚生労働大臣が処分をすることになっていますが、薬剤師本人の聞き取りを行うのは都道府県の担当部局です(薬剤師法8条5項)。そのため、呼び出しは都道府県からくることになります。
4 まとめ
これまで見てきたように、1つの交通事故を起こすだけで、多数の部門から呼び出し・聞き取り・処分がなされることになります。
このような多方面からの要求に、これまで法律と無縁であった方が対応することは困難だと思われます。
事故を起こしてしまった場合、まずは弁護士に相談し、どのように対応することが適切か、方針を考えましょう。次回は薬剤師免許についての手続きを解説します。
【弁護士が解説】弁護士費用の未精算はどのような問題を生じさせるか
【事例】
X弁護士は、Aさんから交通事故損害賠償事件(被害者側)の依頼を受け、保険会社との交渉に当たり、保険会社から保険金を受領しました。
X弁護士がAさんから依頼を受けた当初、Aさんが被害者であることは明らかであり、それなりまとまった金額を受領できることが予想されたことから、委任契約締結時にはX弁護士は費用を貰わず、保険会社から取得出来た金額に対する一定の割合を報酬として差し引き、残った金額をAさんに渡すという契約を締結していました。
X弁護士は、保険会社との示談交渉が完了し、保険金の受領が終了したにもかかわらず、Aさんに保険金の一部の支払いをしないままでいました。このようなことはどのような問題を生じさせるでしょうか。
【解説】
「自由と正義」の末尾に、懲戒の事例が掲載されていますが、事案のように預かったお金を返金しないというケースは度々登場します。
弁護士職務基本規程45条によれば、「弁護士は、委任の終了に当たり、委任契約に従い、金銭を清算した上、預り金及び預り品を遅滞なく返還しなければならない。」とされています。保険会社からの保険金は、依頼者のために第三者あら預かったお金ですから、預り金に該当し、終了時に速やかに返金する必要があります。
事例のケースのように、保険金や遺産等のまとまったお金を返金しなかった場合、業務停止などの重い処分も十分予想されます。そのため、速やかに返金をする必要があります。
ところで、仮に返金できない何らかの事情が発生した場合はどうでしょうか。たとえば、依頼者から「今、妻と離婚しそうで、このまま自分の口座に保険金が流れ込んでしまうと、この保険金も遺産分割の対象となってしまう可能性がある。そのため、先生がしばらく預かっておいてください」等と言われた場合には、どうすればよいでしょうか。
この依頼者の述べている内容が法的に正確かどうかは別として、返金ができない事情(病気や行方不明など)がない以上、仮に依頼者側に事情があったとしても規程上は返金すべきでしょう。
医師・看護師・薬剤師等の処分とはどのようなものか?

【事例】
Aさんは、車を運転している最中、交通事故を起こしてしまいました。
今後Aさんにはどのような処分が待っているのでしょうか。
【解説】
事故を起こしてしまったAさんには、この後様々な機関からの呼び出し、事情聴取、処分が出されます。それぞれについてどのような違いがあるのかを検討します。
0 大前提
これから、様々な処分について説明していきます。ただ、その前提として1つ重要な問題があります。
それは、「それぞれの世界は、独立した世界である」ということです。この後説明しますが、刑事の世界と民事の世界は別の世界ですし、一致することも多いですが、刑事の世界と民事の世界の認定が同じでなければならないという決まりはありません。ですので、それぞれが別々に来てしまうことも十分あり得ます。
1 運転免許について
まずはなじみ深い運転免許の処分について考えていきます。ここで当てはまることが、基本的にはそのままあてはまります。
⑴点数
交通違反をすると、点数が引かれます。この点数がたまると免許が取り消されたり、停止されたりすることからも分かるように、これは「都道府県公安委員会」という役所が個人(免許の名義人)に対しておこなう「行政処分」です。
なお、免許センターに行けば警察官の服装をした方がいますが、⑵で出てくる警察官とは似ているようで違う存在です。
⑵刑事罰
交通事故を起こし、相手方が負傷すると過失運転致傷罪という犯罪が成立しえます。
警察は事件を捜査し、捜査を終えると「検察庁」という役所に送ります。
そして、検察官が起訴するか不起訴にするかを決定し、起訴されると裁判を受けることになります。
起訴後、裁判官が判決を下すことになりますが、罰金、執行猶予付き懲役・禁錮等、刑事罰を受けると、いわゆる前科がつくことになります。
これがいわゆる「刑事事件」です。
⑶賠償責任
事故で被害者がけがをしたり、相手の車がへこんだような場合には、賠償をする義務があります。
ただ、現在ではほとんどの方が任意保険に入られ、賠償については保険で対応されていると思われます。
この、金銭での賠償等についてのやり取りが「民事事件」です。⑴⑵との違いは、役所が登場せず、個人と個人でのやり取り(ただし保険会社が代理する)になるという点にあります。
⑷まとめ
以上の様に、1つの事故で「行政」「刑事」「民事」の3つの問題が発生します。これを念頭に置いて、今度は免許の方を検討します。
2 資格について
それでは、交通事故を起こしたとして、資格はどうなるのでしょうか。医師、歯科医師、看護師、薬剤師などは基本的には同じですので、ここからは医師を例に解説します。
⑴行政処分
医師などの資格は、基本的には厚生労働大臣から与えられた免許という形をとっています。
反対に、医師の資格を奪うときも、厚生労働大臣による処分という形式をとります。
医師法7条
医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 三年以内の医業の停止
三 免許の取消し
このように、医師に対して、医師という資格自体を左右する処分を与えることができるのは厚生労働大臣に限定されており、これは「行政処分」ということになります。
⑵雇用関係
医師などのうち、多くの方はいずれかの医療機関に雇用されていると思われます。
そうすると、交通事故を起こしたことにより、医師免許自体に関わらず、職場を追われる可能性があります。
ただ、これがどのような事件となるかは、現在どのような医療機関に勤務しているかにより異なります。
たとえば、市民病院のような国立・公立の病院の場合、任命権者が市長などの首長になっていることがあります。そうすると、反対にクビ(免職と呼びます)にする場合も首長がクビにすることになりますから、「役所」が対立当事者として登場するので、「行政処分」となります。
これに対して、民間の病院に勤務している場合、理事長・院長であってもあくまでも「民間人」ですから、こちらは個人と個人の間の問題となりますので「民事事件」になります。
3 事件の種類
このように、民事、刑事、行政と様々な種類の手続きが登場するケースがあります。
この場合、それぞれの事件ごとに、手続のルールが異なり、結論が異なる場合もあります。
そのため、争うことを検討されるような場合には、予め専門家に相談し、何をどのように争えるのか検討しておくことが肝要です。
【弁護士が解説】会社の顧問弁護士をしているときに、会社の役員・従業員とはどのような関係になるのか

【事例】
X弁護士は、長年にわたり株式会社Aの顧問弁護士を務めてきており、代表取締役を含む役員らの日常の相談や、会社の経営等について相談に乗ってきた。
⑴役員パターン
しかし、あるとき、会社役員と株主の間に深刻な利害対立が生じ、役員らは株主代表訴訟を提起されるに至った。
そのため、役員らは訴訟代理人を選任する必要が生じたが、これに普段から会社のことをよく知っているX 弁護士が適任ではないかという話が持ち上がった。
⑵従業員パターン
あるとき、従業員のBが逮捕されたという報道がなされた。A社としても早急に対応する必要があったことから、X弁護士に依頼し、Bに面会してもらうこととした。
話を聞いたA社幹部らは、Bのことを思い、このままXにBの弁護人になってもらうことを考えた。
X弁護士として、これらの依頼を受任しても問題はないか。
【解説】
会社の顧問弁護士を務めている場合、弁護士職務基本規程28条2号の「継続的な法律事務の提供を約している」状態にあるということができます。そのため、「会社」を相手方とする事件を受けることは、同号に該当し、同条但書の場合(依頼者・相手方の双方の同意がある場合)を除いては、職務を行ってはならないことになります。
⑴のようなケースの場合、株主代表訴訟の役員側代理人を務めることは、仮に株主=会社であると考えると問題が生じるということになります。たしかに、株主代表訴訟は、個々の株主の直接的利益を満たすものではなく、あくまでも会社の利益を保護するための制度です。その訴訟において、役員側の代理人となることは、会社を相手方にしているのと同じ状況になりますので許されるものではありません。
しかし、会社法849条により、会社は役員側に訴訟参加することが許されています。そうすると、株主対会社・役員という構図の場合もあり得ますので、このような場合には役員の代理人となることが許されるのではないかという疑問もあります。これについては、『解説 弁護士職務基本規程(第3版)』では消極的な見解が取られています。このケースでも会社の代理人となることは問題ないものの、役員の代理人となることは利益相反の可能性が消滅しないとしています。ですので、受任を差し控える方が良いものと思われます。
⑵のケースの場合、会社が依頼者となり、従業員を弁護するというものです。従業員の起こした事件の内容が会社と全く関係ないのであれば、従業員と会社の間には何らの関係もないように思われます。
しかし、弁護士は弁護士法上の守秘義務を負っていますので、逮捕された従業員から聴取した事項については、本人が同意しない限り会社関係者に告げることができません。対して、会社から顧問弁護士として従業員の処遇について尋ねられた場合には、会社の立場から検討してしまうことになります。こうなると公平性を疑わせる状況になりますので、場合によっては問題化する可能性があります。やはり、知り合いの弁護士に依頼するなどした方が妥当であると思われます。
懲戒手続が開始された場合、どのように対応しなければならないか

【事例】
ある日、X弁護士が事務所にいると、弁護士会から書留で書類が送られてきました。
中身を見ると、元依頼者から懲戒請求を受けたため、答弁書を提出するように依頼する弁護士会の綱紀委員会の書類が入っていました。
X弁護士はどのように対応すればよいのでしょうか。
【解説】
弁護士法58条によれば、何人も懲戒請求ができる旨が記載されています。ただ、懲戒請求は必ずしも私人により開始されるわけではなく、検察庁や裁判所によって請求されることもあるほか、単位会自体が懲戒請求を行う「会立件」という形式も存在します。検察庁、裁判所の請求や、会立件の場合には事前に何らかの問題が生じていますので、自分自身でも何となく請求されることが予想できるところですが、私人による懲戒請求の場合にはいきなり請求がなされるケースが多いのではないかと思われます。以下では私人による請求のケースを念頭に置いていきます。
弁護士会に懲戒請求がなされると、大量請求事件のように明らかに理由がないような場合を除いて全て単位会綱紀委員会に事件が係属します。そして、綱紀委員会から対象弁護士に対して答弁書の提出を求める書類が届きます。
おおよその感覚ですが、懲戒請求書が弁護士の手元に届いたときから約1ヶ月後くらいが答弁書の提出期限とされていることが多いように思われます。そのため、答弁書の提出までの期間にはそれほど猶予がないと言えます。
綱紀委員会に答弁書を提出すると、場合によっては綱紀委員会から追加の書類の提出を求められることがあります。なお、委員会は様々なことを求めてきますが、おそらく多くの単位会の会則で、求めに応じることを義務とする規定が存在すると思われます。そのため、綱紀委員会から提出を求められたものを提出しないことは、正当な理由がない限り別途会則違反の事由を構成することになります。
物件の提出の後、綱紀委員会から呼び出しを受け、直接聞き取りを受ける機会があります。このとき、大規模会では綱紀委員会の委員のうちの一部(2名が多いです)から聞き取りを受けます。
この聴き取りの後、綱紀委員会(大規模会では綱紀委員会内の部会となります)で議決がなされます。
綱紀委員会は、あくまでも前段階の審査機関ですので、結論は事案を懲戒委員会に付するか、付さないかのいずれかとなります。綱紀委員会で懲戒処分を決定するものではありません。
ですので、懲戒請求を受けた弁護士としては、まずは答弁書の作成に取り組むことになります。ただ、多くの弁護士にとって初めて作成する答弁書であると思いますので、どのように作成してよいのか分からない点もあると思われます。そのため、懲戒請求書が送られてきた方は、一度第三者に相談していただくのが適切であろうと思われます。
【弁護士が解説】依頼者からの要求は何でもするべきか、その危険性について解説

【事例】
X弁護士は、ある夫婦の妻Aから相談を受け、自身の夫であるBが浮気をしているので何かできることはないかと尋ねられた。
Aが持参してきた調査会社の報告書や、LINEの履歴などから見て、確かにBが不貞行為をしていることとはほとんど確実であると考えたXは、Aに対して離婚や慰謝料の請求を行うことができる旨を説明した。
しかし、Aとしてはそのようなことではとても収まりがつかず、Bの生活をめちゃくちゃにしてやりたいという希望があった。そのためAはXに対し、「あいつのことは絶対に許せない。今の生活ができないようにしてやりたいので、Bの実家や職場に先生から不貞慰謝料請求の内容証明郵便を出してもらいたい」と告げた。
Xはこのようなことに応じてよいだろうか。
【解説】
XにとってAは依頼者となりますので、弁護士職務基本規程第22条の「弁護士は、委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務を行うものとする。」という規律が当てはまります。そのため、Aが希望することについては基本的にその意思を尊重すべきであると言えます。
しかし反面、弁護士である以上、「弁護士は、事件の受任及び処理に当たり、自由かつ独立の立場を保持するように努める。」(同20条)、「弁護士は、良心に従い、依頼者の権利及び正当な利益を実現するように努める。」(同21条)、「弁護士は、名誉を重んじ、信用を維持するとともに、廉潔を保持し、常に品位を高めるように努める。」(同7条)などの規程も定められています。そのため、たとえ依頼者の希望であったとしても、何でもそのまま行ってよいということにはなりません。
今回の事例で考えると、不貞行為をしているということは通常人に知られたくないものであることは間違いありません。また、公になっているようなもでもないですので、いわゆる「秘密」に属することは明らかです。このような秘密について、第三者に口外することは当然守秘義務との関係で問題となります。弁護士職務基本規程23条の秘密保持義務は「依頼者について」の秘密と限定しているものの、弁護士法23条の守秘義務にはそのような限定はありません。この弁護士法23条の守秘義務については、依頼者の秘密に限定されるのか第三者のものも含むのか争いがありますが、日弁連では第三者のものも含むと解釈しています。そのため、今回の事例と同様のケースで、相手方勤務先に離婚事件に関する事実をメールで送信したような事案で弁護士法上の守秘義務違反を認めたケースがあります。
不貞行為があった場合、法的権利として認められるのは離婚や慰謝料の請求が基本的なものです。相手方配偶者の生活環境を破壊するということは、正当な利益ということはできないと考えられますので、これを実現することは、守秘義務違反の問題は別としても基本規程21条や7条の問題を生じさせます。ですので、X弁護士としてはAの依頼を断るべきですし、これで信頼関係が破壊されるようであれば委任契約の解約をする事案ということになります。
今回の事例では、Bの連絡先などが確実に分かっていると言えるケースでしたので、勤務先や実家に連絡をすることが問題となるケースでした。ただ、今回の事例とは異なり、Bの連絡先が勤務先や実家以外全く分からないということは十分あり得ます。そのような場合、弁護士から連絡をすることはやむを得ない場合も存在すると思われます。ただ、そのような場合であっても、事件の内容や弁護士の主張を過度に記載するなどした場合にはやはり同様の問題が生じると思われますので、「連絡が欲しい」程度の簡単な記載に留めるべきであろうと思われます。
« Older Entries