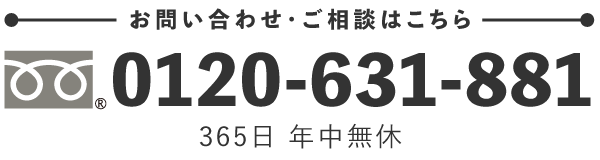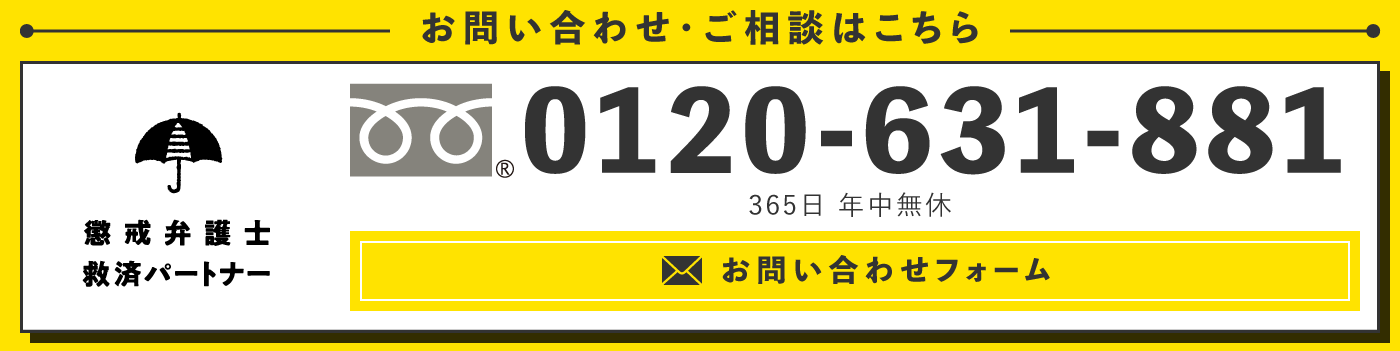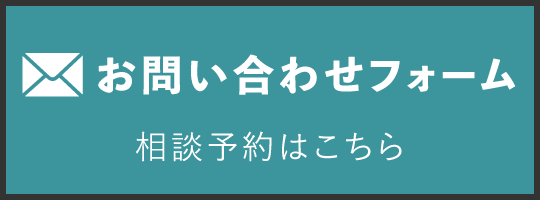このページの目次
1 事案の概要
元々の事案は、信用組合が個人に対し、約束手形に基づいて金銭の請求をした事件でした。
第1審は原告(信用組合)の勝訴、控訴審は第1審被告(個人)の勝訴でした。
この控訴審までは、弁護士の資格について特に争われた形跡はありません(手形の振り出しなどが問題となっていました)。
この控訴審判決について、第1審原告(信用組合)が上告しました。
ところで、この事件の第1審判決期日は昭和38年11月7日、控訴審判決期日は昭和40年2月16日で、その間に控訴審の訴訟手続きが行われています。
第1審被告の控訴審での代理人弁護士は、昭和39年3月18日に弁護士会で業務停止3月の懲戒処分を受けているところでしたが、昭和39年4月15日、控訴審における口頭弁論期日が開かれていました。
この口頭弁論期日での訴訟行為につき、上告人(信用組合)代理人弁護士が、無効な弁論であると主張して絶対的上告理由がある旨を主張しました。
(最判昭和42年9月27日の事例)
2 判旨
「裁判所が右の事実〔注:業務停止の事実〕を知らず、訴訟代理人としての資格に欠けるところがないと誤認したために、右弁護士を訴訟手続から排除することなく、その違法な訴訟行為を看過した場合において、当該訴訟行為の効力が右の瑕疵によつてどのような影響を受けるかは自ら別個の問題であつて、当裁判所は、右の瑕疵は、当該訴訟行為を直ちに無効ならしめるものではないと解する。いうまでもなく、業務停止の懲戒を受けた弁護士が、その処分を無視し、訴訟代理人として、あえて法廷活動をするがごときは、弁護士倫理にもとり、弁護士会の秩序をみだるものではあるが、これについては、所属弁護士会または日弁連による自主・自律的な適切な処置がとられるべきであり、これを理由として、その訴訟行為の効力を否定し、これを無効とすべきではない。けだし、弁護士に対する業務停止という懲戒処分は、弁護士としての身分または資格そのものまで剥奪するものではなく、したがつて、その訴訟行為を、直ちに非弁護士の訴訟行為たらしめるわけではないのみならず、このような場合には、訴訟関係者の利害についてはもちろん、さらに進んで、広く訴訟経済・裁判の安定という公共的な見地からの配慮を欠くことができないからである。」「本件を検討するに、一件記録によれば、弁護士Aが原審において被上告人の訴訟代理人として引き続き訴訟行為をしたこと、しかも裁判所が同人の訴訟関与を禁止した事実のないことがうかがわれるのであつて、同人に対し、所論のような懲戒がされ、しかもその処分が前示のようにすでにその効力を生じていたとしても、以上述べた理由により、同人が原審でした訴訟行為が無効となるものではない」
3 解説
本判決は、訴訟経済等の理由から、業務停止中の弁護士の訴訟行為を有効と取り扱いました。
なお、本判決中でも指摘されていますが、訴訟行為が有効であるからといって、その行為に何らの問題もないというわけではなく、この行為自体も再び懲戒の事由となります。
ですので、業務停止を受けた弁護士としては、速やかに辞任等の措置をとる必要があります。