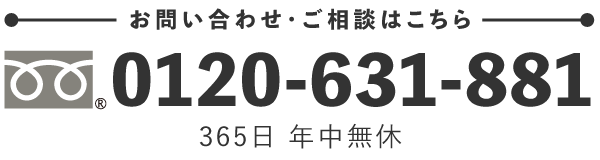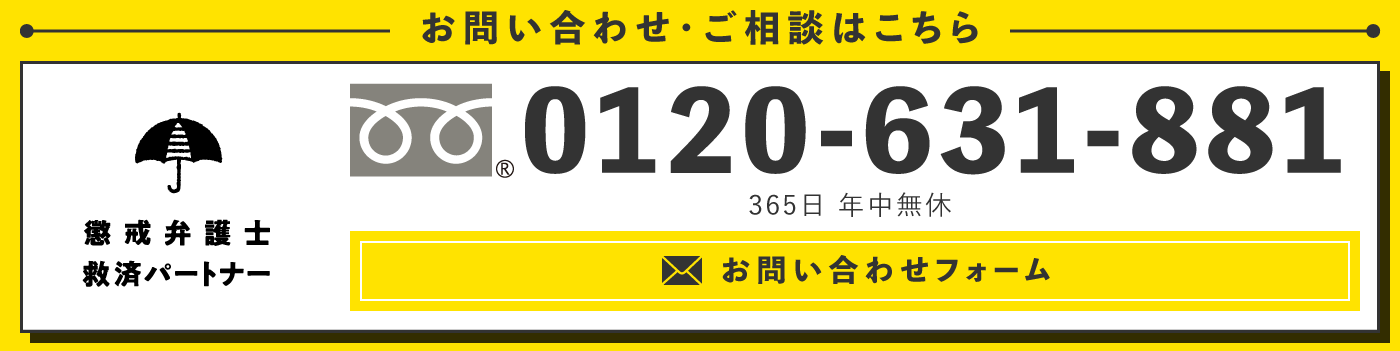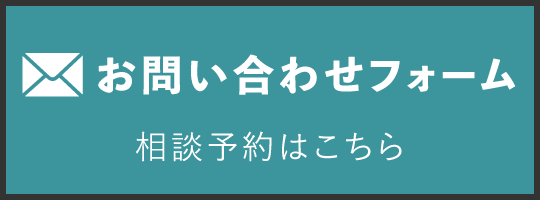このページの目次
1 事案の概要
X弁護士は、生前Aと共に遺言の作成を行った。その遺言の内容は、Xが遺言執行者になることの他、Aの財産を全てBに相続させる旨が記載されていた。
なお、BはXの息子の妻であり、息子はXより先に死亡していたため、AはBを養子としていた。
また、Aにはほかの相続人のとして、Aの娘Cらの他、AとBの間の子ども(代襲相続人)が存在した。
Aが死亡した後、その財産全てをBが相続することとなったが、これに対してCが遺留分減殺の請求を行った。
Cが家庭裁判所に対し、Bを相手方として遺留分減殺請求調停を申し立てると、Bの代理人としてXが就任した。
このXが訴訟行為を行うことについて、①遺言執行者という立場と②特定の相続人の代理人という立場が、利益相反とならないかが問題となった。
(東京高判平成15年4月24日の事例)
2 判旨
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の権利義務を有し(民法一〇一二条)、遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない(同一〇一三条)。すなわち、遺言執行者がある場合には、相続財産の管理処分権は遺言執行者にゆだねられ、遺言執行者は善良なる管理者の注意をもって、その事務を処理しなければならない。したがって、遺言執行者の上記のような地位・権限からすれば、遺言執行者は、特定の相続人ないし受遺者の立場に偏することなく、中立的立場でその任務を遂行することが期待されているのであり、遺言執行者が弁護士である場合に、当該相続財産を巡る相続人間の紛争について、特定の相続人の代理人となって訴訟活動をするようなことは、その任務の遂行の中立公正を疑わせるものであるから、厳に慎まなければならない。弁護士倫理二六条二号は、弁護士が職務を行い得ない事件として、「受任している事件と利害相反する事件」を掲げているが、弁護士である遺言執行者が、当該相続財産を巡る相続人間の紛争につき特定の相続人の代理人となることは、中立的立場であるべき遺言執行者の任務と相反するものであるから、受任している事件(遺言執行事務)と利害相反する事件を受任したものとして、上記規定に違反するといわなければならない。
3 解説
遺言執行者をめぐる利益相反の問題については、多数の懲戒事例、裁判例があり、その判断については事例ごとの判断となります。
上記のような判旨と異なり、遺言の内容によっては「遺言執行者と遺留分減殺請求調停事件の申立人である相続人との間に職務基本規程57条にいう利益相反の関係が存するかについては、具体的事案に即して実質的に判断すべきところ、本件公正証書遺言では、その内容からして遺言執行者に裁量の余地はなく、遺言執行者の職務に同規定57条が適用または類推適用されるとしても、本件では弁護士である遺言執行者と懲戒瀬給者を含む各相続人との間に実質的に見て利益相反の関係は認められない」とした例(日弁連懲戒委員会平成22年5月10日議決)もあり、遺言の実質的な内容についても判断が変わる旨が示唆されています。
上記の東京高裁の事例では、平成22年議決のような視点なく、利益相反に該当する旨が認定されて今うので、このような危険性が存在することは常に意識をしておかなければなりません。