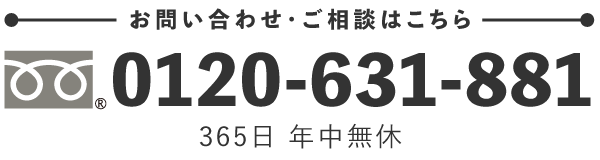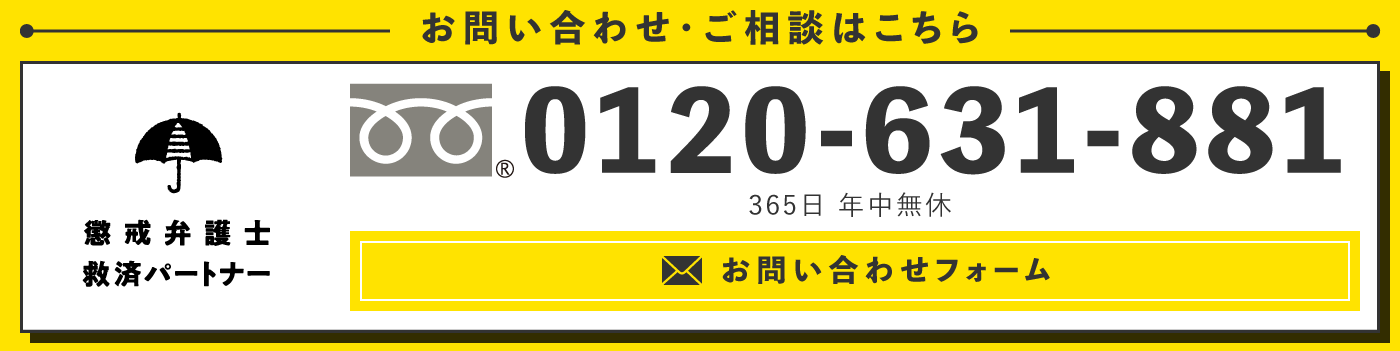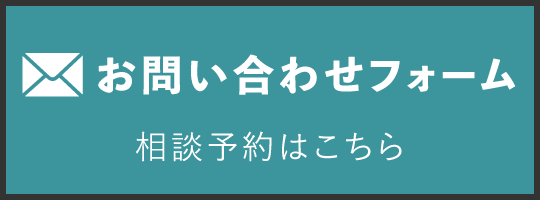Archive for the ‘未分類’ Category
【弁護士が解説】医師の資格と刑法犯

【事例】
医師であるAさんは、職場外で
①盗撮をして現行犯逮捕されました
②万引きで検挙されました
それぞれの場合、Aさんの医師免許にはどのような影響があるのでしょうか。
【解説】
1 医師の資格の欠格事由
医師法7条は、「医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。」としています。そこで、4条を見ると、「三 罰金以上の刑に処せられた者」と書かれています。
そのため、医師免許を保有している者が、罰金以上の刑(これは、医業に関する罪で罰金以上の刑を受けた場合に限りません)を受けた場合には、医師免許取消や医業停止の処分を受ける可能性があります。
2 各事例の検討
①盗撮のケース
盗撮事件で現行犯逮捕されると、多くの場合報道がなされます。また、医師等の職業の場合には、その肩書も併せて報道されるケースが多くなっています。
余程悪質な場合等を除き、盗撮事件であり、前科前歴がなければ逮捕後2日程度で釈放されることが多いと言えます。しかし、後から述べる万引きと異なり、盗撮の場合には初犯であっても罰金刑となってしまいます。
被害者の方と示談をすることができれば、初犯であれば不起訴処分となることもあり得ますが、余罪が多数あるなどのケースでは、示談をしても罰金となることもあります。
盗撮(従前は迷惑防止条例違反でしたが、現在は性的姿態等撮影罪と呼ばれています)で刑事罰を受けた場合、多くの医師が業務停止の処分を受けています。ただ、職場内で盗撮した事件の方がより重いと考えられるので、具体的な月数については、その内容で判断されていると思われます。
②万引きのケース
万引きは、初犯であれば必ずしも現行犯逮捕されることは多くありません。
また、初犯であれば、被害店舗に支払いを行うこと等により、微罪処分・不起訴処分という、罰を受けない処分となることが多いと言えます。ただ、これもケースによる他、被害金額が大きいとそのようなことは当てはまりません。
そのため、万引きでいきなり処分を受けるという可能性はあまり高くないと言えますが、報道等をされてしまうとこの限りではありませんので、注意が必要です。
いずれにしても、犯罪をしてしまった場合、速やかに弁護士に相談し、今後の見通しや、取り得る策を講じたうえで、医師免許への影響を最大限小さくする必要があります。まずは弁護士にご相談ください。
【弁護士が解説】社会福祉士が交通事故を起こすとどうなるか

【事例】
社会福祉士であるAさんは、ある日通勤途中、自動車で交通事故を起こしてしまいました。
幸い被害者の方は全治2週間程度のけがではあったものの、警察の方からは事件を検察庁に送ると言われました。
Aさんはどのような刑事罰を受け、それによって介護福祉士の資格はどうなるのでしょうか。
【解説】
⑴欠格事由
国家資格が何らかの制限(剥奪されたり、効力が一時停止したり)を受けることになる事由のことを「欠格事由」と呼んでいます。欠格事由は、資格を取得するときに問題となっていますが、同様の事由が生じた場合には資格を取消すということになっています。
そして、社会福祉士についての欠格事由を定めているのは、社会福祉士及び介護福祉士法3条です。
(欠格事由)
第三条次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。
一 心身の故障により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三 この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四 第三十二条第一項第二号又は第二項(これらの規定を第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
これが欠格事由になります。全部で4つ欠格事由が定められています。
1は規則に細かい規定があり、「精神の機能の障害により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」とされています。
2が今回問題となる規定ですので後述します。
3は、同じ刑事罰でも福祉関係の法令に違反した場合です。2が「禁錮以上」となっているのに対し、3は「罰金」となっています。罰金の方が軽い刑罰ですので、福祉関係の法令に違反した場合にはより軽い刑事罰でも欠格事由となります。
4は一度欠格事由があって資格を取消された場合の規定です。仮に欠格事由が生じたとしても試験に合格した事実自体は残りますので、形式的には再度登録できるように思われます。しかし、この規程によって2年間は再登録ができないようになっています。
⑵刑事罰と国家資格
さて、それは本題の刑事罰を受けた場合の資格について検討します。
2号で「禁錮以上の刑」と定められています。刑事罰の重さは死刑>懲役>禁錮>罰金>拘留>科料と定められていますので、禁錮以上の刑は死刑・懲役刑・禁錮刑を指します。反対から言えば、罰金刑であればこの規定に該当しないことになります。つまり、交通事故によって罰金刑を受けた場合や当然ですが不起訴処分になった場合には、資格を取消されたりすることはないということになります。
それでは禁錮刑を受け、その刑に執行猶予が付けられた場合はどうでしょうか。
執行猶予とは、裁判が確定した後すぐに刑務所等に収容されるのではなく、執行猶予期間中無事に過ごせば収容されないという判決です。反面、執行猶予中に再び裁判を受けるようなことがあれば、基本的には刑務所に行かなければならない(もう一度執行猶予になることはほとんどない)という判決です。たとえば「禁錮1年執行猶予3年」という判決の場合、「もし3年間何もせずに過ごすことができれば、刑務所にはいかなく構いません。ただし、3年以内に再び裁判を受けるようなことがあれば、新しく犯した罪の刑罰に、追加して1年刑務所に入ってもらいます」という意味になります。
話を戻すと、交通事故で人をけがさせた場合、余程重大な事情(前科があるとか、飲酒運転であるなど)がない限りは執行猶予がつくことがほとんどです。しかし、先ほどの欠格事由の条文には執行猶予を除外する規程はありませんから、仮に執行猶予がついたとしても資格は取り消されることになります。
交通事故は誰でも起こしてしまう可能性があるものですが、一つ間違えると運転免許以外の資格さえ剥奪されてしまうものになります。これを回避するためには初動の対応が重要です。資格のことでご不安な方は、いち早く弁護士にご相談ください。
【弁護士が解説】懲戒手続が開始された場合にはどのように対応するべきか

【事例】
X弁護士は、過去の依頼者とのトラブルから、所属する弁護士会に懲戒請求がなされました。
この後どのような手続となるのでしょうか。
【解説】
懲戒請求を受けた場合、懲戒請求書に相当する書面が事務所に送られてきます(配達証明郵便などが用いられます)。
その中には、懲戒請求を受けたことが記載されているほか、代理人選任権等の一般的な防御権の説明が記載されています。
そして、期日(おおよそ1ヶ月後の日程が指定されていることが多いと思われます)までに答弁書等を提出できることが書かれています。
そのため、まず検討しなければならないことは、答弁書の作成ということになります。
答弁書を提出すると、綱紀委員会からさらに追加で資料請求を受けることがあるほか、最終的には委員会から直接聞き取りを受ける機会が設けられることが多いと思われます。ですので、次に考えることはこの聞き取りの機会への対応ということになります。
ここまで終われば対象弁護士への手続きは終了となりますが、綱紀委員会で最終的な結論が出されるためにはなお時間を要します。
そして、ある程度の時間が経過した後、綱紀委員会からは「事案を懲戒委員会に付するか、それとも付さないか」という結論が出されます。この結論についての書面も、事務所に郵送されます。
ただ、ここで出される結論は、あくまでも「懲戒委員会に付するか」ということのみです。ですので、最終的に懲戒処分を受けるような事案であっても、ここで結論が出されるわけではありません。
このように、綱紀委員会内の手続きだけでも、かなりの時間を要します。しかし、対象弁護士が行える書類の提出などの期限は、手続の極めて早い段階に限定されており、十分検討しないまま書面を出してしまうと、後々の手続きに響いてしまうことも珍しくありません。
そのため、懲戒請求を受けた場合には、第三者の弁護士の意見を聞くなどして、備えることが必要です。
【弁護士が解説】弁護士会からの照会に応じなければならないか

【事例】
X弁護士は、自身の過去の依頼者から懲戒請求を出され、現在事件が綱紀委員会に係属しています。
綱紀委員会からX弁護士のところへ、資料の提出を求める手紙が届きました。
さて、この資料提出に応じなければならないのでしょうか。
【解説】
弁護士法70条の7は「綱紀委員会は、調査又は審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。」と定めており、綱紀委員会が資料要求をする根拠となっています。
それでは、これに回答義務があるのでしょうか。これについては法律では何の定めもありません。しかし、弁護士法が綱紀・懲戒委員会の議事などに細かい規定を置いていない関係で、各単位会には各委員会・手続きに関する規定が置かれているものと思われます。その中で、おそらく多くの単位会では「弁護士等については正当な理由ない限り、資料提出を求められたときには応じなければならない」とする規定が置かれているものと思われます。
守秘義務等の理由で応じられないのであれば正当な理由があると認められると思われますが、そのような理由がないのに資料要求を拒絶すると、会の規定に違反する可能性が高いと思われます。
そして、この違反があった場合、どのようになるかが問題です。
多くの議決書では、調査期日に出頭しないこと等が、処分を重くする不利な事情として記載されています。そのため、要求に理由なく応じないことは、処分を却って重くする可能性がある危険な行為です。また、会員には会則に従う義務が定められていますので、会則違反を構成し、新たな懲戒事由となる危険性があります。
そのため、委員会から求められた場合には、範囲はともかく、資料提示を行う必要性があります。
【弁護士が解説】看護師に対する懲戒処分はどのような場合に出されているか

【事例】
看護師であるAさんは、勤務中入院患者の態度にイライラしてしまったことから、つい患者を殴ってしまいました。
たまたまそのことを同僚に目撃されており、Aさんの行為は暴行罪として警察に被害届が提出されました。
最終的にAさんは罰金10万円を支払っています。
このとき、Aさんの看護師免許はどうなるのでしょうか。
【解説】
1 看護師に対する行政処分
保健師助産師看護師法14条によると「保健師、助産師若しくは看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。」とされています。
そして、9条は「一 罰金以上の刑に処せられた者 二 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者 三 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者」として、4つの事由を定めています。
1号を見ると「罰金以上の刑に処せられた者」とあります。これは罪名を問いませんので、たとえ職務に関係のない私生活上の出来事で罰金を受けたとしても、看護師免許に影響が生じる可能性があります。
2 行政処分の実情
看護師に対する行政処分は、医道審議会(保健師助産師看護師分科会看護倫理部会)で議論されています。
そして、その処分の内容は、公表されており、おおよそ1年に1回程度まとめて看護師に対して処分が出されていることが分かります。
たとえば、直近の令和6年11月7日の会議では、24名に対して行政処分が出され、12名に対して行政指導がなされています。
一つ一つ見ていくと、Aさんと同じ系統の罪名として「傷害」であっても、業務停止1年となっているものや、2年、8月と様々な長さの処分がなされていることが分かります。
これは司法判断の重さに影響されている面もあります。たとえば、同じ傷害であっても、かすり傷程度であれば罰金刑で済むのに対し、骨折以上のけがをさせてしまったような場合には懲役刑が選択される可能性が高いなど、怪我の程度によって刑事処分の重さが変化してきます。そして、厚生労働省が処分をするにあたっては、おそらく刑事処分の程度をそれなりに重視していると思われます。そして、その処分の重さが、業務停止期間の長さに反映されていると思われます。
3 Aさんの場合はどうか
Aさんの場合、罪名は暴行と、傷害より軽い罪です。しかし、患者に対する暴行であるため、私生活上の行為よりは重く判断される可能性が高いと思われます。これは行政処分だけではなく、刑事処分を考える上でも同様です。
そのため、免許に対する処分を回避するためには、まず被害者の方に謝罪をし、示談をした上で刑事罰を回避することが必要となります。
【弁護士が解説】弁護士として追求すべき正当な利益とは?

【事例】
X弁護士は、Aから建物収去土地明渡の依頼を受けました。
Xは、まずは交渉したほうが経済的負担が少ないと考えたため、土地上に建物を建築して占有しているBに直接会いに行きました。
Bはその建物内にいたのですが、X弁護士との話が全くかみ合わず、建物内も相当荒れ果てていました。少なくともX弁護士の話はほとんど理解できていないような様子でしたし、書類がたくさん散乱している様子から見ても、認知症ではないかと思われる状態でした。
以上のような様子を見て、X弁護士はこれ以上話し合っていても仕方ないと考え、Bを被告として建物収去土地明け渡し訴訟を提起しました。
すると、訴状は送達されたようですが、Bからは答弁書の提出もなく、そのまま欠席判決となってAが勝訴しました。
そしてこの勝訴判決に基づいて、Xは強制執行を断行しましたが、執行当日もBは以前と変わりない様子で、Xのことすらも忘れているようでした。
X弁護士の対応に問題はあるのでしょうか。
【解説】
依頼者Aからすれば、これ以上ない結果をもたらしており、Xの行為に問題はなさそうです。
ただ、XがBに会いに行った段階で、訴訟提起をしたとしてもBが防御権を行使することは不可能であろうと予想される状態でした。そのため、Xが訴訟提起をすればほぼ確実に欠席判決となり、勝訴できるという見込みがあったもので、Xからすればある意味当然の結果とも言えます。
弁護士としてこのような対応をすることが問題ないのでしょうか。
この事案は、実際にあった事案を少し改変しています。実際の事案では、弁護士職務基本規程5条、6条、21条、74条に違反するとされています。
相手方を利するような行為をすることは、依頼者に対する誠実義務との関係で緊張関係が生じます。しかし、弁護士である以上、無防備の人間を相手に法的手段をとることは、品位を失うと言われてしまう可能性があります。
今回の事例の場合、Bの戸籍等を調査し、親族がいるようであれば成年後見の申立てを依頼したり、仮に親族がいないような場合であっても、市町村長による申立ての手段を検討するなど、Bの防御権を行使させる方法は存在するように思われます。そのため、防御権行使のための検討をしなかった場合、X弁護士が懲戒を受ける可能性も否定できません。
もっとも、弁護士がどの程度Bの状況を認識していたのか、Bが受ける不利益の程度はどのくらいであるのかによっても結論は左右されます。建物収去土地明渡の場合、簡単に言うと住むところがなくなり、財産を失うわけですから、その不利益は相当大きいものといえます。不利益が大きくなればなるほど、防御権を行使させsる必要性が高いと言えます。反対に、Bに対する認識が小さいほど、Xとして取りうる手段を検討する機会が少なくなってきますので、Xが訴訟提起することがやむを得ないと評価されるようになります。
弁護士としては、勝てばよいという考えだけではなく、法律家としてその振る舞いが適切であるかということも評価の基準となっていることを意識する必要があります。
【弁護士が解説】対立当事者からの直接の連絡にはどう対応すべきか?

【事例】
X弁護士は、Aから建物収去土地明け渡し訴訟の依頼を受け、Bを被告として訴訟提起をした。
第1回口頭弁論前に、Bには代理人としてYが選任され、Yから答弁書が提出された。
弁論準備手続が何回か経過した後、裁判所から和解の話を持ち掛けられ、当事者双方が持ち帰り検討することになった。
ある日、Xの事務所にBから連絡があり、Bは以下のようなことを述べた。
「裁判所から出された和解案なのですが、もう少し金額を上乗せしてもらえないでしょうか。そうすれば応じることも考えたいと思っています。また、明け渡しの期限も少しだけ猶予をください。もし、先生の方でお考えいただけるようであれば、その結果を私の方に連絡してください。Y先生に連絡しても、どうせ私のところに連絡が来て、判断するのは私ですので、それなら直接電話をください」
X弁護士は、Bのいうように電話してよいのでしょうか。
【解説】
弁護士職務基本規程52条は「弁護士は、相手方に法令上の資格を有する代理人が選任されたときは、正当な理由なく、その代理人の承諾を得ないで直接相手方と交渉してはならない。」と定めています。
今回のYが「法令上資格を有する代理人」であることは争いありませんので、問題はしてはいけないと定められている相手方との「交渉」の範囲が問題となります。
交渉を辞書的に考えると、「話し合うこと」「かけあうこと」という意味になります。そのため、言わゆる示談交渉などを行うことは当然許されませんし、和解交渉を行うことも許されません。また、交渉の方法も限定されていませんので、対面で面会する以外にも、電話やメール、郵便物を送ることも許されません。
反対に、時効の援用や解除の意思表示というような、一方的な通知であれば、差し支えないと考えられます。それでも、相手方に対して何か応答を求めるような文言を記載することは、直接交渉になりかねませんので、差し控えるべきであると言えます。
それでは事案について検討をします。
まず、XはBから電話があり、その話を聞いています。これ自体は、かかってきてしまった以上、やむを得ないところです。もちろんXとしては、話の内容が和解条項に及びそうになった段階で「そういう話は代理人のY先生を通して伝えてください」という風に対応する方が望ましいように思われますが、話を聞く(ただし、それについて何も弁護士側から応答しない)だけであれば、弁護士が交渉をしているわけではないので、規程には該当しないように思われます。ただし、できれば「私の方から、Y先生にこのようなお電話があったことはお伝えしてよいでしょうか」と尋ね、Y弁護士に連絡をしておいた方がよいと思われます。反対に、ここでYへの連絡を拒絶するような場合には、YとBの間で問題が生じている可能性が高く、今後の対応方法についてより一層慎重になる必要があります。
次に、XがBに返事の連絡をする行為ですが、これは仮に「そのままお受けします」であったり、「お断りします」というような一方的な通知であったとしてもするべきではありません。和解の交渉ですから、さらなる提案がある可能性は十分ありますし、仮に受けるにしても場所や受け渡し方法の調整など、他に交渉すべき事項は残っています。ですので、相手方当事者への直接の連絡は、代理人がいる場合にはするべきではありません。
【弁護士が解説】介護福祉士が交通事故を起こした場合国家資格はどうなるのか

【事例】
介護福祉士であるAさんは、ある日通勤途中、自動車で交通事故を起こしてしまいました。
幸い被害者の方は全治2週間程度のけがではあったものの、警察の方からは事件を検察庁に送ると言われました。
Aさんはどのような刑事罰を受け、それによって介護福祉士の資格はどうなるのでしょうか。
【解説】
2 介護福祉士資格について
それでは、前回に引き続いて、今回は交通事故により介護福祉士の資格がどうなるかを解説していきます。
⑴欠格事由
国家資格が何らかの制限(剥奪されたり、効力が一時停止したり)を受けることになる事由のことを「欠格事由」と呼んでいます。欠格事由は、資格を取得するときに問題となっていますが、同様の事由が生じた場合には資格を取消すということになっています。
そして、介護福祉士についての欠格事由を定めているのは、社会福祉士及び介護福祉士法3条です。
(欠格事由)
第三条次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。
一 心身の故障により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三 この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四 第三十二条第一項第二号又は第二項(これらの規定を第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
これが欠格事由になります。全部で4つ欠格事由が定められています。
1は規則に細かい規定があり、「精神の機能の障害により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」とされています。
2が今回問題となる規定ですので後述します。
3は、同じ刑事罰でも福祉関係の法令に違反した場合です。2が「禁錮以上」となっているのに対し、3は「罰金」となっています。罰金の方が軽い刑罰ですので、福祉関係の法令に違反した場合にはより軽い刑事罰でも欠格事由となります。
4は一度欠格事由があって資格を取消された場合の規定です。仮に欠格事由が生じたとしても試験に合格した事実自体は残りますので、形式的には再度登録できるように思われます。しかし、この規程によって2年間は再登録ができないようになっています。
⑵刑事罰と国家資格
さて、それは本題の刑事罰を受けた場合の資格について検討します。
2号で「禁錮以上の刑」と定められています。刑事罰の重さは死刑>懲役>禁錮>罰金>拘留>科料と定められていますので、禁錮以上の刑は死刑・懲役刑・禁錮刑を指します。反対から言えば、罰金刑であればこの規定に該当しないことになります。つまり、交通事故によって罰金刑を受けた場合や当然ですが不起訴処分になった場合には、資格を取消されたりすることはないということになります。
それでは禁錮刑を受け、その刑に執行猶予が付けられた場合はどうでしょうか。
執行猶予とは、裁判が確定した後すぐに刑務所等に収容されるのではなく、執行猶予期間中無事に過ごせば収容されないという判決です。反面、執行猶予中に再び裁判を受けるようなことがあれば、基本的には刑務所に行かなければならない(もう一度執行猶予になることはほとんどない)という判決です。たとえば「禁錮1年執行猶予3年」という判決の場合、「もし3年間何もせずに過ごすことができれば、刑務所にはいかなく構いません。ただし、3年以内に再び裁判を受けるようなことがあれば、新しく犯した罪の刑罰に、追加して1年刑務所に入ってもらいます」という意味になります。
話を戻すと、交通事故で人をけがさせた場合、余程重大な事情(前科があるとか、飲酒運転であるなど)がない限りは執行猶予がつくことがほとんどです。しかし、先ほどの欠格事由の条文には執行猶予を除外する規程はありませんから、仮に執行猶予がついたとしても資格は取り消されることになります。
交通事故は誰でも起こしてしまう可能性があるものですが、一つ間違えると運転免許以外の資格さえ剥奪されてしまうものになります。これを回避するためには初動の対応が重要です。資格のことでご不安な方は、いち早く弁護士にご相談ください。
【弁護士が解説】国選弁護人が担当被疑者の事件の私選弁護人となってよいか

【事例】
X弁護士は、窃盗罪で勾留中のAさんの国選弁護人として選任され、接見に行きました。
数日間は何事もなかったのですが、ある日接見に行くと、Aさんから次のようなことを言われました。
ケース1
「先生はすごくよくやってくれていると思う。でも、国選弁護人は報酬が低いということを聞くし、それでは先生に申し訳ない。先生を改めて私選弁護人として選任して、費用はお支払いしたいと考えています」
ケース2
「先生に相談があるのです。実は、私は事件の直前に交通事故の被害に遭っていて、加害者の保険会社と示談交渉をしていました。先生を見込んで、この示談交渉について依頼をしたいと考えています。この示談交渉についての弁護士費用は、別途きっちりお支払いします。」
各ケースにおいて、X弁護士は事件を受任してもよいのでしょうか?
【解説】
ケース1について
まず、国選弁護人が同一事件の私選弁護人となれるかどうかについて検討しましょう。
弁護士職務基本規程49条2項によると、「弁護士は、前項の事件について、被告人その他の関係者に対し、その事件の私選弁護人に選任するように働きかけてはならない。ただし、本会又は所属弁護士会の定める会則に別段の定めがある場合は、この限りでない。」とされています。この規程によれば、たとえばX弁護士が、「私選弁護人に切り替えてくれれば、もっとよく接見に来たりする」などというような発言をしていた場合に問題が生じることになります。この規程は「働きかけ」を禁じているものですから、何らの働きかけがなく、本人の方から自発的に私選への切り替えを要望してきた場合には問題がないように思われます。
しかし、同項には但書があり、各単位会の会則などで別段の定めがなされている場合があります。『解説 弁護士職務基本規程(第3版)』をご確認いただければわかりますが、単位会によっては刑事弁護委員会の許可がない限り私選への切り替えを認めない運用をしているところもあります。ですので、働きかけがなかったからといって、直ちに私選弁護人になってよいというものではありません。必ず事前に所属の単位会の会則を確認する必要があります。
ケース2について
ケース2の場合には、元の事件とは全く別の事件の依頼を受けています。これであれば許されるのでしょうか。
ただ、仮にケース2で委任契約を締結すると、当然X弁護士にはいくらかの報酬が支払われることになります。
弁護士職務基本規程49条1項によると、「弁護士は、国選弁護人に選任された事件について、名目のいかんを問わず、被告人その他の関係者から報酬その他の対価を受領してはならない。」とされています。確かに、別の事件での報酬であれば「国選弁護人に選任された事件について」の報酬ではないので、規程に反さないように思われます。また、今回の事件のように被害弁償を要することが予想される事件において、資力確保のための活動(今回でいえば、交通事故の賠償金の回収)を行うことは有益であるとも言えます。
そのため、X弁護士の受任が禁止されるようなものではありませんが、たとえば報酬が通常以上に高額な契約になっている場合には、対価の受領ではないかという疑いが生じます。法テラスを利用しての契約であれば問題が生じる可能性は生じにくいと考えられるので、法テラスの利用などを検討する必要があります。
【弁護士が解説】書面での表現はどこまでであれば許されるのか

【事例】
Aさんから離婚調停の委任を受けたX弁護士は、Aさんの配偶者(B)側が提出してきた準備書面について、Aさんと対応を協議していました。
Aさんとしては、準備書面の内容は事実無根であり、そのようなことを言っている配偶者は決して許すことができないと強く憤っています。
そこで、AさんはX弁護士に対して強い反論を書いてほしいと思っています。
X弁護士の立場で、以下のような表現をすることは許されるでしょうか。
①Bは平気でうそをつく性格を有することは明らかであり、嘘で固めた人生を送っている
②Bのごね得は許されるべきではなく、これらすべてが演技であったとすれば俳優顔負けである
③Bの主張する事実は全て虚偽のものであり、良心のかけらも見出されない
【解説】
弁護士職務基本規程6条によれば、「弁護士は、名誉を重んじ、信用を維持するとともに、廉潔を保持し、常に品位を高めるように努める。」とされています。
弁護士法56条の懲戒事由に「その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたとき」という規程が設けられていることからしても、弁護士が品位を失うような行為をした場合には、何らかの懲戒処分を受ける可能性があります。
弁護士が職務上作成する書面は、基本的には読者が外部に存在するケースがほとんどです。また、その読者は、たいていの場合対立する当事者や裁判所であったりします。そうすると、どうしても依頼者の意向などに流され、過激な表現となってしまうケースがあります。
弁護士としての表現が過激であった場合、それが不必要なものであると判断されてしまうと、品位を失うようなものとして懲戒を受ける可能性があります。なお、たとえば当事者らの発言を引用する形で書面を作成し、その発言内容自体が過激なものであった場合は、弁護士が行った表現というわけではありませんから、それを理由として懲戒を受けるということは考えにくいと思われます。
上記に記載した①~③の事例は、いずれも実際に懲戒を受けた事案で問題となった表現を参考に作成したものです。「こんなこと書くわけないだろう」と思われたかもしれませんが、実際にこれに近い表現の書面が出されたことがあります。
このような書面とならないよう、冷静な目で書面を作成し、依頼者に対しては懲戒の可能性や、裁判官の心証(おそらく、過激な表現をしても心証は良くならないばかりか、かえって悪化すると思われます)の点について説明を尽くし、合理的な範囲に収めることが必要となります。
« Older Entries Newer Entries »