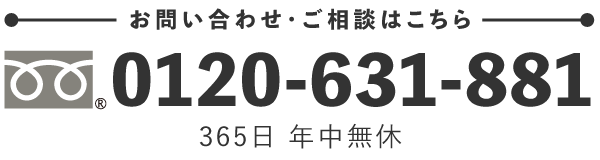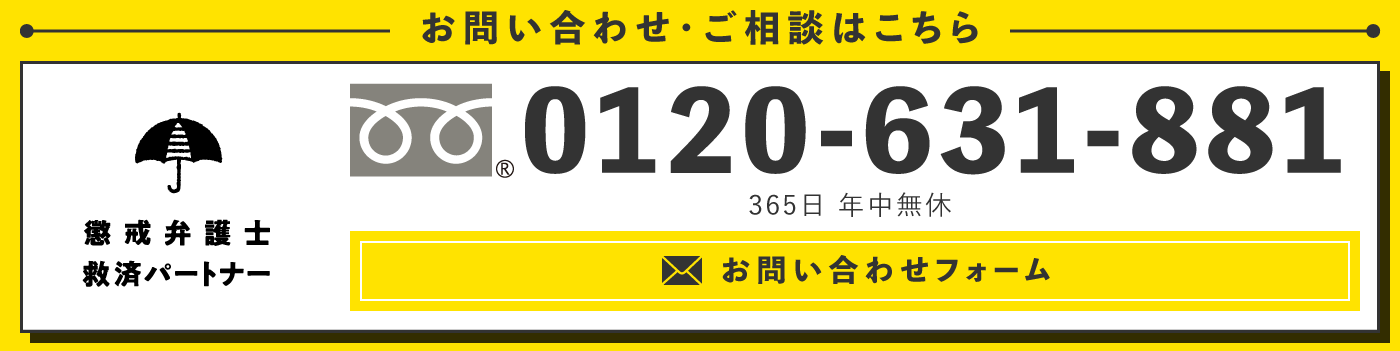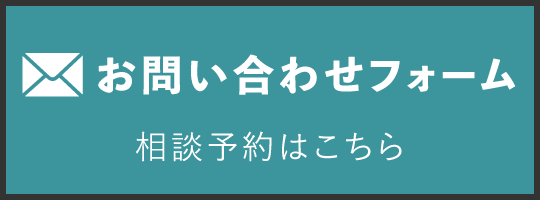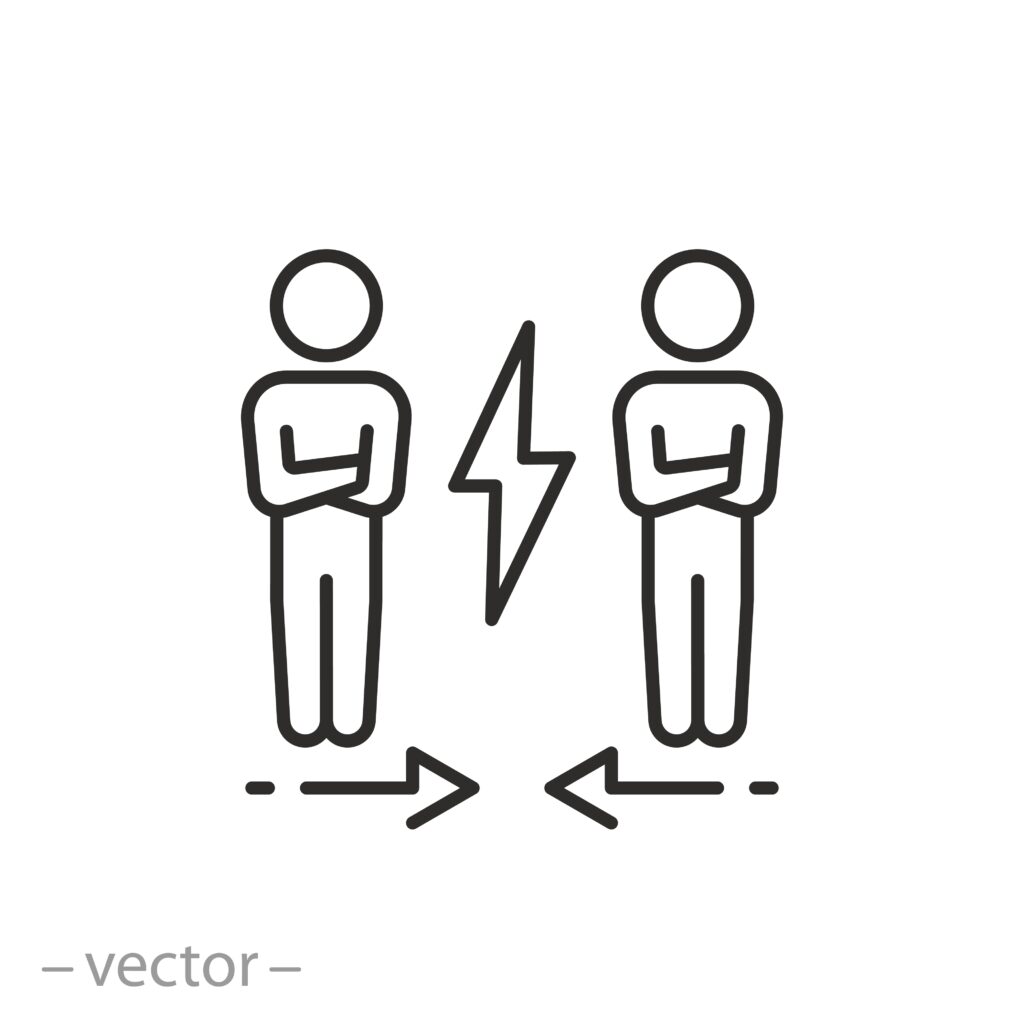
【事例】
X弁護士は、亡Aの遺産相続に関して遺言執行者に選任され、遺言執行を終えた。
ただ、その遺産の中にあった不動産について、Aの相続人のBとCの間で対立があり、Aの遺言上はBが相続するということになっていたのでXもその通り手続きを進め、登記上はBが所有者となったのだが、実際にはCが占有を継続しているような状況となった。
X弁護士は、遺言執行が終了した後、Bから「先生、Cがまだ建物を占拠しているのは納得できないので、先生が私の代理人となってCを訴えてください」との依頼を受けた。
そこで、X弁護士は、Bを代理して、Cに対して明け渡し訴訟を提起した。
【解説】
X弁護士が最初に請け負っていた事件は、遺言執行であり、依頼者はいうなれば亡Aでした。しかし、遺言執行者は特定の相続人の代理人というわけではありませんので、相続人間では公平であるべきです。
実際、東京高判平成15年4月24日によると「遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の権利義務を有し(民法一〇一二条)、遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない(同一〇一三条)。すなわち、遺言執行者がある場合には、相続財産の管理処分権は遺言執行者にゆだねられ、遺言執行者は善良なる管理者の注意をもって、その事務を処理しなければならない。したがって、遺言執行者の上記のような地位・権限からすれば、遺言執行者は、特定の相続人ないし受遺者の立場に偏することなく、中立的立場でその任務を遂行することが期待されているのであり、遺言執行者が弁護士である場合に、当該相続財産を巡る相続人間の紛争について、特定の相続人の代理人となって訴訟活動をするようなことは、その任務の遂行の中立公正を疑わせるものであるから、厳に慎まなければならない。」とされており、中立性が要求されています。
本事例と同様の事例において、戒告の処分とした例があります。遺言執行者としての任務が終了したからといって直ちにどのような事件でも受任可能になるというわけではなく、特定の相続人に偏ったものではないかどうかを検討したうえで、弁護士の公平さ(弁護士職務基本規程第5条)に反しないかを検討するべきであると言えます。形式的には利益相反の規程に反しませんが、注意を要します。