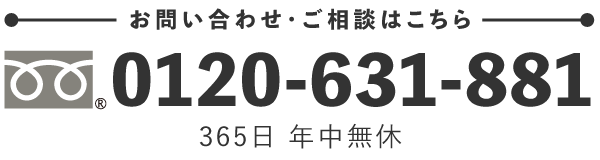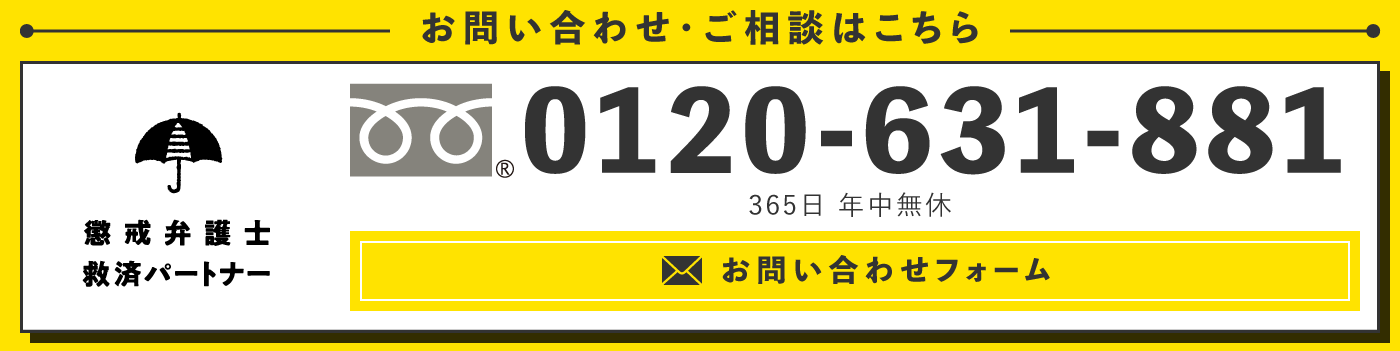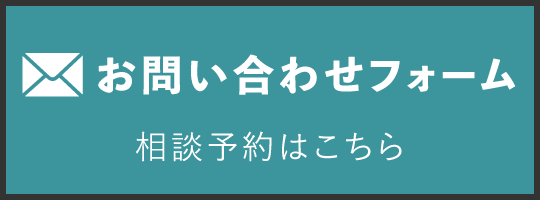このページの目次
1 事案の概要
元々の事案は、原告である大手貸金業者が、被告(個人)に対してキャッシングに基づく貸金契約の返済を求めた事件でした。
しかし、これに対して被告が原告に対して反訴提起しました。この反訴提起は、被告が、原告に対して不当利得返還請求権を有する別の人物からその債権を譲り受け、譲り受けた不当利得返還請求権を元に起こしたものでした。
この債権譲渡について、弁護士法72条に違反するものではないかということが問題となりました。
(東京地判平成17年3月15日の事案)
2 判旨
まず、弁護士法七三条は、「何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によって、その権利の実行をすることを業とすることができない。」と規定しているところ、被告が、本件債権譲渡を「業」としてしたことを認めることはできないから、本件債権譲渡が同条に直接違反するものとはいえない。
また、弁護士法二八条は、「弁護士は,係争権利を譲り受けることができない。」と規定しているところ、本件債権譲渡の法律主体は被告であるから、やはり、本件債権譲渡が同条に直接違反するものとはいえない。
また、弁護士法二五条の趣旨を受ける弁護士倫理二六条二号は、弁護士が「受任している事件と利害相反する事件」については職務を行ってはならないと規定しているところ、本件債権譲渡を前提とした反訴の提起自体が、被告及びApの債務整理受任事件と直接利害相反するものと認めるのは困難である。
さらに、弁護士法七二条本文は、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件(中略)その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」と規定しているところ、被告が本件債権譲渡を受けて反訴を提起したこと自体が同条によって直接禁止される行為であるということも困難である。
そうすると、本件債権譲渡に関する被告又は被告訴訟代理人らの行為について、これらの各規定の直接適用はできないものというほかない。
もっとも、弁護士法七三条の趣旨は、非弁護士が権利の譲渡を受けて事実上他人に代わって訴訟活動を行うことによって生ずる弊害を防止し、国民の法律生活に関する利益を保護しようとする点に、また、弁護士法二八条の趣旨は、弁護士が事件に介入して利益を上げることにより、その職務の構成、品位が害せられることを未然に防止しようとする点に、それぞれ存するものと解される。
また、弁護士倫理二六条二号の趣旨は、弁護士が、法律上及び事実上の利益・利害が相反する事件について職務を行うことを防止し、もって当事者の利益を保護するとともに、弁護士の品位を保持し、さらには、弁護士の職務の公正さと弁護士に対する信用を確保しようとする点に存するものと解される。
さらに、弁護士法七二条本文前段の趣旨は、弁護士業務の誠実適正な遂行の担保を通して当事者その他の関係人の利益を確保し、もって、法律秩序全般を維持し、確立させようとする点に存するものと解される。
ところで、前記に認定した本件紛争の経緯に、被告が本人尋問に出頭しないことにつき民事訴訟法二〇八条の規定の趣旨を併せると、本件債権譲渡は、Bら法律事務所に所属する弁護士主導のもとに斡旋されたものであることが明らかである。
そして、これら一連の行為を実質的に見れば、法律事務所の弁護士らが主体となり、報酬を得る目的で、業として、自らが債務整理を受任した依頼者のうち原告に対して不当利得返還請求権を有している不特定多数の者から原告に対して貸金債務を負担している不特定多数のものに同不当利得返還請求権を譲渡させ、これらの権利の実現を訴訟等の手段を用いて実行しているものということができる。
かかる行為は、前記の弁護士法七三条及び二八条の趣旨に抵触するものというべきであり、かつ、斡旋の際の説明内容や、対価の額及び支払態様、これらと債務整理事件の報酬との関係によっては、原告に対して不当利得返還請求権を有している不特定多数の依頼者の利益を損ねるという、前記の弁護士倫理二六条二号の趣旨に具体的に反するおそれが高い、看過し難い行為であるというべきである。
そうすると、かかる債権譲渡行為の私法上の効力を認めてこれを放任することは、不特定多数の関係人の利益を損ね、広く弁護士業務の誠実適正な遂行やこれに対する信頼を脅かし、ひいては法律秩序を害するおそれがあると認められるのである。
よって、かかる態様による債権譲渡は、公序良俗に反し無効であると解するのが相当である。
3 説明
なぜ弁護士事務所がこのようなことをしたのかということについて明らかにはされていませんが、おそらく訴訟手数料の集約や、手続の負担を軽減する(同じ相手方に対して多数の訴訟が係属するより、一本の訴訟内でまとめて解決したほうが負担が少ない)という目的ではないかと思われます。
このとき、弁護士自身が譲り受けるわけにはいかない(係争権利の譲り受けとなる)ため、依頼者の内の一部の者に権利を集約してしまうという手法がとられたものと思われます。
しかし、このような手法は当然法の潜脱ということになりますから、上記判旨の通り無効されました。