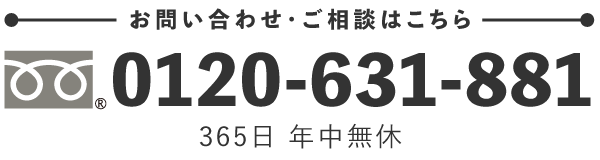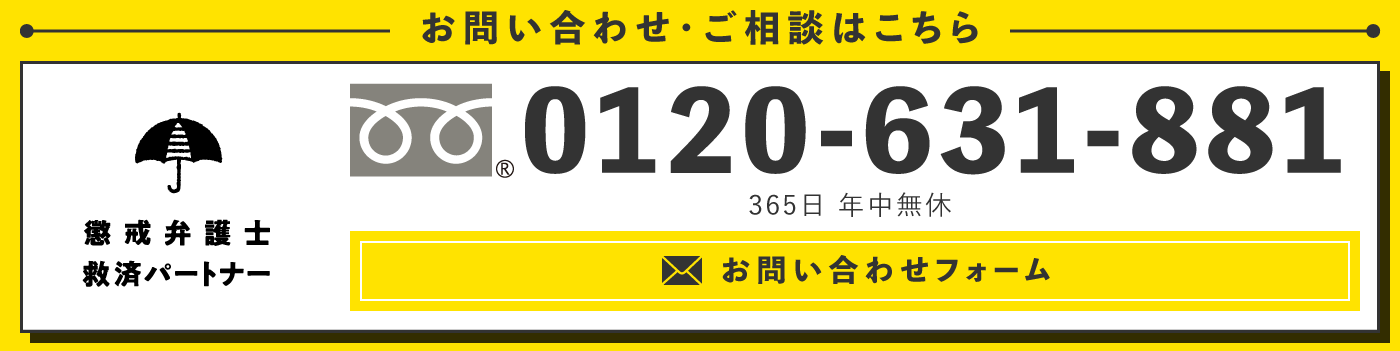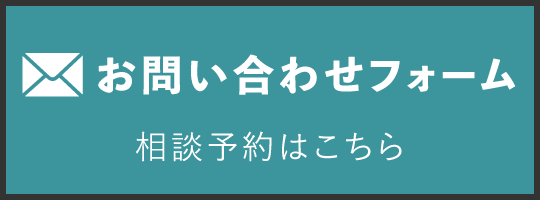【事例】
X弁護士は、Aから、ある不動産の明け渡しに関する相談を受け、Bに対して訴訟提起を行った。
しかし、この訴訟でXが主張した法的な構成は、第一審でも第二審でも認められず、Aは敗訴しました。
この結果に納得できなかったAは、Xに対して再び訴訟提起をすることを求めました。ただ、X弁護士としては、既に主張できる法的構成は1回目の裁判で主張してしまっており、今さら新たな法的構成を考えたとしても無理筋なものであると考えていました。既判力のことを考えると、どうしても訴訟提起は難しそうです。
このとき、X弁護士が訴訟提起をすることに問題はないでしょうか。
【解説】
弁護士は、不当な事件を受任することはできません(弁護士職務基本規程31条)。
今回のように、不当訴訟と思われるものを引き受けることは、この規程に違反する可能性があります。ただ、だからといって裁判を受ける権利がある以上、代理人になることが一律に否定されるものではありません。
裁判例で、弁護士の訴訟提起行為が不法行為を構成する場合は、「一般に代理人を通じてした訴や控訴の提起が違法であって依頼者たる本人が相手方に対し不法行為の責を負わなければならない場合であっても、代理人は常に必ずしも本人と同一の責を負うべきものと解することはできない。すなわち、代理人の行為について、これが相手方に対する不法行為となるためには、単に本人の訴等の提起が違法であって本人について不法行為が成立するというだけでは足りず、訴等の提起が違法であることを知りながら敢えてこれに積極的に関与し、又は相手方に対し特別の害意を持ち本人の違法な訴等の提起に乗じてこれに加担するとか、訴等の提起が違法であることを容易に知り得るのに漫然とこれを看過して訴訟活動に及ぶなど、代理人としての行動がそれ自体として本人の行為とは別箇の不法行為と評価し得る場合に限られるものと解すべきである。」(東京高判昭和54年7月16日)とされています。そのため、単に不当訴訟だと認識しながら訴訟提起するだけでは足りないと考えられていますので、弁護士としてはそこまで心配する必要はありません。
不法行為上の責任を負う場合よりも、懲戒請求を受ける場合の方がより厳格な場合に限定されます。そのため、懲戒請求を受けるのは、被告に損害を与える目的が明白な場合や、それにより弁護士が利益を得る場合など極限的な場合に限られると考えられます。
もっとも、原告(依頼者)側が敗訴に納得するかという問題も再びあります。弁護士は結果を装って受任することが禁止されているので、原告には敗訴の可能性を十分告知した上で受任しなければなりません。