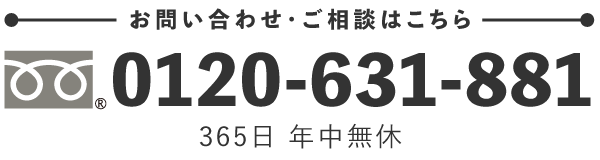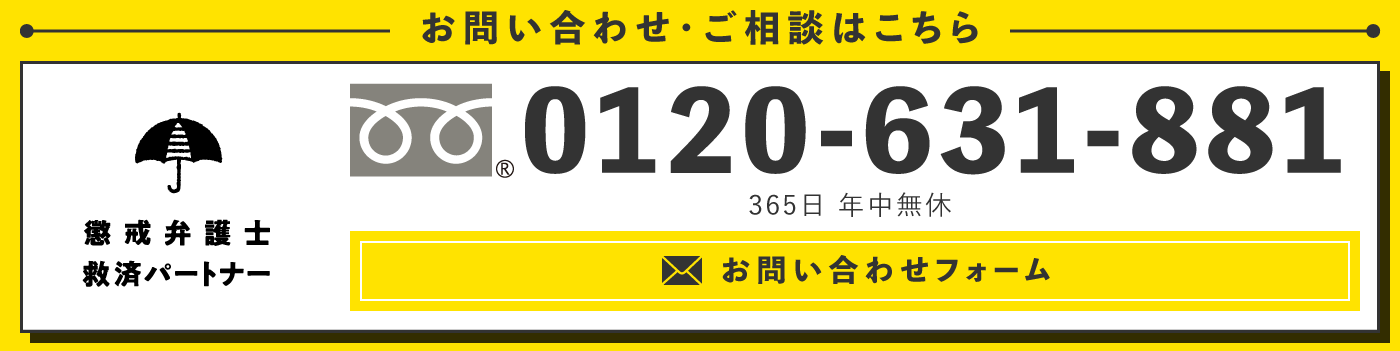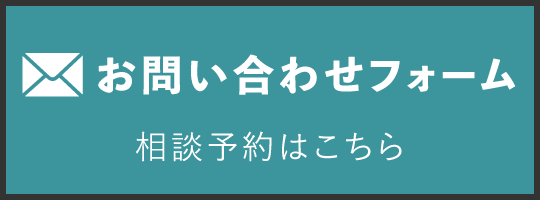Archive for the ‘懲戒処分’ Category
【弁護士が解説】弁護士報酬を請求する際にトラブルとなった場合にはどのように対応すればよいか

【はじめに】
弁護士として事件を受任し、時間と労力をかけて、なんとか当初の見立て通りの結果が出たとします。仮に弁護活動の結果自体は満足のいくものであったとしても、法的紛争が起こっているからこそ弁護士にお金を払って依頼するのであり、事件が終了したのであれば弁護士にお金を払いたくないと考えてしまうのはある意味合理的なのかもしれません。したがって、事件終了時にトラブルになる可能性が高い問題の一つとして、報酬に関する問題が出てきます。
今回は、弁護士報酬に関してトラブルになった事例を一つ取り上げて、弁護士報酬トラブルでの懲戒請求について説明します。
【事例】
X弁護士は、登録15年程度の弁護士であり、個人事業主として法律事務所を経営していた。あるとき、依頼者男性Yから、相手方女性Zとの離婚調停、審判、裁判を受任した。離婚、財産分与、親権に関する結果についての成功報酬額は委任契約書に記載されていた。経済的利益の計算方法は法律事務所の基準による旨を説明しており、当該基準は法律事務所のホームページにも記載されていた。X弁護士の見通し説明としては、離婚を防ぐこと、子の親権をYとすることは困難であるものの、Zの不貞等の関係やZ側の財産分与に関する主張との関係で、財産分与についてはZ側の請求額から一定程度が減額される可能性があるとのことであった。着手金は、受任の時点でYからXに支払われた。
受任から約3年後、結局審判を経てYとZは正式に離婚することとなり、子の親権者はZとされたものの、YがZに支払わなければならない金額としてはZの請求額よりも1000万円程度減額された。 弁護士報酬は、着手金、成功報酬、日当を合わせると合計400万円程度となった。X弁護士から依頼者Yに上記報酬を請求したところ、Yから、財産分与については一定の結果が出たものの自分としては親権を獲得したいというのが一番の希望であって、事件解決にも時間がかかっているので報酬には不満であること、弁護士報酬についても説明が十分になかったこと、他の弁護士事務所よりも弁護士報酬が高いので弁護士報酬を払いたくないと言った不満が出た。これに対し、X弁護士は料金は契約書通りであるので必ず支払ってもらう旨Yに伝え、それから3か月ほどYに内容証明等で督促をし続けたがYは一向にZが上記弁護士報酬と着手金の差額を支払おうとしなかった。そのため、XはZに対し、弁護士報酬の合計を350万円とする旨の提案をしたが、Yはそれにも応じなかった。やむなく、Xは所属弁護士会に対して紛議調停を申し立てたところ、それに腹を立てたYがXを懲戒するよう、Xが所属する弁護士会に懲戒請求を行った。
(事例は、フィクションであり、実在の弁護士、依頼者、その他個人、会社、団体とは一切関係ありません。)
【対応方法】
弁護士として仕事をしていると、事件が終わったところになってこのように元依頼人から報酬についての不満を出されることがあるかと思います。このような場合に実際に懲戒処分がされる事案については、ある程度共通した事情があると考えられます。
本件に関係しそうな規定は以下です。
弁護士職務基本規程
(名誉と信用)
(弁護士報酬)
第二十四条 弁護士は経済的利益事案の難易時間及び労力その他の事情に照らして 適正かつ妥当な弁護士報酬を提示しなければならない。
弁護士法
(懲戒事由及び懲戒権者)
第五十六条 第1項 弁護士及び弁護士法人は、この法律(弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員又は使用人である弁護士及び外国法事務弁護士法人の使用人である弁護士にあつては、この法律又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律)又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
本記事を作成するために調べた限りだと、弁護士報酬が単に他の事務所よりも高いからといってそれだけで懲戒処分がなされる事案は多くないように思われます。懲戒処分がなされるような事案は、契約の際の説明に大きな不備があるとか、あまりにも相手方に配慮がない請求の仕方を行っている等の要素が目立っているように思います。本件について考えると、弁護士報酬や計算基準については契約書に記載されていますが、経済的利益の計算基準についてはX弁護士の法律事務所基準によるとし、実際にホームページに記載があるとはいえ、契約の際に具体的には説明を行っていません。この点については、「基準」の予測可能性がどの程度あるか、「基準」について依頼者が疑義を申し立てることが有ったかどうかが問題になりそうです。
また、弁護活動が完全に成功したわけではないところで契約書通りの請求を行っていますが、依頼人によってはそのような請求をとらえて懲戒請求において主張してくる可能性があります。弁護士報酬の説明状況等について具体的に説明出来るようにしておくことで、実際に懲戒処分を避けることができる可能性が上がるでしょう。
最後に、X弁護士側から紛議調停を申し立てた点ですが、具体的な交渉状況を説明し、これがやむを得なかったことを説明する必要があります。
【最後に】
上に挙げた事例とは異なり、弁護活動に際して契約書を作成せずに弁護活動に入り、弁護士報酬を請求して懲戒される、というパターンは非常に典型的なパターンといえます。上に挙げた事例では、契約書もありますし、依頼者に対して相当な説明をした、という主張は比較的しやすいかも知れません。しかし、懲戒処分は厳密な証拠裁判主義にのっとって行われる民事・刑事裁判とは異なりますので、懲戒対応の経験やノウハウを持つ弁護士が代理に入ることで、納得のいかない処分を回避出来る可能性は上昇すると考えられます。
加えて、勤務弁護士が懲戒処分を受ければ、当該勤務弁護士について解雇・業務委託契約解除をしたとしても法律事務所への悪影響が生じるのを防げない可能性があります。
勤務弁護士が懲戒請求を受けている場合も含めて、懲戒請求手続のノウハウを持つ弁護士への相談を検討している先生方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
弁護士法人の懲戒①
1 弁護士法人の懲戒
弁護士法人は、弁護士同様弁護士会に所属をしており、弁護士会による監督を受ける存在です。
そのため、所属弁護士とは別に弁護士法人自体についても懲戒を行うことが可能となっています(弁護士法30条の2以下)。
もちろん、弁護士法人に所属する弁護士自体に懲戒処分を出すことも可能ですが、仮に弁護士法人自体に懲戒ができないとすれば、所属弁護士を入れ替えるだけで業務を継続できることになってしまい、組織的に行われた非違行為等に対応できなくなる可能性があります。ですので、弁護士法は弁護士だけではなく弁護士法人にも懲戒処分を行うことができるようにしています。
2 懲戒事由
弁護士法人に対する懲戒事由は、弁護士に対するものと同じです。
⑴戒告
これについては全く自然人たる弁護士と同じです。
⑵業務停止
弁護士法人は、主たる法律事務所と従たる法律事務所を有している場合があります。
この場合、従たる法律事務所を監督する弁護士会は、その従たる法律事務所のみを業務停止にすることが可能です。
これに対し、主たる法律事務所を監督する弁護士会は、その弁護士法人自体に対する監督権限を有していますから、主たる法律事務所だけではなく、他の管轄区域にある従たる法律事務所の業務の停止も命ずることが可能です。
弁護士法人が業務停止の処分を受けた場合でも、そこの所属する社員弁護士や使用人弁護士自体は、弁護士としての業務停止を受けたものではありませんから、個人として弁護士業務を行うことは可能です。
この点については「被懲戒弁護士法人の業務停止期間中における業務規制等について弁護士会及び日本弁護士連合会の採るべき措置に関する基準」(平成13年12月20日理事会議決)があります。弁護士法人自体が業務停止となった場合、基準第2第1項16号ロによると「被懲戒弁護士法人の社員等は、被懲戒弁護士法人が第一号又は第二号の規定により解除すべき、又は解除した法律事件等を、自己の業務として引き継いで受任することができない。」とされていますので、個人として受けていた業務は継続できるものの、事務所として受任した事件については、これを個人に引き継いで受任することはできないとされています。
除名処分
1 除名
除名とは、懲戒処分の中で最も重い処分であり、効力発生日から3年間弁護士となる資格を喪失させる処分です(弁護士法7条3号)。
退会命令の場合、特定の弁護士会から退会を命じられるのみで、弁護士となる資格を喪失するわけではありませんので、別の弁護士会へ登録の請求を行うことは可能ですし、実際登録することも法律上は不可能ではありません。
しかし、除名の場合には弁護士となる資格そのものが3年間失われますので、いかなる弁護士会にも登録することができず、弁護士としての活動が不可能になるということになります。
ただ、除名の処分を受けたとしても、司法修習生の修習を終えたこと自体は取り消されたりするわけではありませんので、3年間経過すれば、弁護士となる資格自体は回復することとなります。
2 除名の効果
除名処分を受けると、その効力が発生した時点で弁護士でなくなります。
そのため、弁護士法74条の規定により、弁護士や法律事務所の標示は禁止されますし、業として法律事務を行うことも許されなくなります。
それだけでなく、記章を返還するほか、法律事務所を閉鎖することも求められます。
3 除名後
除名を受けると、その旨が公告されるほか、裁判所、検察庁といった関係官公署にも通知されることとなっています。
また、当然ではあるのですが、弁護士ではなくなりますので、会費の徴収も行われなくなります。
退会命令
1 退会命令
退会命令は、対象弁護士を所属弁護士会から一方的に退会させる処分です。
そのため、退会命令の効力が生じると、その弁護士は単位会を退会することとなり、同時に弁護士の身分を失うこととなります。
2 退会命令の効果
退会命令の効力が生じると弁護士ではなくなりますので、当然法律事務所を標榜してはいけなくなりますし、報酬を得る目的で法律事務を行うことも禁止されます。
また、弁護士事務所を直ちに閉鎖し、記章や身分証明書もすぐに返還しなければなりません。
3 退会命令後
退会命令後は、単位会は日弁連及び関係各所(裁判所、検察庁)へ連絡を行い、日弁連は懲戒の公告を行います。
ただ、退会命令がの効力が生じると、対象弁護士は既に弁護士ではなくなっていますので、弁護士会は対象弁護士(であった者)に対して指導監督を行うことはできません。
4 退会命令後の再登録
退会命令は、あくまでも当該単位会を退会させるという命令にすぎません。
そのため、弁護としての身分を失うだけであって、弁護士となる資格を喪失するものではありません。
ですので、他の弁護士会が当該弁護士会や他の弁護士会に対し、改めて登録の請求を行うことは可能です。
しかし、過去に退会命令を受けている事実などから、日弁連への進達を拒絶される可能性があります。
業務停止④
1 基準の存在
以前記載した通り、業務停止中の弁護士が、いかなる活動をすることができるかということについてはそれほど定まった法令等があるわけではありません。
そのため、日弁連は平成4年の理事会決議として「被懲戒弁護士の業務停止期間中における業務規制等について弁護士会及び日本弁護士連合会の採るべき措置に関する基準」を公表しています(弁護士法人、外国法事務弁護士についても同様の規定があります)。
それでは、この規程にはどのようなことが定めてあるのでしょうか。
2 基準の内容
今回は、受任事件以外の規定をいくつか確認します。
①法律事務所の管理行為
「被懲戒弁護士は、法律事務所の管理行為及び賃貸借契約並びに補助弁護士等及び従業者との雇用契約等を継続することができる。」
代表弁護士が懲戒を受けたような場合でも、雇用している弁護士との契約や、事務員との雇用契約を解除することまでは求められません。これは、業務停止期間が経過した後は再び弁護士として活動することが予定されているからです。
②法律事務所の使用
「被懲戒弁護士は、その法律事務所を自らの弁護士業務を行う目的で使用してはならない。ただし、受任事件の引継ぎその他この基準によって業務停止の期間中も認められている事務等のため必要があるときは、その法律事務所の使用目的その他必要な事項の届出を行った上で、弁護士会等の承認を得てその法律事務所を使用することができる。(後略)」
業務停止を受けた弁護士は弁護士としての活動を行うことができませんので、その目的で法律事務所を使用することはできません。ただし、引継ぎ等は必要であり、求められるところですので、例外的に使用が許容されています。
③外観的な規定
「被懲戒弁護士は、直ちに弁護士及び法律事務所であることを表示する表札、看板等一切の表示を除去(表示としての機能を失わせる措置一般をいう。以下同じ。)しなければならない。(後略)」
「懲戒弁護士は、弁護士の肩書又は法律事務所名を表示した名刺、事務用箋及び封筒を自ら使用し、又は他に使用させてはならない。(後略)」
「被懲戒弁護士は、弁護士記章規則(規則第三十五号)第五条第二項及び弁護士等の身分証明書の発行に関する規則(規則第六十号)第十三条第一項第二号の規定により、直ちに弁護士記章及び身分証明書を日本弁護士連合会に返還しなければならない。」
業務停止中は弁護士としての活動を行うことができませんから、外部から見て弁護士のように見えるものは除去を求められます。それが看板・広告の除去、名刺等の使用禁止、身分証・徽章の返還に表れています。
④受任事件以外の事件
「被懲戒弁護士は、弁護士会及び日本弁護士連合会並びに法第四十四条の弁護士会連合会の会務に関する活動をすることができない。」
「被懲戒弁護士は、弁護士会等の推薦により官公署等の委員等に就任している場合は、直ちに当該官公署等に対し、辞任の手続を執らなければならない。弁護士であることに基づき委嘱された人権擁護委員、選挙管理委員、労働委員会委員、調停委員、鑑定委員、破産管財人、後見人、後見監督人等についても、同様とする。」
受任事件以外であっても、会務活動や、弁護士であることを理由に推薦されている官公署の委員等についても辞任をする必要があります。
業務停止③
1 基準の存在
前回記載した通り、業務停止中の弁護士が、いかなる活動をすることができるかということについてはそれほど定まった法令等があるわけではありません。
そのため、日弁連は平成4年の理事会決議として「被懲戒弁護士の業務停止期間中における業務規制等について弁護士会及び日本弁護士連合会の採るべき措置に関する基準」を公表しています(弁護士法人、外国法事務弁護士についても同様の規定があります)。
それでは、この規程にはどのようなことが定めてあるのでしょうか。
2 基準の内容
まず今回は、事件の処理等に関する規律を確認します。
①受任事件の取扱い
被懲戒弁護士は、受任している法律事件(裁判所、検察庁及び行政庁(以下「裁判所等」という。)に係属するものに限らない。以下「受任事件」という。)について、次のイからニまでに従った措置を採らなければならない。
イ 被懲戒弁護士は、直ちに依頼者との委任契約を解除するとともに、委任契約を解除した受任事件に ついて、解除後直ちにその係属する裁判所等に対し、辞任の手続を執らなければならない。
ロ イの規定にかかわらず、業務停止の期間が一箇月以内であって、依頼者が委任契約の継続を求めてその旨を記載した確認書を作成し、その写しを弁護士会等に提出する場合は、被懲戒弁護士は、依頼者との委任契約を解除しないことができる。ただし、被懲戒弁護士が依頼者に対して委任契約の継続を求める働きかけをした場合は、この限りでない。
このように、短期間で終了する事件以外は、受任事件は原則解除となります。
②顧問契約の取扱い
被懲戒弁護士は、直ちに依頼者との顧問契約を解除しなければならない。
顧問契約は、例外なく解除です。
③期日変更
被懲戒弁護士は、期日の延期及び変更の申請をすることができない。
これが意外と思われるかもしれませんが、たとえば業務停止期間が1カ月間であり、その停止期間中に存在する期日を、停止期間外に延期するよう求めるというようなことは許されていません。
このようなことを許してしまうと、①の潜脱となりかねません。業務停止を受けた場合には、速やかに辞任をし、依頼者が新しい弁護士に依頼できる期間を作るようにしなければなりません。
④復代理人の選任
被懲戒弁護士は、新たに復代理人を選任し、又は他の弁護士若しくは外国法事務弁護士を雇用する等してはならない。
これも①の実効性を確保するために必要です。復代理人を選任し、その者に業務停止期間を乗り切ってもらうというようなことは許されません。
業務停止②
1 業務停止期間中にできないこと(前回の続き)
(1)税理士等の業務
弁護士が、弁護士業務の一環として税務活動を行うような場合には、これは当然停止されます。
問題は、弁護士が、弁護士という資格を利用して、同時に税理士登録をしている場合(税理士法第3条第1項3号)、この税理士資格に基づく業務がどのようになるかです。
この点について税理士法には第43条で、原資格が停止されたときには税理士業務を行ってはならない旨の規定があります。
しかし、同じように弁護士がその資格を以て登録可能な資格の中でも、弁理士にはそのような規定はありません(社会保険労務士なども同様)。このような場合にどのように考えるかが問題となりますが、それらの資格にはその資格特有の懲戒手続が存在し、そのような懲戒手続きを経ず、法の規定もない中で、資格の効力を制限することはできないと考えられています。
ただ、弁理士については、次回説明をする通知により特別の定めがありますので、その点に注意をする必要があります。
(2)会務活動
業務停止によって停止される「業務」については、弁護士法第3条で定める業務、つまり「弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。」に記載されていることに限られるという考え方と、それに限らず広く考える考え方と2通りあり得るところです。
そのため、業務を限定的に解釈した場合には、弁護士会の会務活動はこれに当たらず、業務停止期間中であっても会務は可能であると考えることになります。対して、業務を広く考えれば、会務活動を禁止することに繋がります。
この点についても、通知に特別の定めがありますので、そちらに従うことになりますが、会則上は会務活動は行えないことになっています。
ただ、法解釈としては、文言上は法律に定められた職務を基準に考えるべきであるとも考えられます。
(3)業務停止に関する基準
これまでの通り、業務停止期間中にどのような業務を行うことが禁じられるのかについては、解釈上明確でない点があります。
そのため、この点を明らかにするため、日弁連では業務停止中の禁止事項を定める通知が必要となるところです。
現行の通知は、平成4年に発出された「被懲戒弁護士の業務停止期間中における業務規制等について弁護士会及び日本弁護士連合会の取るべき措置に関する基準」であり、実際にはこの基準に基づいて、各弁護士への指導が行われることになっています。
業務停止中の行為が問題となった事例
1 事案の概要
元々の事案は、信用組合が個人に対し、約束手形に基づいて金銭の請求をした事件でした。
第1審は原告(信用組合)の勝訴、控訴審は第1審被告(個人)の勝訴でした。
この控訴審までは、弁護士の資格について特に争われた形跡はありません(手形の振り出しなどが問題となっていました)。
この控訴審判決について、第1審原告(信用組合)が上告しました。
ところで、この事件の第1審判決期日は昭和38年11月7日、控訴審判決期日は昭和40年2月16日で、その間に控訴審の訴訟手続きが行われています。
第1審被告の控訴審での代理人弁護士は、昭和39年3月18日に弁護士会で業務停止3月の懲戒処分を受けているところでしたが、昭和39年4月15日、控訴審における口頭弁論期日が開かれていました。
この口頭弁論期日での訴訟行為につき、上告人(信用組合)代理人弁護士が、無効な弁論であると主張して絶対的上告理由がある旨を主張しました。
(最判昭和42年9月27日の事例)
2 判旨
「裁判所が右の事実〔注:業務停止の事実〕を知らず、訴訟代理人としての資格に欠けるところがないと誤認したために、右弁護士を訴訟手続から排除することなく、その違法な訴訟行為を看過した場合において、当該訴訟行為の効力が右の瑕疵によつてどのような影響を受けるかは自ら別個の問題であつて、当裁判所は、右の瑕疵は、当該訴訟行為を直ちに無効ならしめるものではないと解する。いうまでもなく、業務停止の懲戒を受けた弁護士が、その処分を無視し、訴訟代理人として、あえて法廷活動をするがごときは、弁護士倫理にもとり、弁護士会の秩序をみだるものではあるが、これについては、所属弁護士会または日弁連による自主・自律的な適切な処置がとられるべきであり、これを理由として、その訴訟行為の効力を否定し、これを無効とすべきではない。けだし、弁護士に対する業務停止という懲戒処分は、弁護士としての身分または資格そのものまで剥奪するものではなく、したがつて、その訴訟行為を、直ちに非弁護士の訴訟行為たらしめるわけではないのみならず、このような場合には、訴訟関係者の利害についてはもちろん、さらに進んで、広く訴訟経済・裁判の安定という公共的な見地からの配慮を欠くことができないからである。」「本件を検討するに、一件記録によれば、弁護士Aが原審において被上告人の訴訟代理人として引き続き訴訟行為をしたこと、しかも裁判所が同人の訴訟関与を禁止した事実のないことがうかがわれるのであつて、同人に対し、所論のような懲戒がされ、しかもその処分が前示のようにすでにその効力を生じていたとしても、以上述べた理由により、同人が原審でした訴訟行為が無効となるものではない」
3 解説
本判決は、訴訟経済等の理由から、業務停止中の弁護士の訴訟行為を有効と取り扱いました。
なお、本判決中でも指摘されていますが、訴訟行為が有効であるからといって、その行為に何らの問題もないというわけではなく、この行為自体も再び懲戒の事由となります。
ですので、業務停止を受けた弁護士としては、速やかに辞任等の措置をとる必要があります。
業務停止①
1 業務停止とは
弁護士の懲戒処分の2つ目は、「業務の停止」(通常、業務停止と呼ばれます)です。
これより重い処分である退会命令、除名が弁護士としての身分に直結するような処分であるのに対し、業務停止の処分は弁護士という身分自体には影響しません。そのため、業務停止期間中であっても、弁護士会の会費は徴収されます。
2 業務停止の期間
弁護士法第57条1項2号の定めでは、「2年以内」の業務停止と定められていますが、具体的な期間等は定めがありません。
しかし、実際に懲戒をする際には、具体的な期間(たとえば3か月、1年6か月など)を設定して処分をすることになっています。
処分の始期は、具体的な処分の告知があった時点と考えられています。
3 業務停止期間中の登録取消し
業務停止期間中に弁護士の登録を取り消すことは可能とされており、その場合には業務停止の処分が当然に失効するとされています。
4 業務停止期間中にできないこと
それでは、具体的にどのような「業務」が停止されるのでしょうか。
⑴依頼者との委任契約
弁護士が業務停止となったとしても、依頼者との委任契約自体が当然に解除、失効するものではありません(委任契約書に記載があれば別論)。
そのため、業務停止の処分を受けても委任契約自体は存続していることになります。
⑵具体的な活動
ただし、仮に委任契約が存続していたとしても、弁護士としての業務(訴訟事件等の一般法律事務。定義は弁護士法3条1項)は停止されている状態にありますから、具体的な弁護活動はできません。
委任契約が存続しているので、義務はある一方、業務停止処分を受けていますから、債務不履行状態に陥っています。
なお、仮に業務停止期間中に弁護活動を行った場合には、そのこと自体が新たな懲戒事由となりますので、代理人・弁護人を辞任する等の措置をとる方が依頼者の方のためと言えます。
⑶官公署による委嘱
弁護士の職務として、「官公署の委嘱」によって行う法律事務が含まれます。たとえば国選弁護人や破産管財人、司法試験委員、人権擁護委員などが挙げられます。
このうち、国選弁護人や破産管財人など、法律事務を行うことが委嘱の内容となっているものについては、当然その職務を行うことができなくなりますので、委嘱した官公署は直ちに委嘱を取り消すべきです。ただ、この点についても、上記の委任契約と同様、業務停止処分を受けたからといって、特段の行為無しに委嘱が取り消されるものではありませんから、官公署による取消しが必要であると思われます。
次に、弁護士であることが委嘱の要件となっているものの、法律事務を内容としないようなものの場合(たとえば司法試験委員など)については、業務停止処分によって弁護士たる身分は喪失しないことから、委嘱を継続することも可能であると思われますが、業務停止を受けていること自体から弁護士としての見識の問題が生じていると言え、できる限り弁護士自身が辞任するか、委嘱の取消しをすべきであると言えます。
最後に、弁護士であることが委嘱の要件となっておらず、法律事務も含まれていない場合ですが、こちらも2番目の事例と同じように考えられるところですので、辞任等をする方がよいと思われます。
戒告
1 戒告
(1)戒告とは
戒告は、弁護士法第57条1項1号に定めがある処分で、懲戒処分の中では最も軽い
処分となっています。
(2)戒告による影響
業務停止以上と異なり、戒告を受けた場合であっても弁護士資格には一切影響を及ぼしません。
そのため、戒告後も通常通り弁護士活動を行うことができます。
ただ、戒告になった場合にはその処分が公告され、『自由と正義』に事案が掲載されるほか、官報に公告をされることになっています(弁護士法第64条の4)。ただし、弁護士としての資格には影響を与えない処分ですので、裁判所・検察庁への通知は行われません。
それ以外にも、日弁連の会長選挙の被選挙権を3年間失うことになっています。
2 戒告処分に対する不服申立て
戒告も懲戒の処分の1つですから、単位会が戒告の処分としたときには日弁連懲戒委員会への審査請求、日弁連が懲戒にしたときまたは審査請求が棄却されたときには東京高等裁判所へ取消訴訟を提起することができます。
戒告は弁護士の身分に影響を与えないものではありますが、訴えの利益がないということにはなりません。ただし、戒告は処分をした段階で執行が終了することになりますので、執行停止の申立てはできないと考えられています。